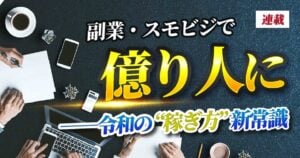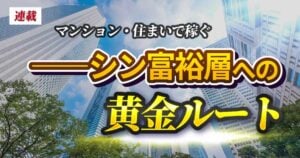手取りを増やしながら資産を育てる“最強の節税方法”を元メガバンク行員が告白「申請すれば払ったお金が戻ってくる制度」のカラクリとは

2024年から始まった新NISAは大きな注目を集める一方、「何から手をつければいいのか」と悩む投資初心者は少なくない。そうした中、初心者でも簡単に実践できる投資術をわかりやすく解説して支持を集めているのが、「バンクアカデミー」の小林亮平氏だ。
初心者が選ぶべき「ゴールデン銘柄」から、資産寿命を延ばす「新NISA出口戦略」の鉄則、さらには税金の一部が戻ってくる超お得な制度の全貌まで、同氏に詳しく解き明かしていただいた。全3回の第3回。
目次
手取りを増やしながら資産を育てる“究極の節税”
新NISAと並んでよく紹介されるのが個人型確定拠出年金、通称「iDeCo(イデコ)」です。これは私的年金制度の一種で、最大のメリットは掛け金(毎月積み立てるお金)が全額「所得控除」の対象になる点です。
所得控除とは、その年の所得から掛け金分を差し引ける仕組みのことで、結果的に所得税や住民税が安くなるという強力な節税効果があります。
ただし、iDeCoには注意点もあります。それは、原則として60歳になるまで資産を引き出すことができないという点です。また、NISAとは異なり、受け取る際に税金がかかる場合があり、出口の考え方が少し複雑になります。
「NISAとiDeCoはセットで」はもう古いのか
「新NISAとiDeCo、両方やったほうがいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。これに対する私の考えは、「基本的には、まず新NISAを優先すればOK」です。
というのも、以前のNISA制度は投資枠が小さかったため、iDeCoを併用する価値が非常に高かったのですが、新NISAは年間360万円まで投資できるようになったため、ほとんどの方の資産形成は新NISAだけで十分カバーできるようになったからです。
また、iDeCoは60歳まで引き出せないという流動性の低さや、受け取り時の税金の複雑さを考えると、いつでも引き出せて、いつ売却しても税金がかからない新NISAのほうが、シンプルで分かりやすく、万人におすすめできる制度だと言えます。
もちろん、「老後資金のためなら60歳まで引き出せなくても問題ない」「節税メリットを最大限に活用したい」という方であれば、iDeCoの活用も非常に有効な選択肢となります。
ふるさと納税を“ネットショッピング感覚”で始める方法
前回の記事で、使わないと損なお金の制度としてふるさと納税を挙げましたが、「ふるさと納税がお得なのは分かったけど、手続きが面倒くさそう……」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、実際のところ、ふるさと納税は驚くほど簡単に始めることができます。ここでは、3つのステップに分けて解説します。
ステップ1は、「ふるさと納税サイトで返礼品を選ぶ」。まずは「さとふる」や「ふるなび」、「楽天ふるさと納税」といった、ふるさと納税のポータルサイトにアクセスします。これらのサイトには、全国の自治体が提供する返礼品が、まるでネット通販サイトのようにズラリと並んでいます。
お米やお肉、海産物、フルーツといった食料品から、日用品、旅行券まで、様々なジャンルの返礼品がありますので、普段のネットショッピングと同じ感覚で、欲しいものを選んでみましょう。
ふるさと納税の恩恵を100%受け取るための必須ステップとは
ステップ2は、「サイト上で寄付(支払い)をする」。欲しい返礼品が見つかったら、そのままサイト上で寄付の手続きに進みます。支払いもクレジットカードなどで簡単に決済できるため、特別な手続きは必要ありません。ここまでは、ネット通販で商品を購入するのとほとんど同じです。
ステップ3は、「税金控除の手続きをする」。ふるさと納税でもっともハードルが高いと思われがちなのが、この税金控除の手続きです。本来は確定申告が必要なのですが、会社員の方であれば「ワンストップ特例制度」という簡単な手続きで済ませることができます(ただし年間の寄付先が5自治体以内であることなどの条件があります)。
この制度を利用する場合、寄付をした後に自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入し、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーを添えて、自治体に郵送するだけです。たったこれだけで、翌年の住民税から自動的に寄付額(-2,000円)が引かれるので、確定申告は不要になります。
このように、ふるさと納税は思った以上に手軽に始められます。まだの方はぜひチャレンジしてみてください。