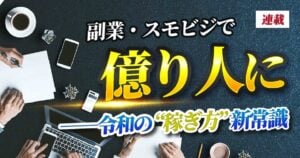賃貸利回り、ドバイは日本の約3倍…日本の富裕層が「海外不動産」に注目する理由

賃貸か、持ち家か。この永遠のテーマは、多くの人が一度は悩む大きな問題と言える。そんな質問に対し、海外不動産投資家・海外移住コンサルタントの宮脇さき氏は、「結論から言えば、どちらが絶対に正しいという答えはありません。ライフスタイル、家族構成、そして最も重要な『資産状況』によって、最適な選択は人それぞれ異なるからです」と話す。
一方で、将来に備えて資産を築きたいと考えているのであれば、「持ち家という選択肢は大変魅力的」と付け加える。
といっても、誰もがすぐに住宅を購入できるわけではない。では、一体どうすればいいのか。そこで宮脇氏が推奨するのが、「海外不動産」だ。持ち家がもたらすメリットや日本の不動産市場の現状を踏まえたうえで、海外不動産という新たな選択肢について考えてみましょう。全3回中の2回目。
※本稿は宮脇さき著『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意』(KADOKAWA) から抜粋、加筆修正したものです。
第1回:20代から始める「ヤドカリ投資」普通の会社員が億を築く資産形成
第3回:日本を脱出する裕福層たち……海外移住を決める3つの理由と人気の移住先とは
目次
日本の持ち家は「実需半分・投資半分」
日本の住宅ローンは超低金利で、税制優遇も手厚いため、持ち家は「実需半分・投資半分」という感覚で購入できる時代です。特に、都心のタワーマンションや好立地のブランドマンションなど、資産価値が落ちにくい物件を選べば、リスクを抑えつつ資産を形成できます。
過去の不動産市況を見ても、良い立地の物件を保有していた人が最終的に得をしているケースは圧倒的に多いのが現実です。ただし、すべての物件が資産性に優れているわけではありません。また、今の価格が2倍、3倍に跳ね上がるような急激な上昇は、今後はそう簡単には期待できないでしょう。
さらに、価値が上がる不動産は日本全体で見ればごく一部であり、都心部でも一部のタワーマンションに集中している傾向があります。なぜなら、タワーマンションは長期的に価値を維持しやすい「耐久消費財」としての側面が強いからです。
また、日本の不動産市場は国内の動向だけでなく、世界の経済状況にも左右されます。アメリカの金融政策や為替、株式、金利など、グローバルなトレンドに影響を受けるため、未来を正確に予測するのは非常に困難です。
だからこそ、「未来予測は絶対ではない」という認識を持つことが重要です。重要なのは、柔軟な姿勢で「間違ったら、早く修正する」ことです。
それでも、一つだけ確かなことがあります。それは、資本主義社会において、モノの価格は少しずつ上昇し続けるということです。賃貸でお金を払い続けるか、資産としての住まいに変えていくか。この違いが数十年後には驚くほどの資産格差を生む可能性があります。