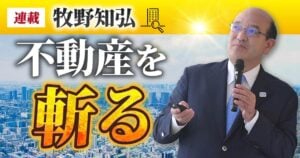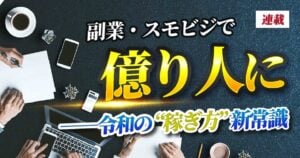米国株停滞の「利回り逆転」対策・・・著名投資家が教える日米ポートフォリオの勝ち筋

本稿で紹介している個別銘柄:エヌビディア(NVDA)
日経平均株価が堅調に推移する中で、日本株と米国株のどちらに投資すべきか、投資家の間で意見が分かれている。
それぞれの市場には独自の魅力があり、どちらが優れているとは一概には言えないのが実情。しかしながら、自身にはどちらの投資先が適しているのか知りたい人も多いだろう。
そこで今回は、『Financial Free College』(以下、FFC)の講師、松本侑氏(@smatsumo0802)にインタビュー。日米両株式市場のメリットとデメリットを比較し、各主要銘柄の動向をもとに、具体的にどのような銘柄に投資をするべきなのかについて話を伺った。インタビュー連載全2回の最終回。
目次
外国人投資家が主導する日本市場、今や米国株より強い
ーー日米株式相場の景況感の違い、市場参加者の変化、資金の流れ、主要銘柄の動向についてお聞かせください。
まず、現在の投資環境を概観すると、日本株の優位性を示す兆候がいくつかあります。
10月に発表された日銀短観(9月調査)のDI値は、大企業製造業でプラス14、大企業非製造業でプラス34と、全体として改善傾向が続いており、特に非製造業では高い水準を維持しています。
一方、米国の10月ISM景況指数は製造業が48.7、非製造業が52.4と、製造業は50を下回る状態が続いているものの、非製造業では景気拡大の兆しがより明確になってきました。
市場参加者の構造変化にも注目です。日本株市場では、外国人投資家の買いが変動的ですが、直近のデータ(10月第5週)では約3459億円の買い越しを記録しています。
これに対し、日本人投資家は売り越し傾向を示す場面もあり、外国人投資家の影響力が株価形成を強く主導しています。
8月のお盆休み期間中に日経平均が最高値を更新した背景にも、この外国人投資家の積極的な買い入れが大きく寄与していましたが、その流れは秋以降も継続していると言えますね。
ーーここまで外国人投資家が参入してくるようになったのは、いつ頃なのでしょうか。
はっきりとした起点はわかりませんが、2023年の東証によるPBR改善要請や、その後の累進配当、DOE導入などがきっかけで、現在は外国人主導の市場構造にシフトしています。
これにより、日本株は国内経済要因を超えた国際的なリスクヘッジ市場として機能している可能性が高いと考えています。
米国市場の変動に対する分散投資として、日本株が選ばれている状況がうかがえますね。