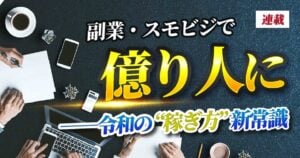値上げラッシュに打ち勝て! 最強”家計防衛”…「状況把握、共有、見直し、可視化」の極意

鬼すぎる円安で1世帯あたり6万円増
今や誰もが知る「お、ねだん以上~♪」のCM。価格と質にこだわる家具・日用品販売大手ニトリは、満足度と適正さを問い続け、客のハートをつかむことに成功してきた。だが、足元の原材料価格の高騰や急速な円安進行はその満足度を妨げ、国民は食料品や日用品でも「お値段、異常」と苦しむ。政府や日銀には是正に向けた動きはみられず、やり場のない怒りが込み上げるばかりだ。ならば、私たちの生活は自分たちで守るしかない。今、決行すべきは「家計防衛のカイゼン」だ。
総務省が6月24日発表した5月の全国消費者物価指数は、前年同月比2.1%増となった。指数が前年水準を上回るのは9カ月連続のことだ。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻などに伴う原材料価格の高騰や、24年ぶりの安値をつけた円安の進行が物価を押し上げる。
値上げは日用品や食料品にも波及し、庶民の味方である即席麺や外食チェーン、菓子類といったものまで値上げラッシュに加わった。帝国データバンクによれば、主要食品メーカーが2022年に計画する値上げは、5月末までに累計1万品目を突破。値上げ率の平均は10%を超える。ガソリンや電気代といったエネルギーは17.1%、生鮮食品を除く食料も2.7%上昇している。
円安基調は当面続くとみられ、原油高や円安が収まらなければ「再値上げ」が現実味を帯びる。民間調査会社のみずほリサーチ&テクノロジーズの試算によれば、エネルギーや食料品の価格上昇に伴い家計の支出は1世帯あたり平均で6万円程度の負担増になるという。
給与が上がらない日本と、上がる海外を一緒にするな
こうした中、日銀の黒田東彦総裁は6月6日の講演で「日本の家計が値上げを受け入れている」と発言し、庶民感覚とのズレを批判されている。欧米と比べれば、消費者物価の伸びが相対的に低いとの思いがあるのだろう。たしかに、5月の英国の消費者物価指数は前年同月比9.1%上昇。米国は8.6%、カナダも7.7%それぞれ伸び、いずれも40年ぶりの大幅な上昇を記録している。しかし、欧米主要国は日本と比べ実質賃金指数が高い。20年以上も国民の平均給与が上がらない国とは違うのである。
日用品や食料品の値上げが家計に与える影響は小さくない。このまま続いていけば、家計の節約志向は強まり、消費を下押しする。欧米の中央銀行やエコノミストには、世界経済が景気後退入りする確率は50%前後との声も目立つ。「消費への影響はますます深刻になってくる」(経済同友会の桜田謙悟代表幹事)と懸念する声は広がる一方だ。
政府や日銀が動かない中、庶民はどのように生活を守っていけば良いのか。ヒントになるのは、海外では「トヨタ式」としても知られる「カイゼン」である。生産性の向上に加え、組織の活性化やモチベーションアップにつながるといわれるものだ。
その基本的構成を簡単に言えば、「状況の把握」「目標の共有」「内容やプロセスの見直し」「効果の可視化」といったところだろう。これは値上げラッシュに苦しむ家計の防衛にも応用できる。