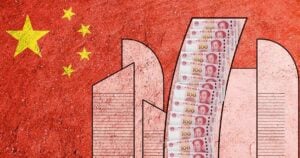米国の支えなしに独り立ちすることすら難しい日本…中国リスクと米国リスク「それぞれの現在地点」(三浦瑠麗)

国際政治学者三浦瑠麗氏の全3回短期集中連載「政界再編」。第3回のテーマは国際情勢だ。かつて国内政治を二分していた「対米自立派」と「同盟強化派」だが、三浦氏は「対米自立の選択肢はまったく現実的でないと見なされるようになった」と指摘する。またどっちつかずの中間層についても「ウクライナ侵攻によって明確に減少した」。三浦瑠麗氏が米中にはさまれる日本の未来を考えるーー。
目次
米国による恩恵とリスク
第二次世界大戦後、米国は国際経済秩序を主導して作り上げるとともに圧倒的な国力差を背景として自国市場を世界に開放してきた。とりわけ西側陣営諸国はその恩恵に大きく与った。戦後日本の焼け跡からの復興を奇跡に例え、日本人の勤勉さを称える言説をよく目にする。これはまことその通りなのであるが、ひとつ重要な背景事情を見落としている。米国が戦間期の過ちに学び、敗戦国を復興させつつ自らの秩序内に組み込むことを目指したという点である。「持たざる国」を困窮に追いやるような過ちは繰り返さない。欧州から日本にいたるまで、戦後復興は世界で最も豊かな米国市場に比較的自由なアクセスができたことに下支えされていた。
自由貿易体制とは、したがってそもそもが、国際秩序の安定と米国の国益にかなうために作られたものである。当然、その恩恵を受ける同盟諸国が米国の政策に付き従うこととセットであった。また、米国経済に余裕が乏しくなればアクセスには制限がもたらされるようになる。日本は70年代に繊維製品で、80年代以降は自動車や半導体関連分野において自主規制を課さざるをえなかった。恩恵とこうした制約は背中合わせのものだと理解していたからである。米国の国内法は、常に域外への適用可能性を秘めたものとして力を発揮してきたため、米国依存度の高い同盟国にとっては米国の意向と力の行使は警戒すべきリスクの一つだった。その観点から、日本がかつてイランとの間で独自外交を繰り広げることができたのは、ごく稀なケースであったと言える。