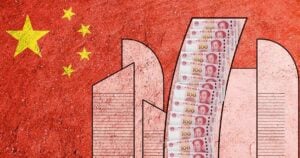中国政治学者「胡錦濤に認知症の疑い」…無敵の習近平が次に狙う「巨大企業経営者」たち

最高位の7人すべてが子分…ついに完成してしまった習近平独裁体制
世界の注目を集めた第20回中国共産党大会が終わった。習近平自体の続投は予想されていたため、焦点は、習に続く権力体制がどうなるかということだったが、結果は最高意思決定機関である共産党常務委員の7人のポストがすべて習近平に近い人物で占められた。だがこの結果に対しては、日本をはじめとした海外からと中国国内からでは、見える光景が大きく異なっているということを伝えておきたい。
まず海外からの視点では、そもそも習の前例のない3期目就任自体をネガティブに受けとめている。首脳人事でも透明性や公明正大さを求めるし、異なる意見を反映できる仕組みこそが政権運営のバランスを取り、政治の暴走を抑えるために必要だと考える。だから今回の党大会の結果に対する評価は、ある種の驚きと失望しかないだろう。なんといってもこれまで経済運営を担ってきた首相李克強はもちろん、次の首相の有力候補と目されてきた胡春華の名前さえ外されてしまったのだから。名実ともに、主要国ではロシアに次ぐ独裁国家になってしまったかのような人事だ。
一方、中国国内ではどのように受け止められているのか。残念ながら、いまの中国では、人々の政治に対する関心が極めて低い。もっとも日本人を見ても政治に関心がある人ばかりではないので、あまり変わらないのかもしれないが、ともかく多くの中国人は自分たちの生活が良くなっていくのなら、政治家は誰でもいいとさえ思っている。今回の党大会でも、北京の街は「偉大なる習近平」といったふた昔前のようなスローガンがあふれていたようだが、それに乗せられている人も反対する人も多くはない。
世界経済を大混乱させた上海ロックダウンにしても、当事者の上海市民は別にして、それ以外の地域に住む中国人にとっては、ネットやSNSも当局の都合で遮断され、正確な情報などは何も伝わらず、ほとんど他人事のようなものだ。だから外からいくら習近平の愚策を嘆いたところで、多くの中国国民には事の重大さが理解されていないだろう。
一方、今回の党大会の結果に、最も戦々恐々としているのは民間企業の経営者、といっても中小企業の経営者ではなく大企業の経営者たちだろう。具体的には、ご存じのように、アリババやテンセント、バイドゥといった企業の経営者たちだ。客観的に見れば、今回の党大会の人事は、これから国家統制の経済へ進むというメッセージを発信したのと同じことだから、彼らはかなり動揺しているのではないか。
毛沢東をしのぐ独裁体制…いまの習近平の心境は「勝者総取り」
ともあれ、今回の党大会を見て私が思うのは、習近平が「自分の目的を達成するためにはルールを無視してもいいと思っている」ことを世界に示した、ということだ。言うまでもないことだが、グローバリゼーションの社会では、たとえ為政者であってもルールを破ることは許されない。こうまであからさまに反対意見が出る心配がない “お友達内閣” をつくったのは、中国の建国以来、初めてのことだろう。私が想像するに、いまの習近平は「ウィナー・テイク・オール」の状況だ。自分への批判は許さない。全員一致内閣をつくり、異論を排除して、自分がやりたいことをすべてやってやる――。こんな心境なのではないだろうか。
上海ロックダウンを強行し、世界中から批判された李強を首相にするという人事などはその最たる例だが、これまでほとんど実績がないような人物を要職に選び、自分の意のままに政権運営を行わせようというのだから、極めて危険な方向に進んでいると言わざるを得ない。
過去を振り返っても、鄧小平には陳雲や李先念といった、配慮しなければならない長老の存在があった。あの毛沢東にしても、周囲には劉少奇や彭徳懐、林彪など共産党革命世代の英雄たちが複数存在した。それによって、凄惨な権力闘争が起こり、文化大革命の悪夢に繋がったことも事実だが、政権発足時に、ここまで個人でやりたいことができる政治体制を築いたことは中国共産党の歴史上、一度もなかった。
長老と言えば、共産党大会の最終日に、習近平の横に座っていた前・総書記の胡錦濤が途中で退出した場面が西側メディアで報道され、話題や憶測を呼んだ。胡錦濤には認知症のうわさがあり、新華社が報じた通り、本当に体調不良で退席したとしても不思議ではない。だが、私があの場面を見て思ったのは、習近平のあまりにも不自然で冷たい態度だ。常識で考えれば、体調を崩した前任者を気遣って見送るのが筋だろう。
いくつかの報道であった、「その後の人事を妨害されないために強制的に排除したのでは」という意見には、実際の人事は夏の北戴河会議で決定していただろうから違うと思うが、それにしても不自然だった。真相はやぶの中だが、西側メディアが今回の人事を象徴したできごとと報道するのも理解できなくはない。
そもそもなぜ、習近平が中国で権力を確立することができたのか
そもそもなぜ、習近平がここまで権力基盤を強固にできたのだろうか。総書記に就任前の習近平に会ったことがある人が口をそろえて言うのは、「おっとりとした性格で、物静か。とても人に脅威を与えるようなタイプには見えなかった」ということだ。しかも習の父親、習仲勲は、文化大革命の弾圧を経て、党中央政治局委員にまで上り詰めた人物で、その人柄の良さでも知られ、周囲から尊敬されていた。そうした背景もあって、習の内面を知らなかった周囲が、まんまと騙(だま)されてしまったのかもしれない。
習の本当の人柄が垣間見えるエピソードがある。習には浙江省時代に省トップに抜擢してもらった恩人とでも言える長老がいた。毛沢東の元秘書で、習仲勲同様に文化大革命で迫害を受けながら後に復権した李鋭という人物だ。
アメリカに移住している李鋭の娘、李南央氏が米メディアのインタビューに答えたところによると、李鋭は後に「習近平を推薦したことは、私の生涯最大の過ちだ」と悔やんでいたそうだ。というのも海外人脈の豊富な李鋭が、中国軍の近代化のために、最先端の科学技術者を紹介したいと習近平に書簡を送ったところ、完全に無視されてしまったそうだ。長老だからと言って、必ずしも従う必要はないのだが、恩人に最低限の礼を尽くすのは人間として当然のことではないか。党大会での胡錦濤への態度にも通じることだが、一度権力を手中にしてしまえば、恩人だろうが何だろうが、冷たく突き放すという、習の冷酷さを証明していると言えるのではないか。
多くの日本人は、あまり実感できないだろうが、近現代の中国の指導者は、多かれ少なかれ裏の顔と表の顔を併せ持っていたものだ。日本では人気があった周恩来でさえも、そうした一面があった。二面性を併せ持つ指導者の典型は、言うまでもなく毛沢東だ。「人民の味方」然として、多くの若者や大衆を扇動しておきながら、大躍進や文化大革命などの悲劇を起し、死ぬまで権力を放そうとしなかった。いま、習近平の姿を毛沢東に重ねる見方が増えてきたが、独裁志向を隠さなくなった彼を見る限り、その見方は否定できないだろう。
共産党独裁の特権階級が存在する限り「共同富裕」は実現しない
いずれにせよ、今回の党大会の結果を見るにつけ、私が思うのは、習近平の言っていることは矛盾だらけだ、ということだ。まず台湾に対しては平和的な統一を目指すと言うが、このように強権を強めていけば、台湾の人々の心が離れるだけだ。「製造強国」を目指すと言うが、国内でグーグルにすらアクセスできない状態では、世界最先端のイノベーションを目指すことなどできるわけがない。貧富の差を無くして皆が豊かになるという「共同富裕」は習近平肝煎りの政策だと言われているが、これなどは毛沢東時代のスローガンと同じで、完全にプロパガンダそのものだ。共産主義は誰でも最低限の暮らしができるという前提があるはずだが、今の中国では社会保障制度すらろくに整備されていない。
なぜなのか。共産党の幹部の特権があるからだ。時折、地方視察などの際に共産党の要人たちが市場で庶民と触れ合っている場面が報道されるが、もちろんあれは宣伝に過ぎない。彼らは私生活では庶民とは隔絶されていて、生活に関する費用はすべて公費でまかなうために自己負担はゼロ。もちろん、スーパーなどで買い物をすることもない。例えば共産党の高級幹部が普段、車で移動するときには、周囲を徹底的に交通規制して、彼らの車が通る信号をすべて青信号にして最優先に通す。日本では総理大臣でもそのようなことはしないだろう。
だから、彼らには庶民の苦しみなどは絶対に理解できない。極論を言えば、こうした共産党の独裁体制が続く限り、「共同富裕」は実現しない。皆を豊かにするためには、共産主義を捨てて、様々な意見をぶつけ合うことができる民主主義の政治体制にするしかないのだ。
政権内での権力基盤は、かつてないほど強固になった習近平だが、だからといって今後、中国14億人の心を治めることができるかどうかは別問題だ。いくら政治に関心が薄いと言っても、自分たちの生活が苦しくなってくれば、そうも言っていられなくなる。経済政策に全く実績のない “お友達内閣” で、果たして正しい経済運営ができるのだろうか。
こうした表現は使いたくないのだが、周りがイエスマンばかりで固められ、習近平の独裁色が強まる次の5年間は、中国の歴史の「終わりの始まり」かもしれない。ここで言う中国が、中国共産党のことを指しているのならまだ救いがあるのだが。