「トランプ関税は単なる貿易問題ではない」識者がみる相互関税の“真の狙い”…米国への投資80兆円の正体と、トランプ政権がやりたいこと
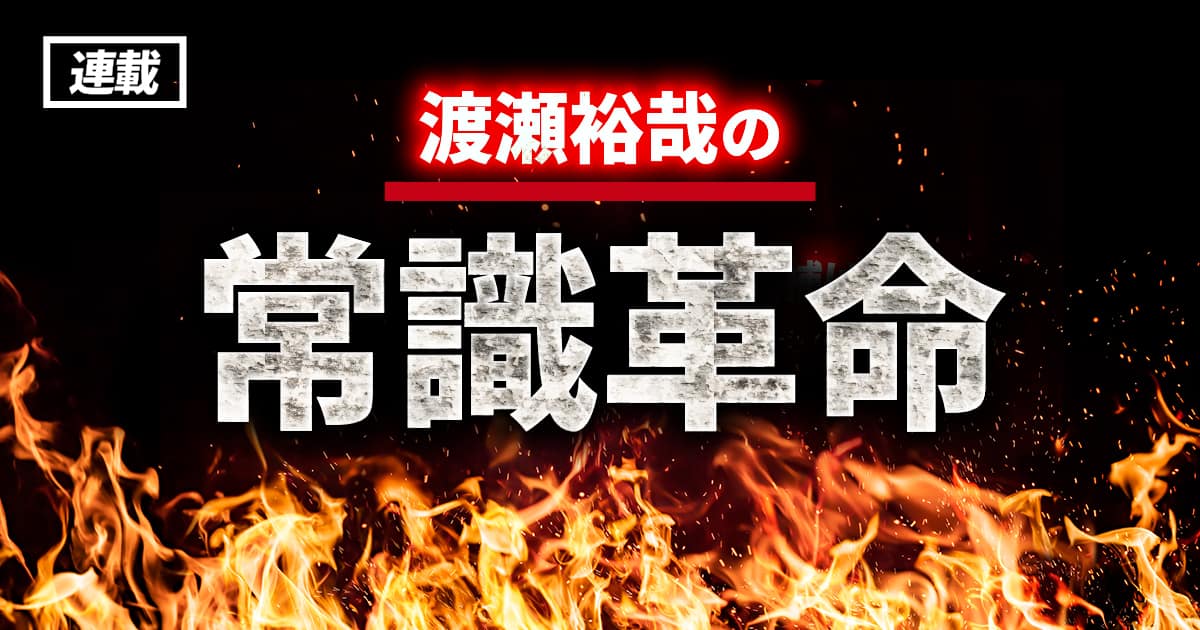
米トランプ政権は8月7日、「相互関税」を発動させた。その税率については、日本だけでなく、いまだに世界各国と米国間で認識の食い違いが相次いでいる。
では、そもそも、トランプ大統領は何がしたいのか。かつて第一次トランプ政権の誕生を見事に言い当てたこともあり、米国政治への造詣が深い国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏が解説するーー。
目次
「トランプ関税」のアイデアはどこからきたのか
第二次トランプ政権の関税政策が目指すものは何か。この問題を深堀するためには多角的な視座が必要となる。特に米国の覇権維持という観点からしっかりと捉え直すことが重要だ。
そもそも「相互関税」という単語は、現在ホワイトハウスの顧問となっているピーター・ナヴァロ氏の発案によるものだ。ナヴァロ氏は著作の中で貿易の不均衡に対する問題を指摘し、それを解消するための関税を相互関税であると明言している。米国と世界各国の貿易がフェアな条件となれば、米国の貿易赤字は各国に対して10%減少するというのが同氏の持論だ。おそらく現在のベースラインとなっている一律10%関税はこの発想を援用したものであろうことが推測される。さらに、トランプ大統領は世界各国が十分な対応ができないことを見越し、関税政策を公然と貿易問題以外の外交政策を変更するためのツールとして用いるようになっている。
米国側は「してやったり」だった関税交渉
まず関税については一律15%(石破政権とトランプ政権間で齟齬があるとしても)という内容が公表された。これは相互関税に関わる部分の交渉の結果と言えるだろう。
相互関税が本当に日本側の既報通りであれば、事前に予測された範囲内であるし、米国側が日本に対しての関税率を何も修正しなければ、「合意文書を作らなかった日本側が間抜け」というだけの話だ。今回のケースではいつでも態度を翻せる強者を拘束するために大義名分として合意文書が必要である。少なくとも筆者が米国側なら「してやったり」と思っているだろう。
「セクター別関税」こそが、トランプ関税交渉の本丸である理由
それはともかく、今回の交渉の本質はセクター別関税のほうにある。自動車等のセクター別関税については一旦問題が収束したように見えるが、半導体や医薬品などの関税問題はいまだに燻ったままとなっている。これらセクター別関税は何時ひっくり返るか分からない上での極めて緩い合意に過ぎない。なぜなら、こちらこそがトランプ政権の関税交渉の本丸だからだ。
ナヴァロ氏は中国とのデカップリングを事実上主張しており、米国の軍事産業等のサプライチェーンの見直しを訴えている。実際、現在までの米中の関税の引き上げ合戦の顛末に鑑み、米中の貿易はあらゆる面で深く結びついており、高関税を単純にかければ良いという次元のものではないことが確認された。特に中国の影響力を完全に排除するためには、同盟国も含めた軍事産業のサプライチェーンの見直しを図るセクター別関税の重要性は見過ごすことはできない。














