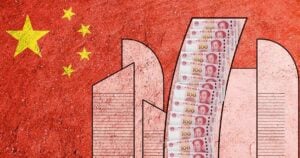中国の若年層失業率は18.9%に跳ね上がった…不動産バブル崩壊で実質ゼロ成長に陥ったとみられる中国経済の暗すぎる将来展望

一時的には世界の覇権を取るかとみられていた中国だが、不動産バブル崩壊や最近の低成長によって翳りが見えている。今後、中国経済はどうなっていくのか。
東京財団政策研究所・主席研究員の柯隆(かりゅう)氏は「中国経済を展望すると、簡単には成長軌道に戻れそうにない」と分析するーー。みんかぶプレミアム特集「資本主義は人を幸せにできるのか」第4回。
目次
中国の若年層失業率は18.9%に跳ね上がった…政府の公式統計は必ずしも中国経済の実態を示していない
目下の中国経済がいったい何パーセント成長しているかについて、おそらく習近平主席もわかっていないと思われる。中国政府は5%を2025年の成長目標として掲げているが、中国経済の内実をみて、今年は5%成長を実現できそうにない。
オーソドックスな経済分析では、経済成長の原動力について、個人消費、投資と純輸出(輸出-輸入)をそれぞれ検証するが、8月、若年層失業率は18.9%に跳ね上がり、消費(小売上高)は3.4%、不動産投資は-12.9%、といずれの指標も5%成長を支えるほどよくない。付言しておきたいことだが、中国政府が公表している公式統計は必ずしも中国経済の実態を示していない。
スタンフォード大学の許成剛教授「中国の実際の経済成長率は政府の公式統計を3ポイント引いたレベルが実体に近い」
中国国内のアナリストでSDIC証券のチーフエコノミスト高善文氏は「これまでの数年間、中国経済規模が1割ほど過大評価されている」と指摘している。中国政府の公式統計では、2024年の経済成長率は当初の目標通り、5%だったと発表されている。高氏は「実際の成長率は3-4%しかなかった」と指摘している。
そして、スタンフォード大学の許成剛教授(経済学)は「中国の実際の経済成長率は政府の公式統計を3ポイント引いたレベルが実体に近い」と分析している。許教授の分析でいけば、2024年、中国政府の公式統計は5%だったが、実際は2%程度の成長だったということになる。
米国シンクタンクRhodium Groupの分析によれば、2024年の中国経済成長率は2.4%-2.8%だったといわれている。三者の見方に多少の違いがあるが、いずれも中国政府の公式統計を大きく下回る値になっている。要するに、2024年の中国経済は5%成長を実現していないということである。
2025年の中国経済は政府目標を達成できるか
答えはノーである。まず、8月の消費者物価指数は-0.4%だった。製造業のPMIは50を下回り、49.4だった。この公式統計をみても、中国経済はすでにデフレ状態に陥っており、瞬間風速でいえば、ゼロ成長に近いと判断される。
仮に5%に近い成長が事実だとすれば、若年層失業率が二けたになることはない。同時に中国社会の高齢化は日本以上にスピードが速い。年金と健康保険などの社会保障制度が十分に整備されていないなか、個人消費が伸びにくい。将来に関する不安と足元の就職難は個人消費の拡大を妨げている。個人消費が伸びないため、企業の設備投資も不動産関連投資も委縮してしまっている。それにトランプ関税戦争により、輸出製造企業の業績も急速に悪化している。これでは、中国経済は成長できない。
中国経済はコロナ禍後遺症、不動産不況の長期化とトランプ関税戦争の三重苦に悩まされている
論点を整理すれば、目下の中国経済はコロナ禍後遺症、不動産不況の長期化とトランプ関税戦争の三重苦に悩まされている。そのいずれもかなり長期にわたって中国経済に伸し掛かり、今のところ、中国経済が成長軌道に回帰する兆しはみえていない。
具体的にみてみよう。コロナ禍の3年間、中国政府は厳格な都市封鎖政策(ロックダウン)を実施したため、たくさんの飲食店やスーパーなどが閉店した。これらのサービス企業の多くはいまだに回復していない。2021年、大手不動産デベロッパーの恒大集団はデフォルト(債務不履行)を起こしてしまった。2025年8月、恒大集団は香港証券取引所での上場が廃止となり、正式に倒産した。不動産市況をみると、売れ残りの物件、未完成の物件、ローンの返済が滞って裁判所に差し押さえられた競売物件などの在庫は買い手がつかず、たくさん残っている。だからこそ不動産関連投資伸び率は二けたのマイナスになっている。こうしたなかで、トランプ関税戦争は中国の輸出製造業にとってまさに青天の霹靂である。8月、中国の対米輸出は前年同期比33%減少してしまった。
中国独特のビジネスサイクルとその最大の弊害
デフレ経済の特徴は縮小均衡である。習近平政権にとっていかにして縮小均衡に陥った中国経済を拡大均衡に戻すかという課題に直面している。中国にとって参考になるのは日本の「失われた30年」の経験だが、状況的に違う点に気を付ける必要がある。「失われた30年」の日本はもっぱら需要を喚起するための金融緩和政策と財政出動だった。しかし、それでも消費者の期待値を変えるのに時間がかかった。結果的にGDPの2倍以上の国債を発行してしまい、国の債務比率が急上昇した。
それに対して、習近平政権はサプライサイドに注目して、家電や自動車などの買い替えを促進する政策を実施している。結局、その補助金は生産者側に行き、家計の購買力が強化されていない。何よりも、若年層失業率が跳ね上がっているため、家計の購買力は依然弱いうえ、人々の消費マインドが高まっていない。
こうしたなかで、中国独特のビジネスサイクルは問題になっている。