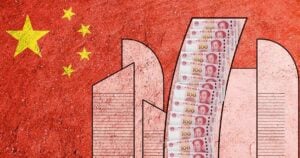橘玲氏が語るリベラルの「資本主義批判」が根本的に間違っているワケ いまだに“資本家vs.労働者”の構図で語る左派の残念すぎる時代錯誤

「資本主義が格差を拡大させる」――。こうした批判は後を絶たないが、そもそも「資本主義」とは何かを明確に定義できるだろうか。作家の橘玲氏は、多くの議論、特にリベラル派による批判は、マルクスが見た19世紀の「産業資本制」のイメージに囚われた時代錯誤なものだと断じる。
現代の格差の本質は国内の「階級」ではなく、生まれた国で人生が左右される「場所」にあると語る同氏に、複雑な現代を生き抜くための思考法とサバイバル術を伺った。全3回の第1回。みんかぶプレミアム特集「資本主義は人を幸せにできるのか」第5回。
目次
なぜリベラルは「資本主義」を正しく議論できないのか
誰もが「資本主義」という言葉を実に気軽に口にします。資本主義のせいで格差が広がり、社会が歪んでいる。資本主義は悪だ――。しかし、そもそも「資本主義とは何か」と問われて、明確に答えられる人はどれほどいるでしょうか。実は、「資本主義」の定義は人によってバラバラで、漠然としたイメージだけが先行しているのが現状です。
議論を始める前に、まず言葉の定義を整理しておきましょう。なぜなら「資本主義(キャピタリズム)」が「イズム(-ism)」つまり思想や主義だという誤解が、さまざまな混乱を生む原因になっているからです。
この言葉が生まれたのは19世紀半ばで、マルクス主義者(マルキシスト)や共産主義者(コミュニスト)が、自分たちの戦うべき敵として名付けたのが始まりとされます。彼らは「コミュニズム」という理想の社会像(思想)を持っており、それと対立する既存の体制を「キャピタリズム」と呼んだのです。
左派が雰囲気で批判する「資本主義」の実態
しかし冷静に考えてみれば、「資本主義」という思想やそのイデオローグは存在しません。共産主義のように「こういう社会を作ろう」という設計図があるわけではないのです。それは思想というより経済の仕組み、すなわち「経済制度」ですから、「資本主義」ではなく「資本制」と呼ぶのが正しいと考えています。
では、「資本制」における「資本」とは何でしょうか。私はこれを「お金を生み出す原資」と定義しています。この視点に立つと、現代社会が直面している問題の本質が、よりクリアに見えてくるはずです。今回は、この「資本制」が歴史の中でどのように姿を変えてきたのかを紐解きながら、私たちが今どこに立っているのか、そしてこれからどこへ向かうのかを考えていきたいと思います。
誰も指摘しない資本主義の“本当の”起源とは
「資本とは、お金を生み出す原資である」。この定義に従って人類の歴史を振り返ると、資本制が大きく4つのフェーズを経て変化してきたことがわかります。
最初の資本制は、紀元前7000年頃にメソポタミアで農業が始まり、最初の都市国家が成立したときに誕生しました。この時代、お金(富)を生み出す原資は、まぎれもなく「土地」でした。肥沃な土地を多く所有し、そこで作物を育てることで富が生まれる。
それ以降、古今東西、土地を所有する者、すなわち王侯貴族が最も裕福で、絶対的な権力を持っていました。彼らは土地を支配し、農民を働かせ、そこから上がる収益(税)によって豊かさを維持していたのです。この「土地資本制」は、数千年という長きにわたって人類社会の基本構造であり続けました。
15世紀にヨーロッパで始まった大航海時代では、貿易によって富を得る商業資本家が台頭しましたが、それにしてもアフリカから奴隷を新大陸に「輸出」し、プランテーションでサトウキビや綿花を栽培させていたのですから、土地資本制の亜種と見なせるでしょう。
人類はいかにして“土地の呪縛”から解放されたのか
この長大な土地資本制の歴史に終止符を打ったのが、17世紀のイギリスで始まった産業革命です。テクノロジーのイノベーションによって、人類は初めて「土地以外のもの」から利益を生み出す方法を発見しました。それが工場や機械などの「産業資本」です。
これは人類史における巨大なパラダイム転換でした。それまで土地に縛り付けられていた農民は、都市に流入し、工場で働く「労働者」へと姿を変えました。そして、工場を所有する「資本家」という新しい階級が、王侯貴族に代わる社会・経済の支配者として登場したのです。
カール・マルクスが分析し、私たちが「資本主義」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、まさにこの「産業資本制」の時代です。そこには「搾取する資本家」と「搾取される労働者」という、分かりやすい二項対立の構図がありました。チャールズ・チャップリンの映画『モダン・タイムス』で描かれたような、労働者が機械の部品のように扱われる世界観です。
豊かになったはずの世界で再び格差が広がったワケ
しかし、この単純な「資本家 vs 労働者」という構図は、マルクスが『資本論』を発表した19世紀後半にはすでに変わりはじめていました。とりわけ第二次世界大戦後、先進国で目覚ましい経済成長が起こり、社会全体が豊かになると、日々の生活に事欠くような労働者は減少し、自己実現を目指す「ブルジョア」的な中間層に変わっていきます。企業の経営者も、かつての独裁的な資本家というよりは、部下よりも必死に働く「高級労働者」のようになっていきました。
そして、経済成長と共にお金が市場に溢れるようになると、そのお金自体を管理し、運用することで利益を生み出す金融機関が巨大化していきます。こうして、お金がさらにお金を生む「金融資本制」の時代が到来しました。これが1980年代頃からの大きな変化です。
このフェーズでは、富の源泉は工場ではなく「金融資本」そのものです。たくさんのお金を運用する者が、経済の頂点に立つ。その結果、先進国では、産業資本制の中でそれなりに豊かな生活を送っていたプチブル的な労働者層のうち、低学歴の工場労働者などがグローバルな知識社会から脱落し始め、再び格差が拡大していくことになりました。
いまだに「資本家 vs. 労働者」の構図で語るリベラルの時代錯誤
そして今、私たちは新たなフェーズへの移行期にいます。