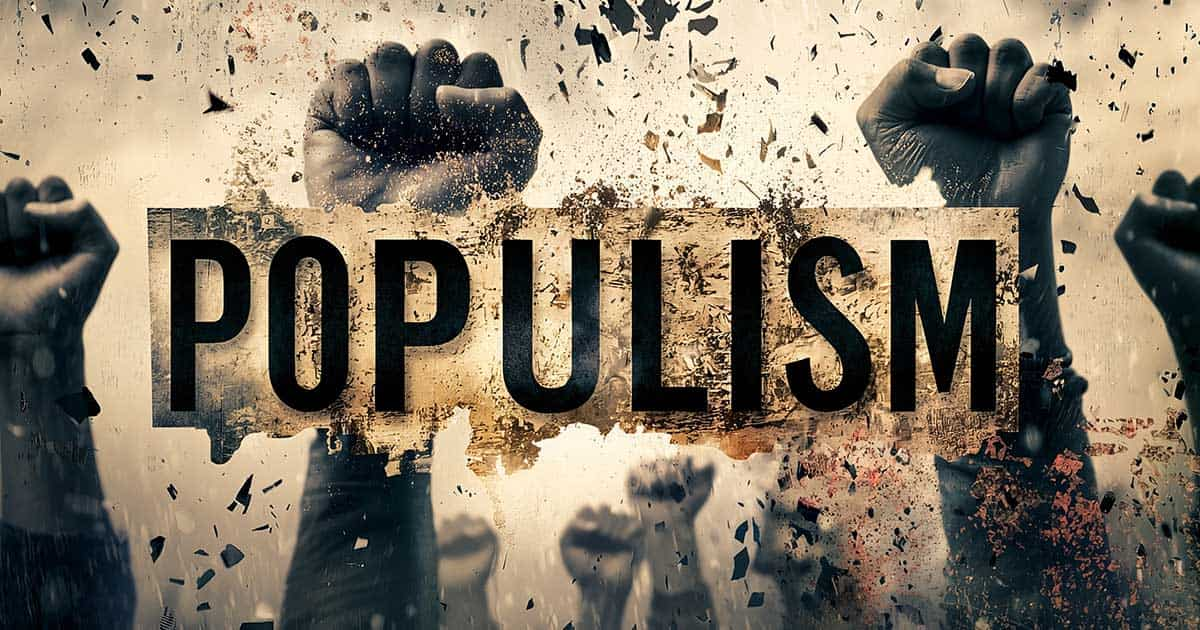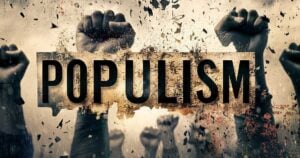上から目線な日本のリベラルが陥った「致命的な偏り」とは…国民の税金が富裕層の“エコカー”に消えているおかしな現状

なぜ、これほど懸命に働いても私たちの生活は楽にならず、社会は閉塞感に覆われているのか。多くの人が「意味のない仕事」に疲弊する一方、物価や不動産価格は高騰し、将来への不安は増すばかりだ。経済思想家の斎藤幸平氏は、この「静かな絶望」の根源は、経済成長を至上命題とする現代資本主義の構造的欠陥そのものにあると指摘する。
社会に不可欠な仕事ほど低賃金である一方、一部の富裕層による投機的なマネーゲームが社会のリソースを独占してしまうのはなぜなのか。なぜ人々の不満は根本的なシステム批判に向かわず、自己責任論や排外主義に吸収されてしまうのか。同氏に詳しく話を伺った。全3回の第3回。みんかぶプレミアム特集「資本主義は人を幸せにできるのか」第10回。
目次
いま杉並区で起きている“静かな変化”とは
では、具体的にどうすれば「脱成長」へと社会を転換していけるのでしょうか。その鍵は、国家レベルの大きな変革を待つだけでなく、私たちの足元から「コモン(社会の共有財産)」を再生していく実践にあります。
その好例が、東京都杉並区の岸本聡子区長の取り組みです。彼女はヨーロッパの国際NGOで、水道事業の民営化などによって引き起こされた問題に向き合い、市民の手にコモンを取り戻す活動に携わってきた経験を持ちます。杉並区長に就任して以来、彼女は「区民参加型予算」を導入しました。これは、予算の一部について、区民自身が使い道を議論し、投票によって決定するという画期的な試みです。自分たちが払った税金が、自分たちの意思で、自分たちのために使われる。この納得感が、政治への信頼を取り戻す第一歩となります。
富裕層の「やりたい放題」をこのまま許していいのか
杉並区のみならず、例えば世田谷区では、新しい公園のあり方を市民を交えて議論するような試みも始まっています。また、下北沢の再開発でも、区、事業者の小田急電鉄と住民がそろって参加する「デザイン会議」や、ワークショップを行って、高層ビルを乱立させない道が実現されました。
自分たちの住む街や地域を、金儲けの対象ではなく「自分たちのもの」として捉え直し、その管理に主体的に関わっていくこと。こうしたローカルなイニシアチブが、少しずつですが日本各地で生まれつつあります。
これらの小さな動きがネットワークで結びついていくとき、それは大きな社会変革の力となり得ます。私が著書でも紹介したスペインのバルセロナでは、市民運動を母体とする地域政党が市政を担い、住宅問題やエネルギー問題に市民本位で取り組むという大きな変革を成し遂げました。日本でも、こうしたボトムアップの変革は決して不可能ではないはずです。
日本のリベラルが陥った“致命的な偏り”
最後に、日本の左派勢力が復権し、社会のオルタナティブを力強く提示していくために、どのようなアジェンダが必要かについて考えてみたいと思います。
左派・リベラルが掲げるべき旗として、「再分配」と「承認」という二つの軸が指摘されることがあります。「承認」とは、LGBTQの人々の権利や、人種・ジェンダーによる差別をなくすといった、個人の尊厳に関わる問題です。一方で、「再分配」とは、経済的な格差を是正し、誰もが人間らしい生活を送れるように富を分け合う問題です。
この二つは、車の両輪のようにどちらも不可欠です。再分配はされているけれど、マイノリティが差別される社会は間違っていますし、その逆もまた然りです。
しかし、近年の日本のリベラルは、どちらかといえば「承認」の問題に重点を置きがちで、それが一部から「金持ちの余裕のある人たちが人権問題を語っている」といった「バラモン左翼」的な批判を招く一因にもなっていました。