「玉木る」と言われ人気ガタ落ち国民民主と「減税潰しの維新の高笑い」…左派的ポピュリズムを始めた高市政権が日本経済を潰しにかかる
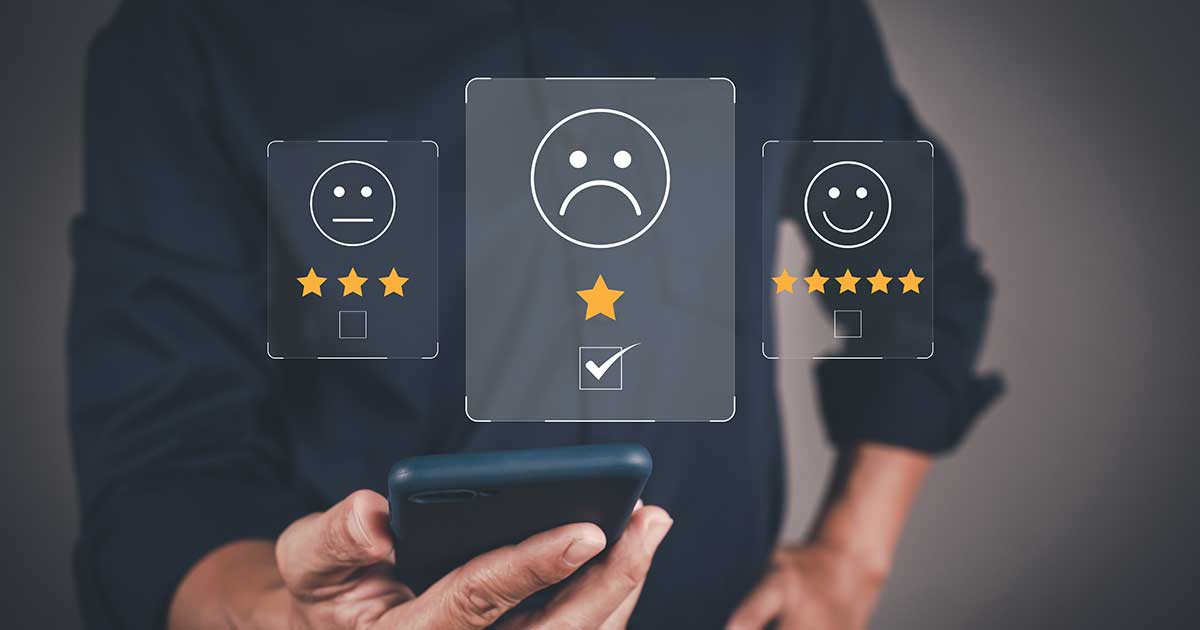
一時は玉木雄一郎総理の誕生かなどともてはやされたが、結局連立与党入りすることも、立憲民主党と合意することもできなかった国民民主党。代表の優柔不断を揶揄して、ネットでは「玉木る」という言葉も一部で使われたようだ。この問題に関して経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説するーー。
高市首相の解説本を発売しました!
目次
玉木も反応したネットの「玉木る」という言葉
一本の記事が、書いた人間の手を離れ、思わぬ旅をすることがある。先日公開した私の論考<「玉木る」とまでいわれ…評判ガタ落ち国民民主と維新の高笑い!化けの皮がはがれる「口先だけの改革派」国民の生活に直結する減税策>が、まさにそうであった。政局の渦中にいた国民民主党の玉木雄一郎代表、本人から直々に言及があったのである。
玉木氏がSNSで記した「タイトルだけ見ると、また私をディスる記事かと思いきや、国民民主党の経済政策への期待の記事でした」という一文に、逆風の中に立つ政治家の複雑な心情が滲む。この記事で問いたかったのは、玉木雄一郎という個人の評価ではない。国民民主党が掲げた政策という珠玉の輝きと、その輝きを無慈悲に踏み潰した者たちの罪、そして日本政治が失った計り知れない機会についてであった。その意図が、少なくとも当事者には届いた。この事実を起点として、もう一度、あの政局の嵐が何であったのかを、より深く掘り下げてみたい。
永田町を駆け巡った権力闘争は、高市早苗首相の誕生と、日本維新の会との閣外協力という形で一応の決着を見た。この目まぐるしい椅子取りゲームのなかで、国民民主党代表、玉木雄一郎氏の評判は地に墜ちた。数日前まで政権の鍵を握る男として脚光を浴びていた人物が、電光石火の自民・維新合意によって、一瞬にして「蚊帳の外」へと追いやられた。メディアの前で「二枚舌みたいな感じで扱われて残念」と悔しさをにじませる姿は、敗者のそれであった。そして、SNSでは彼の逡巡を嘲笑うかのように、「玉木る」という不名誉な俗語まで生み出された。
しかし、この「玉木る」という現象は、本当に玉木代表一人の優柔不断さが原因だったのだろうか。事実は異なる。この言葉の背後には、政治家として最も重要な信義を欠いた、日本維新の会の背信行為が存在する。資料を紐解けば明らかだが、維新は当初、野党連携のテーブルに着き、国民民主党と共に自民党と対峙する姿勢を見せていた。
減税策は、他のどの政党の主張よりも具体的
玉木代表が自民党との連携に踏み切れないでいる間に、水面下で高市陣営と密約を交わし、最後には国民民主党を置き去りにして権力の甘い蜜にありついた。これは、ただの駆け引きの巧みさなどではない。共に戦うと見せかけた相手を、自らの利益のためにためらいなく切り捨てる裏切りである。玉木代表が「蚊帳の外」にいたのではなく、維新が玉木代表を「蚊帳の外」へと突き飛ばしたのだ。「玉木る」という言葉は、本来ならば、信義にもとる行動で他者を陥れる維新の振る舞いをこそ指すべきであった。
この一連の騒動で失われたのは、一人の政治家の評判だけではない。もっと重大な、国民生活を豊かにするはずだった政策という名の希望が、党利党略の犠牲になった。国民民主党が掲げてきた経済政策には、特筆すべき価値があった。特に、国民の財布に直接響く減税策は、他のどの政党の主張よりも具体的で、地に足の着いたものであった。













