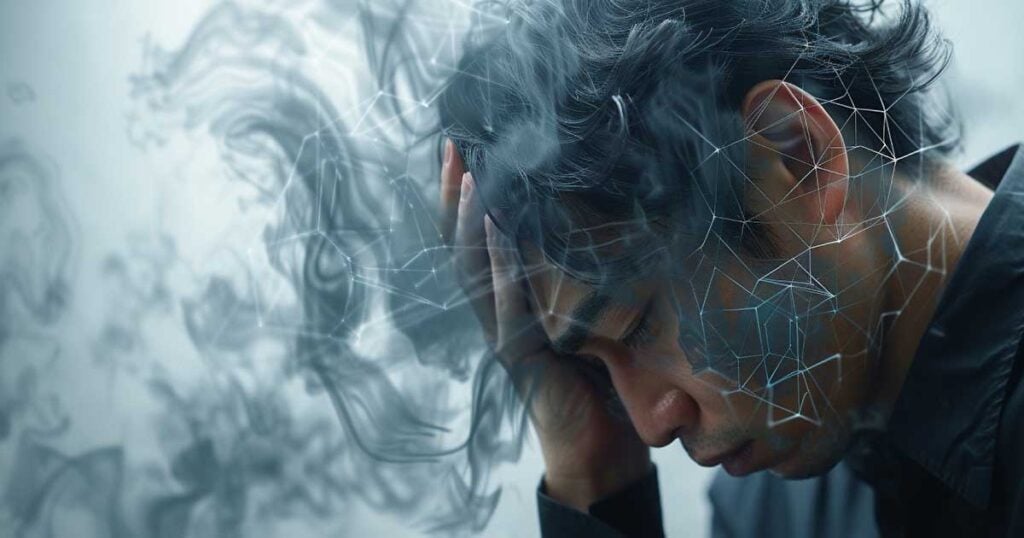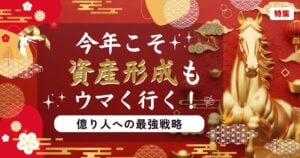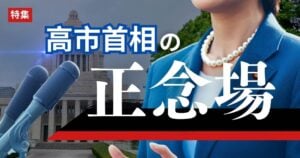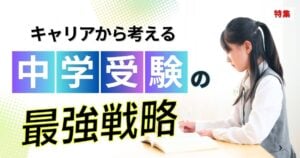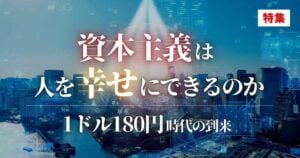みんかぶプレミアム特集「格差社会サバイバル」

都内のマンションはもう一般サラリーマン家庭では手が届かなくなるほど価格が高騰してしまった。そうしたマンションを現金一括で購入できる超富裕層もいれば、学校の給食費や家賃の支払いすらままならない家庭もある。とうとう、日本は本格的な格差社会に突入したのだ。
みんかぶプレミアム特集「格差社会サバイバル」では、この残酷な社会を生き抜くための知恵を識者たちに授けていただいたーー。
#1 「極貧生活→資産35億円」のニート投資家が語る“人生逆転マニュアル”の全貌 お金が勝手に増えてしまうヤバい行動戦略…小金持ちと資産数十億円の大金持ちとの決定的違い(マサニー)7/21
▼働かなくても総資産が35億円に お金が勝手に増えてしまうヤバい行動戦略
▼極貧生活→資産35億円を可能にした「人生逆転の全手法」とは
▼貧乏人はモノを買い、金持ちは「〇〇」を買う

#2 チャイナタウン化する湾岸でタワマンババ抜きに人生を賭けるエリートサラリーマンの厳しすぎる実情…タワマン購入した40歳銀行員「ユニクロとくら寿司にしか行けない」(汐留太郎)7/22
▼勝どきなどの湾岸タワマンは中国人の間で人気が高い…湾岸が「チャイナタウン」と化しつつある
▼ついに外国人による不動産購入の制限が政局の争点にも浮上…それでも中国人による不動産購入を排除するのは難しい理由
▼「1億5000万円の壁」が不動産業界で意識されるようになってきた…それでも中国人富裕層はタワマン高層階を余裕で購入

#3 リベラルエリートの理想が完成させた「知能カースト社会」の絶望 何が日本社会の残酷な格差を生み出したのか(橘玲)7/23
▼リベラルエリートが語らない“格差の正体” 何が日本社会の残酷な分断を生んだのか
▼同じ「年収500万」でも圧倒的な“資産格差”が生じる恐るべき理由
▼“豊かで平和”になるほど格差が広がる絶望的なパラドックス
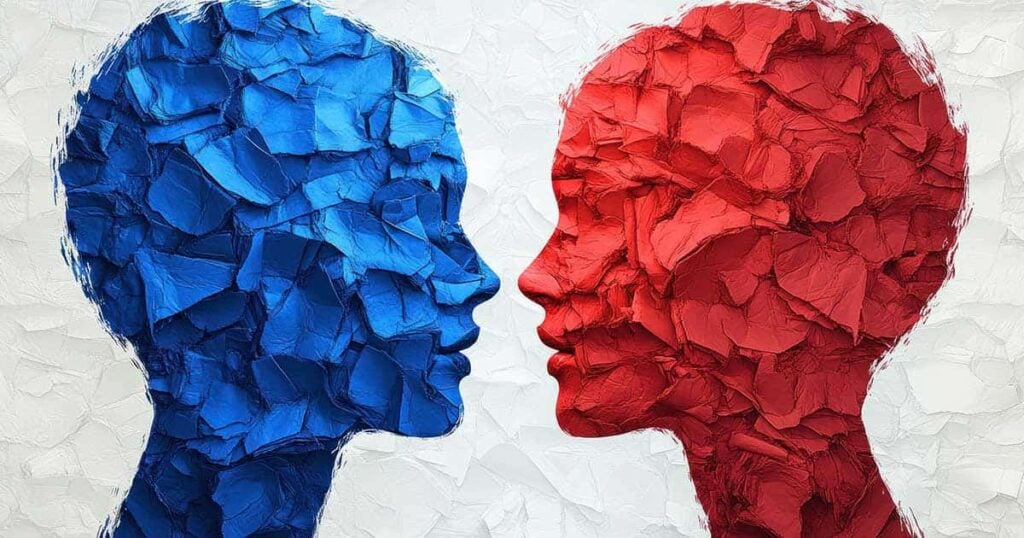
#4 参政党の台頭はリベラルの自業自得か…自らが招いた“理想の未来”に絶望している左派エリートたち(橘玲)7/24
▼リベラルエリートが陥った致命的な自己矛盾…理想社会の成れの果て
▼この国の仕組みは“偏差値60”の人間のために作られている
▼エリート知識人が支配する“古き良き日本”の正体

#5 「これだけやれば億り人も夢じゃない」識者が打ち明ける“最強の投資戦略”とは 格差社会で勝ち抜くための超シンプルで簡単な資産形成術(橘玲)7/25
▼AIがもたらすのは、便利さではなく“新たな格差”だ
▼“脱落エリート”が過激な左派ポピュリズムに傾倒するワケ
▼“凡人”でも金持ちになれる…格差社会で勝ち抜くための超シンプルで堅実な資産形成術

#6 “多様性の時代”がマウント地獄をもたらすという不都合な真実…「SAPIXママ」はなぜママ友同士でマウントしてしまうのか(勝木健太)7/26
▼その「いいね!」本当に共感? 無意識のマウントに心がざわつくワケ
▼“マウント資本主義”の奴隷になる人たち…心をじわじわ蝕む「格付けゲーム」の本質
▼なぜあの人は見下してくるのか? あなたには見せない“切実な不安”の正体

#7 インスタで“子育て大変アピール”するママはなぜ嫌われるのか 愛される人間と嫌われる人間の境界線は「マウントの質」(勝木健太)7/27
▼“健康意識の高い私”を演出するためにわざわざ高級パジャマを買う人たち
▼「素敵な夫アピール」から「子育て大変アピール」まで…インスタグラムの底知れぬ闇
▼アルゴリズムと欲望の「悪魔合体」が生み出すマウントの無限ループ

#8 「1億総マウント時代」で成功するために必要な“新しい処世術”とは…人間関係が円滑になって人生が変わる魔法の法則 (勝木健太)7/28
▼マウント地獄を“無傷”で生き抜くための超現実的な処方箋とは
▼マウントのモヤモヤは資本主義と人間の本能が生み出した“構造的欠陥”にすぎない
▼退屈なマウントを“最高のエンターテインメント”にする思考法

#9 2004年から始まった「女性の貧困」と2017年から始まった「中年男性潰し」の意外な相関関係…女性による逆襲はこれからも続く(中村敦彦)7/29
▼女性の貧困には必ず社会病理が起因している
▼楽しいはずのキャンパスライフが貧困の温床に
▼「働き方改革」で迎えた大きな転機

#10 「日本人ファースト」にかき消されたロスジェネ対策……雨宮処凛「参院選は最後の希望だった」(雨宮処凛)7/30
▼「日本人ファースト」が争点になった参院選に失望
▼自民党は「外国人問題」に乗るべきではなかった
▼優先されたのは企業の論理

#11 ロスジェネ世代が苦しんでいるのは“自分のせい”?雨宮処凛が考えるいま必要な支援とは(雨宮処凛)7/31
▼「社会のせいだ」と言えないロスジェネたち
▼ロスジェネ世代は一枚岩ではない
▼ロスジェネ支援はみんなが安心できる社会づくりにつながる