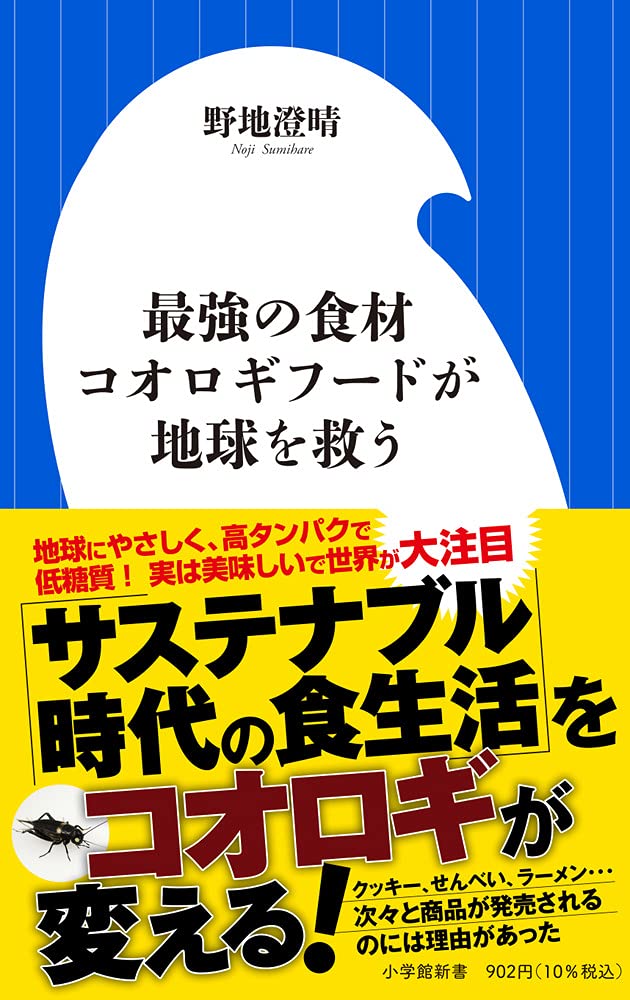そもそも、コオロギの味って?エビに似ている、餌で風味を変えられる

せんべいにクッキー、チョコやラーメンなど、コオロギを使った料理が少しずつ世に出回り始めている。中でも世間に大きなインパクトを与えたのが、2020年に発売された無印良品の「コオロギせんべい」だろう。反発の声も大きい食用コオロギではあるが、商品開発に協力した元徳島大学学長でコオロギ研究の第一人者である野地澄晴氏の著書を基に、食材としてのコオロギのポテンシャルを考える――。全4回中の3回目。
※本稿は野地澄晴著『最強の食材コオロギフードが地球を救う』(小学館)から抜粋・編集したものです。本著は2021年8月に発売されたものであり、記載内容は当時のものです。
第1回:前・徳島大学長「なぜあなたはコオロギを食べるべきか」…世界を救うのは”やっぱりコオロギ”と語るワケ
第2回:前・徳島大学長「栄養満点スーパーフードなコオロギは1200年前から人に愛されていた」 …だが本当に安全なのか
品切れ続出、無印良品の「コオロギせんべい」
無印良品を展開する株式会社良品計画は、2020年4月20日にコオロギせんべいを店頭で販売開始する予定で準備を始めていた。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら一旦延期となったが、5月20日から先行販売がネットストアにて実施された。無印良品のコオロギせんべいは、以下のように宣伝されている。
「無印良品のコオロギせんべいは、徳島大学の研究をベースに飼育された『フタホシコオロギ』という熱帯性のコオロギを使用しています。全て衛生的で安全な環境で飼育され、温度や湿度を一定に保つことにより通年産卵させることが可能で、食用に使用する量を生産することができます。
また、おいしく食べていただけるよう、コオロギをパウダー状にしてせんべいに練りこみ、コオロギの味を活かすために余計な原料を使わず、シンプルな配合にしました。エビに近い香ばしい風味を楽しめます」
ネットストアにて販売を開始したところ、何と短時間で完売となった。追加で販売したが、5月30日には「ご好評につき現在品切れしています」となった。
さらに増産し、「ネットストアにて先行販売していたコオロギせんべいを、本日7月10日より一部の店舗に拡大します。11店舗のみでの発売となります。より多くのお客さまにお届けするため、お一人さま3点までのご購入とさせていただきます」とのメッセージが掲載された。
それ以降、コオロギせんべいは順調に売れている。売り出しても早期に売り切れる状況が続いている。
コオロギ先進国・フィンランドのコオロギパン
無印良品とコオロギの出会いはフィンランドだ。2019年11月、フィンランドの首都ヘルシンキに、無印良品のフィンランド1号店となる「MUJIカンッピ ヘルシンキ」がオープンした。欧州最大の売り場面積と品揃えを誇り、カンッピショッピングセンター4階のワンフロア全てがMUJIの店舗となっている。
2019年、金井会長は、フィンランドで無印良品の1号店を出店するための準備にヘルシンキに出張した。フィンランドで、金井会長が見たものの一つが、コオロギパンであったと推測している。
良品計画食品部の菓子・飲料担当の山田達郎氏は、フィンランドに無印良品の1号店をオープンするために、フィンランドを訪問した際に、コオロギ入りのお菓子を紹介され、「最初は食べたくないと思った」と告白している。
しかし、コオロギ・パウダーを混ぜたお菓子やパンは、高タンパクでしかも環境負荷が少ない商品であり、SDGsの達成に貢献することが「MUJI」のコンセプトに合致していることを理解する。金井会長は、日本でのコオロギフードの開発を考え始めていた。
日本国内での情報収集の結果、徳島大学においてコオロギフードが作られていることを知る。その情報は、「徳島大学が食用コオロギプロジェクト」と題した小さな記事から得たものであった。
2019年4月、徳島大学の産学連携部を通じて三戸太郎准教授と渡邉崇人助教授に会いに来られた。「コオロギフードを作って、販売したいのですが、コオロギのことを教えてください!」
徳島大学のコオロギ研究グループと現アンテグラル社代表取締役の岡部慎司氏らは、コオロギ・パウダーを入れたどのような食品を作るか?を検討していたので、パンはもちろん、焼き菓子など何に入れても、それなりに良い食品ができる自信はあった。そこでコオロギフード事業を展開することに決めた。
2019年5月9日に、徳島大学の渡邉助教、岡部氏、三戸准教授が食用コオロギを生産する大学発ベンチャーを立ち上げ、「株式会社グリラス」と命名した。フタホシコオロギの学名である「グリラス・ビマキュラタス」のグリラスから取ったものである。
徳島大学のコオロギ研究グループが長年研究を重ねてきた成果が、世界のタンパク質不足を解消することに利用されることになる。
しばらくして、良品計画のスタッフが、フィンランドの企業から入手したコオロギ・パウダーを用いて作ったクッキーを、「これはどうでしょうか?」と徳島大学に持って来た。渡邉助教は苦笑しながら、その時のことを話す。「実はほんとに、まずかったのです」
そこで、岡部氏が開発してきたコオロギ・パウダー入りのお菓子を良品計画のスタッフに試食してもらった。「美味しいですね」が答えだった。このやり取りの結果、グリラスの国産コオロギ・パウダーを利用して、日本初のコオロギフードを作製することが決定した。
しかし、大量にコオロギ・パウダー入りの食品を作るとなるとハードルが高かった。良品計画と取引のある食品会社にコオロギフードの製作をお願いしたが、どの会社にも断られた。ある業者は「食品業者にとって、昆虫は天敵ですからね」。一番の問題は、食品業者の虫に対する心理的アレルギーであった。
通常の食品製造ラインに昆虫の痕跡が少しでもあると、不良品になるのである。また、食品生産ラインに少しでもコオロギのパウダーを使用すると、そのラインで生産した食品には甲殻類のアレルギーの表示をしなければならない。そのため、少量のロットでも生産を引き受けてくれる食品業者がなかった。
そんな中、唯一コオロギフードの製造を引き受けてくれたのが、株式会社山三商会であった。海老せんべいのメーカーである。
野口英司社長は「これまで様々なせんべいを売り出してきたが、ビッグヒットしにくい」とおっしゃった。コオロギせんべいをビッグヒットにすることが、徳島大学グループの使命である。まだまだ、食品としての余地があると考えている。
普段、コオロギを食しているアジアの人々は、エビを海のコオロギと呼んでいるらしいが、普段、エビを食している日本人は、コオロギは陸のエビであると言っても過言ではない。同じ甲殻類であり、条件によっては大量に増殖する動物である。この工場で2020年3月から、コオロギせんべいの生産が始まった。
コオロギはエビに似ておいしい
よく聞かれる質問は、「コオロギは美味しいの?」である。コオロギせんべいは「エビせんべい」の味に近い。実際、コオロギせんべいを何も説明せずに食べていただき、「どんな味?」と尋ねると、「エビせんべい」との答えが返ってくる。
従って、一般的にはエビを用いた料理において、エビの代わりにコオロギを用いると、期待される味の料理が得られると考えている。
実は、コオロギの味は、食べた餌に依存する。野生のフタホシコオロギは、雑食性で草地や耕作地で生活し、そこにあるものを食べていると考えられている。この性質は、飼育する立場からするとコオロギの素晴らしい点である。
多くの植食性昆虫は、餌の嗜好性が強く、食べるものが決まっている。例えば、蚕は桑しか食べない。日本産のアゲハチョウ類の幼虫はミカンやカラタチなどの柑橘類の葉しか食べないものが多い。
その点、コオロギは雑食性なので、何でも食べる。徳島大学の三戸研究室で様々な餌で飼育し、その味を調べたところ、最もおいしいコオロギは椎茸を餌にしたものであった。また、徳島の名産である「スダチ」を餌として食べると、スダチの香りのするコオロギができる。また、「柚子」も同様である。
どちらも柑橘類であるが、スダチの場合は皮を残すが、柚子の場合は、皮も含めて食べてしまう。この様に、餌により風味を変えることができる。