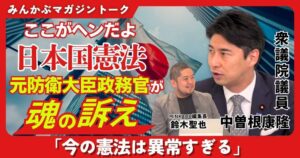コンビニ大手、今期中に雑誌棚の完全撤廃検討…週刊誌1000円時代へ突入「文庫は1600円、新書は1200円」いったい誰が買うのか

出版社が苦境に立たされている。元経済誌プレジデント編集長で『週刊誌がなくなる日』の著者である小倉健一氏が、各社の内情を語る――。
「出版流通は、もはや既存構造では事業が成立しない」
「出版流通はもはや既存構造では事業が成立しない。市場の縮小に、トラック運転手の労働時間規制を強化する『2024年問題』が重なり、本を運ぶ費用を賄えない」(日経新聞5月24日)――こう話すのは、出版取次大手トーハンの近藤敏貴社長だ。トーハンは、2023年3月期の出版流通事業が4期連続で経常赤字になることが見込まれていて、出版各社に書籍や雑誌の運搬費の値上げを相談するという。
物流業界で、今、大きな問題となっているのが「2024年問題」だ。ブラック化しているトラックドライバーの労働環境の改善のため、来年(2024年)4月から、時間外労働の上限が年間960時間に規制され、月60時間以上の残業をした場合、割増賃金率がアップすることになる。
国土交通省「トラック運送業の現状等について」によれば、トラックドライバーは、全職業平均と比較して、労働時間が約1〜2割長く、年間賃金は1〜3割低い状況にある。
物流の労働環境改善が何をもたらすかといえば、運べる荷物の減少と、運賃の高騰にほかならない。書籍の運搬費用は、これまで「聖域」とされ、出版取次が割安価格で提供していた。それが可能だった理由は、流通量で圧倒する雑誌の運搬が収益の柱になっていて、雑誌が発売されていない日などで、空いているスペースで書籍を運んでいたためだ。しかしトラック業務の効率化の過程で、書籍の運搬費用は「聖域」ではなくなりつつある。
紙代は、恐ろしい勢いで上昇した
まさしくドミノ倒しのような現象だろう。紙代が上がり、運搬費用が上がり、価格に転嫁され、紙の雑誌や書籍はますます売れなくなる。
ロシアによるウクライナ侵略戦争によってエネルギー価格や紙代が高騰。昨年(2022年)の出版業界は、紙の雑誌や本の売り上げが下がる中で、急激な値上げを迫られた。その後、ガソリン価格は少しずつ落ち着いた動きを見せるようになり、出版関係者はホッと一息、安心をしていた矢先のダメ押しだ。中堅出版社の紙の調達担当者は、ため息をもらす。