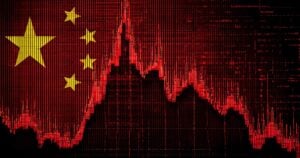“米ドル一強”崩壊の足音が聞こえる……「金融の核兵器」を発射した米国、対抗するロシア

日米両市場の投資家として40年活動してきた米国在住のワイズマン廣田綾子氏は、「今の世界情勢は混沌を極めつつある」と話す。その大きな要因の一つが、「ドル一強」の通貨秩序への動揺だ。現在、世界では何が起こっているのか。ドル基軸通貨体制の観点から、同氏が解説する。
※本稿はワイズマン廣田綾子著「海外投資家はなぜ、日本に投資するのか」(日経プレミアシリーズ)から抜粋、再構成したものです。
第1回:投資キャリア40年・米国在住投資家「日本はいま、世界のバリュー投資家から注目されている」バリュー投資の三つの型
第2回:年間300社の経営陣と面会した投資家が見つけた「成長余力のある企業」の探し方
目次
ドル一強を打ち崩すデジタル通貨
第二次世界大戦以降、ブレトンウッズ体制、ニクソンショック以降の為替変動制導入という変遷の中で、半世紀以上にわたり続いてきた「ドル一強」の通貨秩序。それが決して永遠ではなく、揺さぶられた末に、いつか崩れ去るときが訪れるかもしれない―多くの人々がそう意識する一つのきっかけを作ったのは、2019年にフェイスブック(現メタ)が打ち出した、独自のデジタル通貨「リブラ」の構想でした。低所得層や新興国の住民など銀行口座を持たない人々に幅広く決済手段を提供する金融包摂という大義を掲げ、翌20年の運用開始を目指していました。
リブラは当初、ブロックチェーン技術を活用しつつ、実質資産との連動によって価値を安定化させることで通常の暗号資産と差別化を図るステーブルコインの一種として計画されていました。ただ、デジタル通貨が普及すれば各国の中央銀行が通貨を制御できなくなるとの懸念から多方面で反発が生じ、20年12月にフェイスブックはリブラ構想を事実上撤回し、
「ディエム」に名称を変更。フェイスブックはあくまでディエムを運営する非営利団体の参加企業の一つに過ぎないというところまで、構想は後退を余儀なくされました。
その後、民間団体による新たなステーブルコインの立ち上げが相次ぐ中で、構想は次第に過去のものとして忘れられていきます。しかしこの構想がもたらした一連の騒動は、テクノロジーの進展を含めた時代の変化の中で、ドル基軸通貨体制と各国中央銀行が制定する金融政策という枠組みの前提が崩壊するとどのような事態がやって来るのか、市場関係者たちに頭の体操の機会を与えたと言えるでしょう。