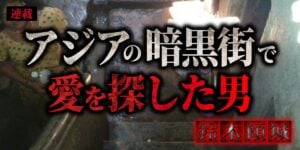「面白いところがある」…80年代バンコク、薄気味悪い男に300バーツで誘われた謎の施設「スモーキングハウス」で男が突き付けられた現実

1980年代から90年代にかけて、アジアの歓楽街は熱気と混沌、そして甘美な腐臭に満ちていた。高度経済成長のあぶく銭を握りしめ、男たちは夜の底へと沈んでいった。これは、かつて暗黒街に沈み、熱気と混沌に溺れながら「愛」を探し求めた男の回想録である。
「ブラックアジア」「ダークネス」でカルト的な人気を博す作家・鈴木傾城氏による連載「アジアの暗黒街で愛を探した男」第3回――。

バンコクのチャイナタウン「ヤワラー地区」(2016年撮影)
<前回までのあらすじ>
1980年代、日本のバブルがもたらした「あぶく銭」を手に、著者は再びタイの熱気の中へと沈んでいく。滞在費を削るため、カオサンを離れ辿り着いたのは、場末の極み・ヤワラー地区の安宿「台北大旅社」だった。そんな宿の従業員が不敵な笑みを浮かべて囁いた。「おい、面白いところがあるんだ。連れて行ってやる」――。
目次
欲望渦巻く「地上の楽園」パッポンへ
私の泊まっていたヤワラー地区の旅社は、路上に立つ女性たちが男を連れ込んでは出ていくようないかがわしい場所だったのだが、そこで働いている従業員もまた輪をかけて怪しい男たちが多かった。
私に「面白いところがある」と執拗に言ってくる痩せた男もまたそんなひとりで、私を見るとニヤニヤと笑って「連れて行ってやる」と離さなかった。どこなのかと言っても「まあ、この近くだ」みたいなことを言って詳しく言わない。
こんな薄気味悪い男について行きたくなかったので、私は適当に返事をしてパッポンに繰り出していた。
パッポンはいつ行っても音楽でやかましく、白人(ファラン)の男たちがサメのようにうろつき、バーからバーへと渡り歩き、ときには酔って路上でケンカしていたり、女たちと熱いキスを交わしていたり、痴態の光景が途切れなかった。
この開けっぴろげな欲望の世界に私は酔っていて、世界中でパッポンほど素晴らしい場所はないと確信していた。ここでは快楽が渦巻いていた。アルコールが満ちあふれ、若い女たちが半裸で踊って男たちをエキサイトさせていた。
もっとディープな世界を追求したい男は、ゴーゴーバー『スーパープッシー』のボーイに声をかければマリファナをこっそり手に入れることもできた。ファランたちはマリファナが大好きで、まず酒を飲んで酔って、次にマリファナを吸って、それからゴーゴーバーに繰り出して、気に入った女性をペイバー(連れ出し)するのがお決まりの順番だったようだ。
「NO AIDS!」楽園に突きつけられた死の宣告
1980年代の頃はまだそれほどの数ではなかったが、レディーボーイたちもいて、彼らは表のオープンバーに座って客を取っていた。
堕落と狂騒にまみれたこの界隈を私は天国だと思っていたが、ある日の夕方、このパッポンを地獄だと思っている人たちの集団と出会ったのを鮮明に覚えている。彼らはプラカードを持ってパッポンの入口に立っていた。
そのプラカードを見ると「NO SEX!!」だとか「NO AIDS!!」と書かれていた。私がぼんやりとそれを見ていると、プラカードを持った女性のひとりが私を指さして「Go Back! AIDS many,many!(帰りなさい、エイズが蔓延してる!)」と言うのだった。
パッポンの女たちとかかわりながら、なるべく考えないようにしていた現実をこの活動家の女性は私に突きつけようとしていた。
ちょうどこの頃、全世界はエイズの爆発的流行で大騒ぎになっていた。著名人がエイズで次々と死んだ。日本でも松本や福原のソープランドで、エイズの女性がソープランドで働いていたことがわかってエイズパニックも起きていた。
タイも東南アジアで有数のエイズ汚染地帯と言われていたのだが、その汚染の中心地がまさにパッポンだったのだ。
「地雷」が埋まった天使の都
パッポンには世界中から男たちがやってくる。女たちは毎日何人もの男たちと関係を持つ。そのせいで、バーガールが次々とHIVに感染してエイズを発症し、深刻な社会問題になっていた。当時、HIVは特効薬のない「100%死に至る性病」だったのだ。
誰もが神経質になり、恐怖と不安に怯え、タイではパッポンのような歓楽街に出入りする男や女は「病原体」として激しく拒絶されつつあった。私の愛する女性たちはみんなエイズ扱いされていた。おそらく、私自身もだ。
私も不安と恐怖が常にあった。だが、自分にできることは何もない。ゴーゴーバーの女性の誰がエイズなのかはわからない。その頃、『地雷を踏んだらサヨウナラ』という本が売れていたが、私にとっての地雷はまさにエイズでもあった。
だが、エイズのことは考えたくなかった。ただでさえ、株式市場にカネを賭けて全財産が吹き飛ぶかもしれないバクチをしているのに、パッポンでもエイズで死ぬかもしれないと考えたら不安で発狂するしかない。
破産して死ぬか。エイズで死ぬか……。不安が募ってもパッポンの魅力から離れられないのであれば、何も考えないで生きるしかない。恐怖と快楽は紙一重だ。熱い肌の女性と過ごし、天国には地雷が埋まってるんだと思わずにいられなかった。
バンコクは現地で「クルンテープ」と呼ばれていて、それは「天使の都」を意味するというのをその頃に知った。パッポンの女たちはさしずめ堕天使だったのかもしれない。彼女たちがすべての問題の元凶だったが、その元凶が私を妖しく誘っていた。
スモーキングハウスとふたりの女性
ある日の夜、ずっと雨が降りしきっていたのでパッポンに行く気が削がれて、安宿の中で壁に張り付いているヤモリを見ながら時間を過ごしていると、例のいかがわしい宿の従業員の男が勝手に私の部屋に入ってきた――。