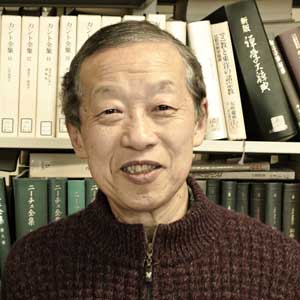大逆襲…統一教会元信者10人に1億6000万円の返還を命じた大阪地裁判決「価値乏しい商品に法外な金」

いずれの新宗教も、布教と集金に対しては並々ならぬ力を注いできた。ただし宗教学者の島田裕巳さんによると、ある程度大きくなった新宗教は複数のリスクも抱えているという。指導者層への富の集中は信者に不満をもたらし、信者の離反が教団に打撃を与えるケースもある。新宗教が直面しているリスクとは――。全4回中の4回目。
※本稿は島田裕巳著『新宗教 驚異の集金力』(ビジネス社)を抜粋、編集したものです。
第1回:統一教会「韓国・財閥としての顔」日韓トンネル利権の仕組み…なぜ女性入信者は「統一原理」に惹かれるか
第2回:公称550万部!朝日新聞より売れる「聖教新聞」…創価学会の驚異的な商材ビジネスモデル
第3回:新宗教信者が「つい献金したくなる」キラーフレーズ…なぜ金を支払うことが快楽につながるのか
「金余り」がもたらす堕落
新宗教のビジネスモデルは効率的で効果的だ。そのため、新宗教の教団には、相当の額の金が蓄積されることになる。それは、「金余り」という、厄介な問題を生むことになる。
創価学会では、金余りが生じても、それが教団のトップや幹部たちの懐を富ませない仕組みが作られている。池田大作の著作はベストセラーになってきたものの、印税は基本的に学会や学会関連の機関への寄付に回され、池田個人の懐にはほとんど入らない。
ところが、そうした仕組みが整えられているのは、創価学会に限られる。他の教団では、そうした仕組みは整えられていない。
教団に集まってきた金は、教団の上層部が自由に使えるようになる。そうなれば、教祖や教主、教団の幹部は、膨大な収入を得て、一般の信者には思いもよらない豊かな生活を送ることができる。信者がその事実を把握したとしても、彼らには教えの源泉である教祖や教主を批判したりはしない。
これによって、新宗教の教団内部には、経済的な格差が生まれる。信者は、自分が出した金が、教団の発展のために使われるのではなく、教団トップや幹部を富ませるために使われれば、それには納得しない。それによって、不満が蓄積されることになる。
金余りは、新宗教の教団にとって、必ずしも健全な状態とは言えない。これからも、教団が発展し、すでに確立されたビジネスモデルが機能していけば、教団にはさらに金が集まってくる。
にもかかわらず、集まった金の使い道がない。これ以上、不動産を取得する必要もなければ、建物を建てる必要もないということになると、集まった金をどうするか、それが問題になってくる。
本来、利益を上げることを目的としていない宗教団体では、金余りが生じたとき、それにどう対処するか、的確な方策が確立されてはいない。そのために、問題が発生する危険性をはらんでいる。
人間は、金の魅力には勝てない。金は、さらなる欲望を喚起し、人間を堕落させ、組織を混乱させていく力をもっている。そうした金の力を制御することは、相当に難しい事柄なのである。
信仰がなくなったとき、教団はどうなる?
新宗教の教団には、もう一つ根本的な問題がつねにつきまとっている。宗教を宗教たらしめているのは、信仰というファクターである。この信仰というファクターが厄介なのは、信仰をもつかどうかで、ある事柄に対する評価が百八十度異なってくる点である。
信仰をもつ人間にとっては、神聖なものであっても、信仰がない人間は、そうとは思わない。「鰯の頭も信心から」ということわざがあるが、信仰のない人間からすれば、ただの魚の頭が、信仰をもつ人間には尊いものであったりするのである。
しかも、信仰というものは、永遠とは限らない。信仰をもたない者が、ある日、あるとき、何かのきっかけで突然信仰をもつようになることがある。それとはまったく逆に、それまで熱心に信仰していた人間が、何か問題や矛盾を感じて、突然信仰を失ってしまうということもある。それまで尊いと信じていたものが、たんに鰯の頭にすぎないと思ってしまえば、その人間の見ている世界は一挙に変化する。
信仰をもっているあいだは、自分が属している宗教や教団を高く評価し、そこに金を出すことを尊い宗教行為としてとらえる。金を出すことは宗教や教団に貢献することであり、できるだけ多くの額を献金に回そうとする。そして、仲間を増やし、そうした人間にも積極的な献金を促す。
ところが、信仰を失ってしまうと、自分がなぜ献金を行ったのか、その理由がわからなくなってしまう。献金はすべて無駄なことに思え、自分は教団によって騙(だま)されたのではないかと考えるようになる。
それによって、同じ献金という行為が、その個人にとって、まったく違う意味をもってくる。信仰にもとづく行為であったものが、騙された上での無意味な馬鹿げたものに思えてくるのである。
信仰を失って、騙されたと感じるようになった人間は、教団を告発して、マスメディアに訴えたり、献金した金を返却するよう裁判に訴えたりする。そうしたことが表沙汰になり、マスメディアで派手にとり上げられれば、教団にとっては大きな痛手になる。興味本位の報道も続き、マイナスのレッテルを貼られることにもなってくる。
それだけではない。新宗教において、信仰を失い、脱会しようとする人間が出てくると、仲間のなかにそれを引き留めようとする者が現れる。ときに、そうした人間は、強硬な手段を使ってでも引き留めようとする。そうするとトラブルに発展するが、そうなると、その宗教は暴力的であるとして、ここでも社会的な批判を浴びることになる。
信者が仲間を引き留めるのは、たんにメンバーが減ることを恐れるためではない。仲間が信仰を捨て、去っていくということは、自らの信仰が否定されたに等しい。引き留めようとする当人は、そうした思いを抱き、そのために必死に引き留めようとする。だが、引き留められる側は、すでに信仰を失ってしまっており、かつての仲間からの働きかけは、自分から自由を奪おうとする暴力的な行為に映ってしまう。
さらに最近では、献金した額が多かったり、献金させる方法に問題があったりすると、裁判所の判断で、脱会者に献金した金を返還することを求められるようになってきている。
たとえば、2001年に、統一教会の元信者10人に対して、大阪地裁は、約2億6000万円の損害賠償請求のうち約1億6000万円の返還を命じた。価値の乏しい商品に法外な金を出させたのは違法だと認めたからである。このように、信仰を失う人間が続出すれば、それは教団の経済にも打撃を与えることになる。
「信仰二世」との温度差
たとえ、信仰を失うまでに至らなくても、信仰の形骸化という事態も起こる。新宗教において、信者は基本的に2つに分けられる。一方には、自らで信仰を獲得した信者がいるが、もう一方には、自らが獲得したわけではないが、親が信者になっていて、その親から信仰を伝えられた信者がいる。前者は「信仰一世」としてとらえられ、後者は「信仰二世」としてとらえられる。
教団が歴史を重ねていけば、信仰二世の下には、さらに信仰三世や四世が生み出されていく。信仰一世の場合には、誰かから勧誘されて信仰を獲得したわけで、信仰をもたない自分からもつ自分へと生まれ変わった体験をもっている。彼らは、何らかの形で、「回心体験」を経ているわけで、信仰者としての強い自覚をもっている。
ところが、信仰二世以下の場合には、親が信者であることで、自分も信者になっただけで、ほとんどの場合、回心体験を経ていない。その分、信仰は空気のようなものになっていて、信仰者としての自覚は一世に比べてかなり弱い。
状況によっては、信仰を強制されたものとしてとらえ、活動にはほとんど参加しない場合も出てくる。安倍元首相狙撃事件の容疑者は母親の信仰にまったく共感せず、母親が多額の献金をさせた教団を強く恨んでおり、そのことが犯行に結びついた。
信仰者としての自覚の薄い二世ばかりが会員になれば、その教団の活動は停滞する。そこで、それぞれの教団では、二世以下の信者の信仰を覚醒するための特別の機会を設けている。たとえば、天理教には、3カ月の研修である「修養科」が設けられている。
しかし、一方では、格別研修の機会を設けていない新宗教も存在する。創価学会の場合がそうである。この教団では日常の活動が活発で、そうした機会を必要としないとも言えるが、やはりそれでは親から信仰を受け継いだ若者に信仰者としての自覚をもたせることは難しい。
そのため、創価学会では、信仰の形骸化が起こり、若い会員の信仰に対する熱意を掘り起こすことが難しくなってきている。会員になっても、熱意でははるかに親の世代に劣るのだ。
しかも、時代が変化したことで、信仰活動に邁進(まいしん)することが、「現世利益」の実現に直結しなくなってきた。そのため、会員たちは、教団での活動よりも、個人的な経済活動に多くの時間と熱意を割くようになってきている。
現在、巨大教団として君臨している新宗教は、おおむね高度経済成長の時代に発展したもので、現在では安定期から衰退期に入っている。日本社会に定着し、社会と対立することも少なくなってきたが、それも、教団にとって必ずしも好ましい事態とは言えない。社会と対立関係にあるときは、教団に緊張感があり、信者も活動に熱心になるが、それが薄れると、熱意はなくなっていかざるを得ないからである。
規模の大きな教団で、現在でも活発に活動しているのは、真如苑や幸福の科学など、少数にとどまる。多くの新宗教教団は、安定期から衰退期に入ったことで、曲がり角にさしかかっている。それは新宗教にとって一つの危機であり、金集めの力も失いつつあることを意味している。