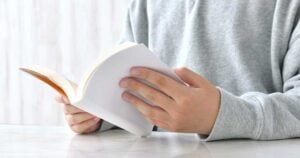東大合格者が守った3カ条。数字にこだわる、志望校公言、そして…「それでも僕は東大に合格したかった」第3話

「自分を変えたければ、東大を目指してみろ」高校1年のあの日、ある教師の一言でずっと落ちこぼれだった僕は途轍(とてつ)もない挑戦を強いられた。結局2浪し、3度目の受験を終えた時、その教師がまた想定外のことを言い出して……。現役東大生作家であり、ドラマ日曜劇場『ドラゴン桜』脚本監修をした西岡壱誠さんの偏差値35のド底辺から合格発表を迎えるまでの原点の物語をお届けする。(第3回/全3回)
※本記事は、西岡壱誠著『それでも僕は東大に合格したかった』(新潮社)より抜粋・再編集したものです。
第1回:偏差値35ド底辺、2年連続不合格の崖っぷち「それでも僕は東大に合格したかった」第1話
第2回:なぜ多浪生が”優等生”を演じだしたら偏差値35→70に爆増したのか「それでも僕は東大に合格したかった」第2話
目次
成績も上がって、モテるようにもなる3カ条
師匠は黒板に3つの項目を書いた。
- 数字にこだわって勉強する
- 東大に行くのだと、周りに公言する
- 他の人の質問を積極的に受けて、時には教える
「いいか西岡、この3カ条を守れ」
師匠は言った。
「まずは数字だ。勉強時間でも、模試の点数でも偏差値でも学校の順位でもなんでもいい。とにかく、いい数字を取れ。どんなに些細なことでも、小テストでも定期テストでも関係なく、1位上を、1点上を目指せ」
それは、まあ、わからなくもない。
「まずは1科目でいい。1科目でいいから、偏差値70を目指せ」
「はい」
「次は東大に行くと公言しろ。今までは恥ずかしがっていたかもしれないが、とにかく周りに言い続けるんだ」
「は、はい」
正直、それは、ハードルが高いなと思った。元々いじめられっ子の僕だ。笑われるのではないかという思いが強い。
「大丈夫だ。数字さえあれば、周りの大人は必ず納得する」
「そういうものでしょうか」
「結果が伴っていることを否定できる人は少ない。言われたら、結果で返事をしてやれ」
だとすると、僕が東大に行くと言ったら笑われそうなのは、結果がないからだ。結果さえあれば、周りは僕のことを「東大に行けるかもしれない人」と思ってくれるのかもしれない。
「そっか、そうですね。頑張ります」
そして3番目を師匠は指差す。
「最後に、他の人の質問を積極的に受けて、お前が人に教える立場になるんだ」
そんなこと、できるのか? 僕は口下手だし、人に何かを教えられるとも思えない。
「西岡、東大生が誰でもやっている勉強法が、これなんだ」
「へっ?」
僕は素っ頓狂な声を出した。