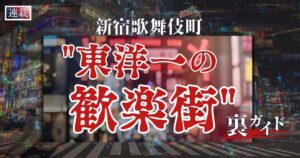SNSで人気の介護士が心に決めた「自分を守る5つのルール」…実施後、施設利用者の97%が反対した思いやりのサポートとは

なぜ介護のプロは何人も同時に介護し続けることができるのか。なぜ在宅介護はこんなに辛いのか。介護士として働きながら、祖母の介護も経験したたっつん氏に「介護者が心と体を守るための5つのルール」を教えてもらった。Twitter上でも大きな反響を呼ぶプロの知恵と工夫を厳選してご紹介する。みんかぶプレミアム特集「逃げの介護」第6回目ーー。
目次
もう知らんわと思うことは大切
私は在宅でご家族を介護されている方を心から尊敬します。なぜなら私自身が祖母の介護を投げ出してしまった過去があるからです。
在宅介護と施設の介護では全く性質が違います。 私は生まれたときから祖母と同居していました。私が祖母の介護をしているとき、それまでの思い出や関係性が介護を邪魔してきました。 端的に言うと、なんかイラつくんです。
祖母は最後は父と2人暮らしで、私は近くに住み父の介護をサポートする立場でした。おばあちゃんの頭には、父に殴られたであろうたんこぶができていて、認めない父とそれをかばう祖母に怒りを覚えました。
そのときに、自分を守る方法として僕がとった行動が「もう知らんわと思うこと」です。祖母の世話を何もせずに帰ったこともありました。徘徊の症状があると事情は変わってきますが、そうでなければその日は諦めて美味しいものを食べて帰るとか全然いいと思うんです。
「家族だから」と過大な義務を背負う必要はなくて、むしろ家族だからこそ「一時的に離れる」というプロセスがないと関係性が密着しすぎていて心が崩れてしまいます。
ここからは、長年介護士として働いた経験から導いた介護者が心と体を守るための5つのルールについて紹介していきます。
介護士の私が仕事中におむつに用を足した理由
1つ目のルールは、常識を疑うこと。介護には既存のルールがたくさんあります。そして、それらのルールのほとんどが検証されることなく、漫然と引き継がれて今に至るケースが多いのです。