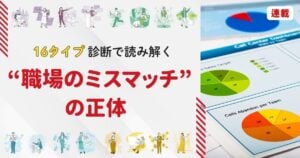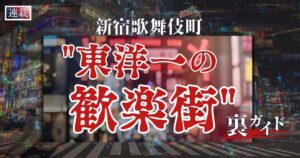「自分の正義を創る哲学の旅」それは羽生結弦のアスリート人生、Novaの旅そのもの…『Echoes of Life』さあ私たちもその身を、視線を、心を千葉へ

目次
羽生結弦は社会という場における「正義」も語っている
表現という場におけるひとつの「正義」。
テレビ朝日『「Echoes of Life」羽生結弦が紡ぐ究極のストーリー』。
羽生結弦自身の表現という場における「正義」と同時に、羽生結弦は人の社会における「正義」にも触れている。
自分の正義をつらぬけなくても、柔軟に相手の正義を受け入れて自分の芯にすると。
これは哲学者プラトン(ディアロゴス)、あるいはフッサール(共通了解)の説くような「対話」による哲学である。
羽生結弦はNovaの旅に絡めてこう説明する。重要なので長文だが起こす。
「相手の意見を受け入れるばっかりだと、実はそんなにうまくいかない。自分の哲学を言った時に相手からいろんな質問をされたり反発をされたりする。そん時に自分がそれに対して受け入れて、こうこう、こう思ってるからこういうふうにできるよ、この理論は正しいでしょ、って言っていく事によってだんだんその理論が固まっていく。で、逆にその反論された時にそれを、やわらかい心を持っていないと、ただひびが割れて終わっちゃう。だから受け入れられるスペースも持っておかなきゃいけない。それが哲学にとっての柔らかい心なのかなあというか、これ違ったんだなとか、その正義を貫けなかったとしても、じゃあ柔軟に柔らかく、正義を受け入れて自分の芯にすることも可能だよね、っていうのはなんとなく、物語の後半でも言ってるつもりはあります」
その表現者が故の「聖なるもの」という証左
これを踏まえてアイスストーリーを、今回の『Echoes of Life』を観るとまた羽生結弦の演じるNovaの想いに踏み込めるように思う。
もちろん松岡が前もって「相反」と言うように。羽生結弦も戦争などの大きな枠の話ではこの「正義」を前提にしてはいない。あくまで人と人の社会という場における「正義」、そして先の羽生結弦にとっての表現の場としての「正義」である。
この「正義」について思想家アランは「正義の原則は平等ということである」として、プロポにこう書いている。※
「正義とは理性的部分が貪欲な部分、強欲な、貪婪な、そして暴利をむさぼる部分を封じる力である。それは君のものであり、ぼくのものでもある諸問題を、仲裁者のように、あるいは仲裁者によって解決するように導く」
「貪欲な部分はきわめて狡猾で、最初、判断を誤らせるものだから、反対の術策あるいは慎重な対応を取ることによってはじめて正義が保たれる」
「正義の基礎であるこの他者に対する大いなる配慮は、つねに目的として考えられるべきであって、決して手段として考えられてはならないということに帰結する」
後半には哲学者イマヌエル・カントの論も引いたプロポだが、おおよそ羽生結弦であれ、アランであれ「正義」に対する見方に乖離はない。
それにしても、私はフィギュアスケートの、アイスショウの話をしている。それなのにこれだ。決して上下や貴賤の話をしているのではない、これほどまでに深淵を語る作品が、フィギュアスケーターがあっただろうか。
羽生結弦のすぐれた表現には学びがあるとよく言われるが、羽生結弦を通してみな学びを深める、これもまさに羽生結弦のアスリートとしての実を伴った芸術、その表現者が故の「聖なるもの」という証左なのだろう。
逃げたら生きる意味がわからなくなる
またスポーツを通したあるアスリートとしての「正義」も語った。
「1位のみが正義なわけであって、2位以下は悪と言っても過言ではない」と。
これはもう羽生結弦の競技会時代を知っていれば誰もがわかる話であり、決してこの通りの話ではないという、ある種の「投げかけ」であることもわかる。