23区内教育ママ「徒歩5分以内の公立中同士でも内心点のつけ方に差があります」…内申書の残酷な真実「偏差値70の高校と偏差値45の高校の評定を取る難易度は全く違います」
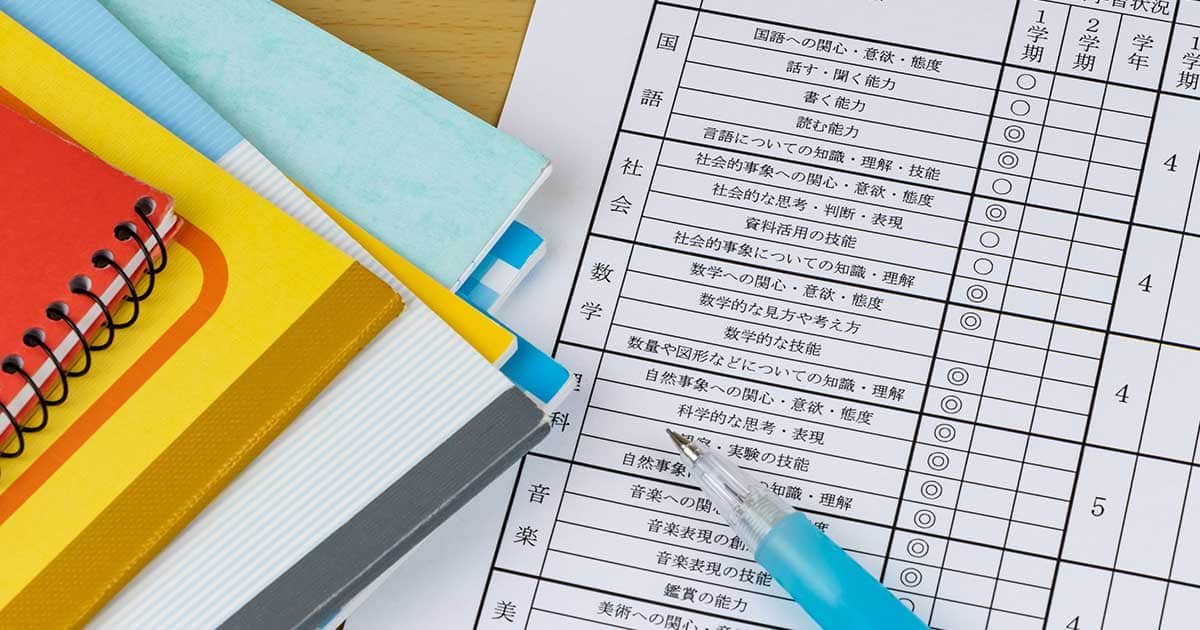
「子供の内申点を上げたい」と考えるのは全親共通の願いだろう。では、学校ごとに内申点のつけ方に差があったらどうだろう。「不公平だ」と思われる方も多いのではないか。教育投資ジャーナリストの戦記氏は「東京都内でも、徒歩5分以内の隣の公立中学校同士ですら、内申点のつけ方に差があるという声もあります」という。同氏が内申点の“残酷な真実”に迫ったーー。みんかぶプレミアム特集「中学受験の新勝ち筋」第4回。
目次
都内教育パパ、家計の事情で公立中を選んだのに、体育の内申点をあげるために塾代がかさみ本末転倒
教育投資ジャーナリストの戦記(@SenkiWork)と申します。
内申書。
この単語を耳にして、プラスのイメージを持つ方は少数派かと思います。何しろ、「保護者や子どもたちに内密に申告する書類」という意味で、内申書という呼称が定着している歴史がありますから。
中学受験を選択して中高一貫校に進学した場合、高校受験が無いことからこのキーワードを学校生活で耳にすることは殆どありませんが、公立中からの高校受験を選択した方には死活問題ですので、敏感に反応することかと思います。
昨年2024年秋に、25年以上の親交がある友人からのLINEを受けて、私は大変驚きました。
「内申書で地獄を見ているよ。子どもが中3で豊島区にある公立A中学校から高校受験をしているのだけど、今の東京都の内申書の制度が予想以上に不公平だと思う。要するに、子どもが内申点5をなかなか取れないわけだが、地域間格差が大きいことに気が付いた。子どもが通うA中学校には、学区内のB小学校の中学受験撤退組が比較的多いのだが、その子たちが優秀なので競争が厳しい。でも、同じ区内でもC中学校には中学受験撤退組が集まらないので、競争が緩い。だからC中学校では内申点が取りやすいんだよ」
「そして、東京都は、実技科目の内申点が2倍になるんだ。これにより、体育とか音楽とかの実技系で頑張らないと内申点に大きく響くことになる。もともと家計への影響を考えて公立中を選んだのに、現実的には体育の内申点を上げるための塾に通うことになってしまった。出費が痛かった」
「自分の知り合いは、この問題に小学生のうちに気が付いていて、わざわざ自宅から遠いC中学校に通うことを選択していたんだよ。当時は何をそこまで、と思ったけど、今はその選択をしなかったことを後悔している。A中学校に進学して失敗だった」
内申書制度に不平・不満をあげる人が多い現状
内申書という制度に不満がある人が多いことは、私も2016年時点から認識していましたが、私と同世代の子どもを持つ友人が語りだしたことに驚きました。調べてみると、上記のような話がX(旧Twitter)に多数存在するではありませんか。どうやら、公教育における高校への接続で重要となる内申書で、不合理なことが発生しているようです。
以上を契機に、2025年現在の内申書(内申点)の闇と光を深堀りすることにしました。これまで、内申書問題は、①公立中学校に通う本人、②本人の保護者、③高校受験塾関係者、④政治家(都道府県議会レベル)、⑤教育政策の研究者、が声を上げることが多かったのですが、調査してみると、これら関係者には複雑な利害関係があることも分かりました。ポジショントークが多すぎるのです。
今回、上記のいずれにも該当しない私にて、「現在小学生である我が子に、中学受験と高校受験のどちらを選択すべきか」という純粋な小学生保護者目線にて、内申書問題を可視化することを試みたいと思います。
尚、本調査にあたり、内申書制度の一般的内容については、2024年7月に出版された『内申書を問う – 教育評価研究からみた内申書問題』(田中耕治/京都大学名誉教授・佛教大学客員教授、西岡加名恵/京都大学教授編)が詳しいので、基礎資料として参考にさせて頂きました。研究者による書籍ですが、一般向けに分かりやすく解説されており、また引用・参考文献リストが充実していますので、1次資料にあたりたい場合にも便利です。公立中学校からの高校受験に関心がある方は、一読をお勧めします。
そもそも内申書とは…実技教科の内申点を10倍にする県も
実は、内申書というのは俗称にすぎません。学校教育法施行規則第78条並びに90条にて規定されている「調査書」が正式名称です。しかし、「保護者や子どもたちに内密に申告する書類」という意味で、内申書という呼称が定着しているのが実態です。内密に申告する、という意味が込められているので、この言葉から受けるイメージが悪いのは当然だと思います。また内申点という言葉も俗称に過ぎず、公的には「調査書の評定」などと呼ばれています。
内申書を理解するには以下ポイントが重要となります。
①内申書の様式は全国の47都道府県ごとに異なる。
②各都道府県内の公立高校入試においては、様式は統一されている。
③内申点として用いる学年は、都道府県別に異なる。1・2・3年次全て、3年次のみ、2・3年次のパターンが存在する。また3年次の評点を2倍にするケースもある。
④内申点の対象教科としては、国語・社会・数学・理科・外国語の主要5教科と、音楽・美術・保健体育・技術家庭の4つの実技教科を合わせた9教科である。これら全てを均等に評価するケースと、教科によって比重を変えるケースがある。学力検査を行わない実技教科を5教科の2倍にするケースが多い(東京都など)が、鹿児島県のように10倍にするケースもある。
⑤基本的に5段階評価。よって、5点 x 9科目 = 45点が満点となる。この素点をベースに総合得点に換算される(東京都は300点満点に換算される)。
以上から分かる通り、各都道府県別に内申書の制度はバラバラですので、小学生保護者目線においては、自分が住んでいる地域のルールを把握することが重要となります。
東京都での内申書のインパクトはどの程度なのか…日比谷に受かりたいならもちろん「オール5」が必要
内申点はいつ決まるのでしょうか。東京都の場合は、調査書の評定(内申点)は「中3の2学期の成績のみ」が対象になります。実務的には1学期の成績が2学期に影響しますので、中3の1学期と2学期の過ごし方が極めて重要になります。
内申点の算出方法ですが、「5教科×5段階評定」と「実技4教科×5段階評定×2倍」の合計65点満点です。つまり、実技4教科の比重が40点/65点となり、61%を占めることになりますので、主要5教科よりも実技4教科の方が点数の上では大事ということになります。そして、この65点が300点に換算されることになります。
それでは、全体の中での内申点の位置付けを見てみましょう。都立高校の一般選抜(学力検査に基づく選抜)では、原則、学力検査700点、内申点300点、スピーキングテスト20点の合計1,020点で判定されます。どんな入試でもそうですが、合格点付近には多数の受験者がいますので、まさに1点の獲得が合否を分けます。内申点はその競争の中での300点ですので、内申書のインパクトが大きいことが良くわかると思います。
市進教育グループの公開資料によれば、おおむね、内申点2/65点(つまり9.2点/300点換算)で偏差値1くらいのインパクトがあります。日比谷高校の合格可能性80%の目安ですと、学力検査の標準偏差値71、内申点63点/65点(=290点/300点)ですから、内申点はオール5を取るような努力が求められることが分かります。
内申書の歴史
内申書は実は約100年に及ぶ長い歴史を持ちます。その100年間の間で、振り子のごとく制度設計が揺れ動いてきました。保護者目線において内申書の歴史を俯瞰する場合、以下の3つの視点を持つと理解しやすくなります。
①学力評価者は「誰」なのか。中学校側が「内申書」で、高校側が「筆記試験」。
②「何」を評価するのか。中学校側の定性的な準備過程が「内申書」で、高校側の定量的な一発勝負が「筆記試験」。
③評価の「判断基準」。相対評価ならばルールに厳格に運用できるので(学校間格差問題を除けば)信頼性を担保できるが、絶対評価の場合はインフレしやすく信頼性が欠ける。
さて、上記3つの視点を持ちながら歴史的変遷を眺めてみましょう。
内申書は、今から約100年前、戦前の1927年(昭和2年)に誕生しました。当時、大都市に存在する難関旧制中学校への筆記試験での受験が過熱した結果、受験地獄ともいえる状況に陥っていました。当時、筆記試験での一発受験に失敗して親子心中する事件などが発生していました。なんだか、2025年現在の中学受験の過熱化に似ていますね。このような状態を改善すべく、1927年に筆記試験一辺倒の入学選抜方法を廃止するために、内申書が誕生しました。内申書第一主義、という考え方です。つまり、内申書というものは、加熱する筆記試験一発競争を緩和するために誕生したのです。
しかし、その後、内申書は廃れていきます。内申書評価が「絶対評価」に基づくものであることから、旧制中学側が受験者の学力を正確に判定できない問題や、旧制小学校間に存在する学力格差を考慮していないことから、旧制中学側からの批判が増加しました。学校間格差問題は、この時から存在していたことになります。そして、時間の経過とともに、もとの筆記試験一発競争の形に戻っていきました。そして第二次世界大戦を迎えます。
戦後はアメリカの占領政策のもとで教育改革が進められました。内申書は選抜の資料としてではなく、中学校と高等学校との接続を前提とした、高校入学後の指導のための資料として活用する前提が取られました。また、戦前の内申書に記載される学業成績が「絶対評価」で機能しなかった反省を踏まえて、内申点は「5段階相対評価」(5:7%、4:24%、3:38%、2:24%、1:7%)が採用されました。つまり、これでは中学校間の格差が存在する場合は、公平に機能することはありませんが、内申書はあくまでも指導のための資料なので問題はなかったようです。
しかし、1956年の学校教育法施行規則一部改正において、高等学校が「選抜のための学力検査」を行うことが明記され、1963年の同法施行規則第59条の一部改正において、選抜する側の高校の優位が確立します。ここで、内申書は選抜目的のための資料として再定義されることになりました。
1966年には内申書重視策が採用され、一発勝負となる筆記試験には弊害も多いことから、それまで得点比率が内申書と筆記試験が50:50だったものを、内申書の比重を更に高める施策に変化しました。戦前の1920年代の雰囲気に戻ったことになります。1960年代といえば学生運動が盛んだった年代ですから、「中学校教員が内申書制度を利用して生徒を抑圧している」という見方が出てくるのは自然なことだと思います。尚、中学浪人を出したくない中学校が、5段階相対評価を改ざんするなどの問題があるとの報道や、高校側が中学校間に学力格差があることを問題視して内申点の調整を自ら行っていたとの報道もされています。
そして、2001年の大きな転換点を迎えます。内申書の原簿にあたる指導要録の総合評定において、それまで戦後から約50年間継続した「相対評価」を廃止し、「目標に準拠した評価」が採用されました。つまり、学校に進学して学習するのに必要な学力を身に付けているのかという「資格」という考え方です。
しかし、「目標に準拠した評価は単なる絶対評価ではないのか」、という内申書に対する信頼性問題が発生し、内申書より当日の学力検査(筆記試験一発勝負)を重視する傾向が強まりました。当時の東京私立中学高等学校協会は「統一テスト」の実施を主張して、東京都教育委員会はこれに反対するなどの動きがあり、2025年現在でも統一テストは実現していません。
以上が内申書の約100年の歴史です。
「学校間格差」は古くて新しい問題
上記の通り、内申書については戦前から旧制小学校の学校間格差が問題になっていましたし、戦後も1960年代には中学校間の格差が問題になっています。2025年現在のXでも、学校間格差が再び浮上しています。つまり、現在発生している問題は、歴史的には既に存在しており、古くて新しい問題だと考えるのが自然でしょう。
そんな学校間格差ですが、実は可視化されたのは、つい最近のことです。文部科学省が2007年(平成19年)に開始した全国学力・学習状況調査(全国学力調査)において、全国の中学校の学校間格差がヒストグラムという形で可視化されるに至りました。これにより、内申書の学校間格差という問題がよりクローズアップされるようになりました。それまで、統計データという形で学校間格差が可視化されてこなかったことは、驚きですよね。
学校間格差が存在することを前提に、内申書制度をどのように運用していくべきなのか。現在は、各自治体がそれぞれ独自に、この問題に取り組んでいます。例えば東京都では、内申書の「評定の客観性・信頼性の確保に役立てる」ことを目的に、都内公立中学校の「各教科の評定状況」などを詳細に公表しています。しかし、調査結果公表の前段階で、公立中学校の校長が中学校3年生の成績一覧表を持ち寄り相互にチェックし合う、などの自主的な相対評価調整が発生しているとの報道もあります。
以上を、中学受験か高校受験かで迷っている小学生保護者の目線で纏めると、内申書は「目標に準拠した評価」という絶対評価に近い建前で運用されているが、何らかの相対評価の概念も反映されている可能性が高い、という見方をするのが自然かと考えます。
それでは、評価手法が統一されている自治体は無いのでしょうか。実は存在します。最近の事例では、評価の統一性に地域で取り組んだ京都府の乙訓(おとくに)地域が挙げられます。乙訓地域は京都府南西部の日向市・長岡京市・大山崎町の2市1町からなる地域で、中学校数は8校、教職員の人事異動はおもにこの地域内で行われています。2011年に、同地域の校長会が評価の統一性を推進する目的でプロジェクトが開始し、地域共通の評価基準を教員主導で開発し、「乙訓スタンダード」と呼ばれています。成果としては、①評価の信頼性が向上(生徒・保護者にとっては地域のどの中学校に進学しても同じ基準での評価が受けられることになった)、②評定の忙しさが改善し、そして、③説明責任としての客観性確保、などが報告されています。
興味深いのは、毎年冬に内申書問題が騒がれるXの世界でも、「乙訓スタンダード」という単語が出てきた歴史はありません(よって、実験的に私が2025年1月に初めて同単語をツイートして歴史を作りました)。要するに、内申書問題は各都道府県で分断された世界であり、Xの教育クラスターにおいて表層的な不平不満の現象が語られるだけで、歴史的背景や他都道府県での取り組みなどが話題になることは少ないのが実態です。
2025年現在、Xでの内申書への不信感
Xで内申書に対して不信感を持っている方の主張を分析すると、おおむね、以下カテゴリーに集約されます。















