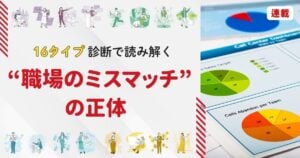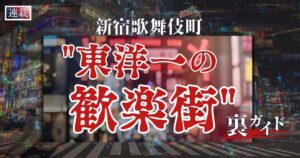「ディズニーの待ち時間」「通販番組」に学ぶ、周りの人間への嫉妬心を抑える方法

これまでの人生の中で、誰かを羨み、妬ましく思った経験を持つ人も多いかもしれない。行動経済学コンサルタントの橋本之克氏は、「それは『アンカリング効果』にハマってしまっている」と指摘する。日常に溢れるアンカリング効果を自覚し、自分の心を落ち着かせる方法について、橋本氏が解説する。全3回中の1回目。
※本稿は橋本之克著『世界は行動経済学でできている』(アスコム)から抜粋、再構成したものです。
第2回:なぜ「この株はあのとき売っておくべきだった」と後悔してしまうのか?行動経済学が明らかにする人間の心の仕組み
第3回:「150ドルもらえても、100ドル支払うほうがイヤ」……人はどうしても“不合理な判断”をしてしまう
目次
人間の判断はすぐにゆがめられる
「同期が自分より先に出世してしまった」
「後輩がどんどん成績を伸ばして活躍している」
こんなとき、心がモヤモヤして妬ましい、腹立たしいという気持ちになってしまうことはないでしょうか。
そう思ってしまうとしたら、あなたは行動経済学で言う「アンカリング効果」にハマってしまっているかもしれません。
「アンカリング効果」とは、「アンカー」(=船のいかり)の位置によって、情報の判断がゆがめられてしまうことを言います。
いかりには、船をその位置で安定させる役割がありますが、人間の心理に働いた場合は「どこにいかりを下ろすか」によって、情報や事実の価値判断や予測が変わってしまうのです。
行動経済学の大家、アメリカのダニエル・カーネマン教授らによる有名な実験があります。
ひそかに仕掛けを施したルーレットを用意します。このルーレット、被験者からは0〜1100の数字のうちのどこかで無作為に止まるように見えますが、実際は「10」もしくは「65」のどちらかで止まるよう仕組まれています。
被験者は、そのルーレットを回してどちらかの数値を見せられたあとで、「国連加盟国に占めるアフリカ諸国の割合」を推定するよう求められます。
すると、ルーレットで「65」の数値を見せられたグループが答えた値の中央値(さまざまな答えがある中で、最大値と最小値のちょうど中央に来る値)が45だったのに対して、ルーレットで「10」の数値を見せられたグループの中央値は25だったのです。
ルーレットの数字には何も意味がなく、そのあとの質問と何の関係もないことが明らかなのに、質問の答えが直前に見たルーレットの数字に引きずられてしまったわけですね。