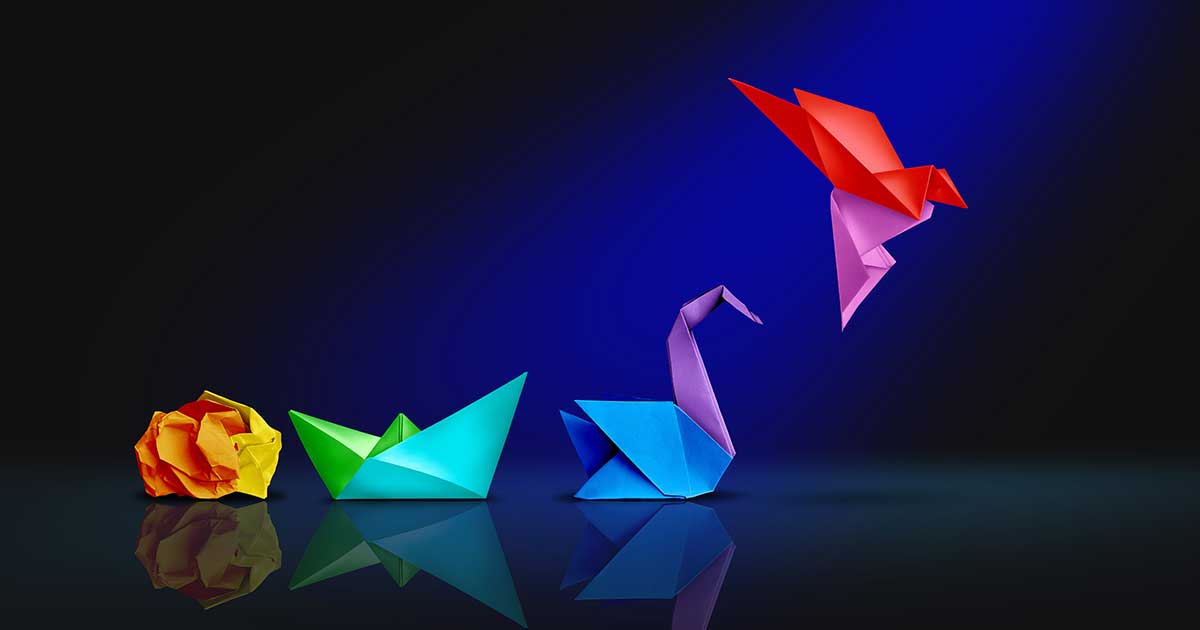羽生結弦の“勇気”の話をしよう。絶望と死神ばかりの世界…興行の世界で希望に手を伸ばす“勇気”の話を。『羽生結弦をめぐるプロポ』「勇気」(2)

目次
手を伸ばす勇気
絶望ではなく、希望と共に前に進む勇気。
その希望とは自分だけの希望ではないみんなの希望。
羽生結弦という存在と、大好きな を「使う」勇気。
そうだ、勇気だ。
多くの人は「好き」をそうした他者のために惜しみなく「使う」ことを躊躇する。それは当たり前の話で、生きるための業なのだから当然の話。誰に非難できることではない。私だってそうだ。まず自分の生活なり、達成がなければ生業は成り立たない。まず自分だ。
しかし、そうではなく惜しみなく「使う」ことを躊躇しない勇気の人はいる。自分のこれからがどうなるか、お金だって欲しいし仕事がいつまで続けられるかわからない。寿命の前に選手寿命という限界が必ず訪れるアスリートならなおさらだ。
フィギュアスケートに限らずスポーツとは怪我のひとつで選手生命が絶たれる、つまるところ仕事を失う残酷な世界である。
芸術だってそうだ、ここは創作でもいいだろう。どれだけの作者が心半ばに消えたことか。書けなくなる、描けなくなる、弾けなくなる、吹けなくなる、撮れなくなる、踊れなくなる、演じられなくなる、何も考えられなくなる――そうした「何もできなくなる日」はある日突然訪れる。あるいはじわじわと自身を追い詰める。
それが年齢か、心の病か、あるいは才能の枯渇かはそれぞれだが、その日は若くしてやってくることもあれば幸いにして死のその時まで来ないこともある。
創作者は常に死神に取り憑かれている
創作者は常に死神に取り憑かれている。その鎌をあてがわれるのが早いか、遅いかでしかない。
ある意味、フィギュアスケートはスポーツと芸術の良い面と同時に残酷な面を二重に負っているともいえる。冒頭に引いた『メダリスト』はその厳しさと喜びとを実に丁寧に描いていると思うが、そこに羽生結弦を想うのは必然でしかないだろう。
そのアニメ化作品『メダリスト』の主題歌でもある米津玄師『BOW AND ARROW』PVの羽生結弦と作品とのシンクロニティもまた必然である。「行け」そして「飛べ」こそ勇気の証。
これまでも歴史における興行の厳しさは書いてきた。例えばヴァーツラフ・ニジンスキーのロンドン公演、後世の偉人であってもエンタメの死神は興行の失敗という悪夢を突きつけられた。※
数字は実入りどころかその後の人生にすらダイレクトに響く
「(ロンドン公演「セゾン・ニジンスキー」)最初の二週が終わったところで、ニジンスキーが高熱を発して倒れ、熱は三日間下がらなかった。おそらくインフルエンザだったと思われる。(ロンドンの劇場の)契約書には「連続して三日間ニジンスキーが出演しなかった場合には契約は即座に解除される」という項目があったため、「セゾン・ニジンスキー」はあっけなく幕を閉じた」