GW明けに依頼が増える!退職代行を利用する新卒社会人「だるいから…」どんなにくだらない理由でもバックレる新入社員が正しい理由
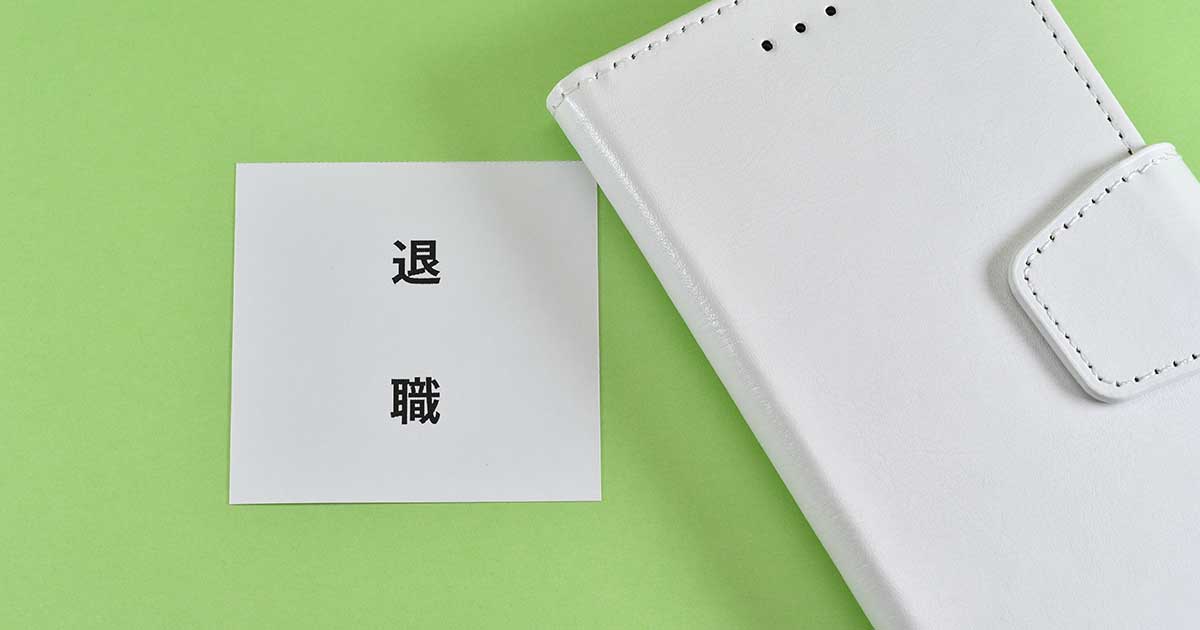
今年も新入社員が会社に入社してもう1カ月。全国転勤のある企業なのであれば、そろそろ初任地に引っ越したところだろうか。そんな中でこの時期にネットニュースで話題になるのは「入社後すぐに辞めた新人」の話だ。石の上にも三年ということわざもあるが、記事を読んで「そんなすぐに辞めちゃだめだろう」とついつい怒りたくなってしまう読者がいる限り、この手の記事は配信され続けるだろう。しかし経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「どんなにくだらない理由でもバックレる新入社員が正しい」と語る。一体どういうのことなのか。小倉氏が詳しく解説していくーー。
目次
新卒社員の7割以上がGW明けに「会社に行きたくない」と回答
ゴールデンウィークが明けた日本の職場に、静かな動揺が走る季節となった。毎年この時期に、いわゆる“五月病”がメディアで語られるが、近年ではより現実的で深刻な兆候が数字として表れている。退職代行サービスの依頼件数が、5月に急増するという現象である。
TBS NEWS DIG(5月6日)に報じたところによれば、退職の意思を代行して伝える「退職代行モームリ」では、年間で最も依頼が集中するのが5月だとされており、2025年も5月単月で298人が依頼した。特に新卒社員からの依頼が顕著であるという。退職代行を利用した22歳の新卒社員は、4月に入社したばかりだったが、10日後に雇用契約書を見て、事前に聞いていたはずの退職金が記載されていないことに気づいた。先輩社員に確認すると、残業時間も募集要項の5倍から6倍に達することが判明したという。不信感が積み重なった結果、自ら退職を申し出ることなく、退職代行サービスを通じて離職を選択した。
同様の傾向は一事例にとどまらない。産経新聞(5月4日)によれば、一般社団法人「日本リスクコミュニケーション協会」が取りまとめた報告書「新入社員の早期退職に伴うリスク対策」では、新入社員の離職がゴールデンウィーク明けに集中する理由として、採用時と実際の業務との間にある「仕事内容と待遇面のミスマッチ」、および「職場環境・サポート体制の不足」の2点が主要因として指摘されている。報告書では、日本労働組合総連合会による過去の調査データも引用されており、新卒社員の7割以上がゴールデンウィーク明けに「会社に行きたくない」「辞めたい」と感じたと回答した。













