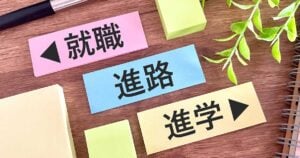日本フィギュアスケート発祥の地…羽生結弦の原点を、想う。仙台市アリーナ開館記念イベント「The First Skate」エッセイ(2)

目次
アスリートたる誇り

これからの、若者たちの群舞。
宮城県、仙台市アリーナ(ゼビオアリーナ仙台、以下ゼビオ)開館記念アイスショー「The First Skate」はアイスリンク仙台のスケーター20名以上による「Legends Are Made」の群舞から始まった。
黒の練習着もまたフィギュアスケート選手のアスリートたる誇り。練習着に限定したわけではないスタイルだが、いずれにせよ私はこの「黒」が好きだ。
銀盤に浮かぶ黒はその四肢をよりよく映す。それそのものに映す。クラシックも、モダンも、コンテンポラリーも練習着は黒が定番、モダンやコンポラならむしろ本番で飾り気のない黒を纏うことも多い。
美しい装飾の足し算の美があるなら、こうした引き算の美もある。普段の練習そのままだからこそ訴えかけるものがある。等身大の若者たちの群舞に、羽生結弦はもちろん、遠い昔のフィギュアスケーターたちもまた見える。私には見える。
その中には歴史に名を残した者もいれば、記録の中に名前だけがある者もある。そこにまで至ることなく消えていった者もまたいる。つるまいかだ作『メダリスト』ではないが残酷な世界である。フィギュアスケートだけでない舞踏芸術とするなら山岸凉子『舞姫 テレプシコーラ』を私は最高傑作のひとつと挙げるが、かくも芸術とは美しく、ゆえに残酷なものだ。
「フィギュアスケート王国」であること
そして、スポーツ競技であり他者採点による数字の優劣で順番をつけられるフィギュアスケートは別の意味でも残酷だ。ここに舞う若きスケーターたちはその中に飛び込んだ勇者だ。
あの日の羽生結弦と同じ勇者――だからこそ力強く頼もしく、それでいて「もののあはれ」を想う。
私たち日本人の美意識「あはれ」とは決して後世の言葉としての「哀れ」ではない(私は単純化したこの言葉が嫌いである)。「あはれ」とは叙情であり幽玄であり無常であり、その先の感動である。故にこの演出からして、私は涙をこらえきれなかった。
この若者たちに東日本大震災の記憶はほぼないだろう。岩手で被災した私の妹、そのお腹の中にいた長女が今年中二である。そうした子たちがこうして育ち、3000人以上の観客や関係者の前で群舞を披露している。仙台は日本のフィギュアスケート発祥の地であり故郷、いまもフィギュアスケート王国であることをこの子たちが証明してくれている。
やがて、群舞の間に間にまさに伝説ーーレジェンドたちの登場。曲は「Nessun Dorma」(「誰も寝てはならぬ」)に変わり、本郷理華、本田武史、鈴木明子、そして羽生結弦がそれぞれに舞い、再びの群舞の輪に入った。みなそれぞれに「これから」を抱くスケーターたち、それは羽生結弦もまたそうだ。世界の羽生結弦、歴史の子、時代の人となったいまも、彼の心はこの仙台、羽生結弦少年のままにある。
ひとりのためだけに
豪華な群舞が去り、東北高校1年の小山蒼斗さんが「Festive Overture, Op.96」(「祝典序曲」)を披露する。
東北高校、言わずと知れた本田武史、荒川静香、もちろん羽生結弦の母校である。