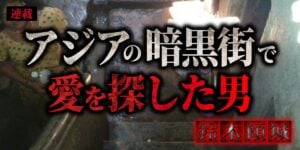俺は絶対に破滅する…「2階こそホンモノ」東南アジアで最も邪悪な街のひとつ・パッポン。狂騒の80年代、男はゴーゴーバーで愛を探した

1980年代から90年代にかけて、アジアの歓楽街は熱気と混沌、そして甘美な腐臭に満ちていた。高度経済成長のあぶく銭を握りしめ、男たちは夜の底へと沈んでいった。これは、かつて暗黒街に沈み、熱気と混沌に溺れながら「愛」を探し求めた男の回想録である。
「ブラックアジア」「ダークネス」でカルト的な人気を博す作家・鈴木傾城氏による連載「アジアの暗黒街で愛を探した男」第1回――。
目次
1986年の夏、バンコクの歓楽街パッポンで私は狂っていた
「こんなことをしてたら、絶対に俺は破滅する……」
日本では第三次中曽根内閣が発足して自民党の絶頂期となっていた1986年の夏。私にとっては2度目のタイだったが、バンコクに到着して適当な宿を取ったあと、小雨が降る中ですぐに直行したのがバンコク最強の歓楽街パッポンだった。
街の喧騒の中に入って、私はつくづく自分にあきれ果てていた。私はバックパッカーになるつもりはなく、何度も海外に向かうような生き方をしたいとも思っていなかった。にもかかわらず、またタイに来てしまっていた。
「いったい、どうするんだ? 破滅したいのか?」
そんな問いかけがぐるぐると自分の中を巡った。だが、この瞬間の私にとっては、パッポンがすべてだった。東南アジアでもっとも邪悪な街と呼ばれたパッポンの魅力に取り憑かれていた。たぶん、私は狂っていたのだろう。
1960年代から1970年代のベトナム戦争の頃、アメリカ軍の兵士は最前線ベトナムから一時的に戦地を離れ、R&R(休養と娯楽)地のタイに休暇にやって来ていた。
そこで、この兵士たちの落とすカネを狙って、バンコクのシーロム地区パッポン・ストリートではあちこちにゴーゴーバーが誕生した。それが、ベトナム戦争が終わったあとも生き残って、観光で来た世界中の男を引き寄せていたのだった。私もまたそこに取り込まれていた。
ゴーゴーバー『リップ・スティック』
2か月ぶりに入ったパッポンは相変わらず白人(ファラン)の男たちがギラついた目でうろつき、バーの入口で女性たちが声を上げて客引きをしていた。蒸し暑いのと、まとわりつく霧雨で私の身体は薄い膜が貼ったように濡れた。
私がひとりで歩いていると、客引きやポン引きがひっきりなしに寄ってくる。そういうのを無視して歩いていると、ゴーゴーバー『リップ・スティック』が目に入った。急に、そこで知り合ったマイのことが脳裏によぎった。
最初の旅のとき、社会見学のつもりで初めてのパッポンで入ったゴーゴーバーが、この『リップ・スティック』だった。そこで私はマイという同い年の女性と知り合って好きになってしまい、しばらく私の泊まっていた安宿で一緒に過ごしていた。
彼女は私を失いたくないと思ったのか、外出することすら許さなかった。その彼女の束縛があまりにも強くて耐えきれず、とうとう私は別れを切り出し、泣いてすがりつく彼女を引き剥がすようにして逃げた。
一方的でひどい別れ方だった。本当はもっと優しくしたかったのだが、あまりにも嫉妬と束縛が強い彼女には耐えられなかった。とにかく逃げたいと思ったのだ。あれから、私は『リップ・スティック』には足を踏み入れなかった。
マイは『リップ・スティック』で働いていたのだから、私と別れたあとに戻った可能性はかなり高いように思えた。会いたいような気もするが、そのままそっとフェードアウトするのがお互いにとっていいはずだ。
私は『リップ・スティック』を通り過ぎて、マイのことを頭から消そうと努力した。歩いていると、あちこちのバーからつんざくような音楽が漏れ聞こえる。ファランたちにまぎれて、ストリート売春をするレディーボーイたちの姿も見えた。
そのとき、ひとりの客引きの男がいきなり私の肘をつかんで「面白いショーがある。来いよ」と英語で言ってきた。マイのことで頭がいっぱいで、とてもそんな気にはならなかったが、男は強引だった――。