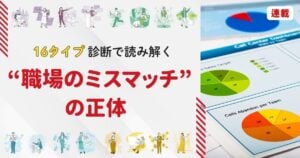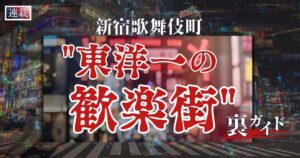「学歴が低い人は不幸」「こんな子生まれるなら結婚しなかった」過剰すぎる教育熱…高学歴親の悲しい末路

精神科医で「子育て科学アクシス」代表の成田奈緒子氏は、「高学歴の親ほど子育てに悩む傾向がある」と言います。わが子を愛するがゆえに過剰な期待や配慮を押しつけすぎ、結果子育てに失敗してしまう。そんな高学歴親の実態を成田氏が語る――。全5回中の2回目。
※本稿は成田奈緒子著『高学歴親という病』(講談社)から抜粋、編集したものです。
第1回:ここまできたZ世代親の過干渉「エントリーシート代筆」「大学の履修登録」…人生を狂わせられる子と”混乱する”高学歴親
「学歴がなければ不幸になる」と思う親の過ち
子育ての「三大リスク」は「干渉・矛盾・溺愛」です。
わが子ばかり見てしまう。過剰に愛情をかけてしまう。それが溺愛のイメージです。皆さん、わが子に良かれと思って動いています。特に高学歴親は経済的に余裕のある人が多いので「良かれと思ったこと」ができてしまいます。一方で、見分けはとても難しいのですが、干渉がなくあふれる愛情がある「甘やかし」は私の中では決してネガティブなものではありません。
溺愛の問題は、それが干渉につながりやすいこと。そして、この干渉を続けていくと、それを正当化するために今言ったことと以前言ったことに矛盾が生まれます。こうやって、溺愛をベースに干渉、矛盾が乗っかってくる。つまり子育ての「三大リスク」は連関しているのです。
高学歴親がわが子を溺愛する際の特徴は「聡明な先回り」だと考えます。皆さん、知識があって頭脳明晰なので、子どもを見ていると「このままではきっと失敗する」といった近い未来に起きることがある程度見通せます。その「見通し力」が優れるあまり、転ばぬ先の杖を用意してしまいます。
あるお母さんは長い不妊治療の末に女の子を授かりました。30代後半の高齢出産です。このため「目に入れても痛くない」とかわいがりました。印象的なのが「せっかく授かった大切な子どもなのだから、私が経験したすべての幸せをひとつ残らず同じように経験させたい」と言ったことです。自分がやってきたピアノなどの習い事、中学受験のための塾など、すべてやらせました。
ところが、娘は夫婦が期待したほど小学校で良い成績を取れませんでした。ショックを受けたお母さんは、娘が小学3年生になると夜10時、11時まで塾に通わせました。夫婦ともにフルタイムで多忙にもかかわらず、塾への送り迎えなどを手分けして行いました。
「少しやりすぎでは?」と伝えましたが、「ちゃんと学歴をつけないと幸せになれない。このままでは不幸になってしまう」というのがお母さんの持論でした。これだと「学歴が低い人は不幸」という論理になります。本人は気づいていませんが、彼女のなかに強い差別意識を感じました。
「子どもの幸せを思って」モンスターペアレントが生まれる背景
こういったわが子を溺愛するがゆえの先回りは、他の高学歴親にも見られます。小学校で、高学歴のお母さんが「うちの子が不利な立ち位置になってしまう」といった見通しを立てると、担任の先生に何かと口出しをしてしまうと聞きます。たとえば、運動会で高学年は組体操をします。すると、わが子がペアを組む子どもについて「あの子はよく文句を言うから、別な子と組ませてほしい」と先生に頼み込むのです。
そこで最終的に配慮してペアを替えると、それが子どもに返ってきます。親が口出ししたことを察した子どもたちから、そのことを責められたりします。最も傷つき、嫌な思いをさせられるのは子どもなのです。
ほかにも「悪口を言われたからクラスを替えてほしい」「〇〇ちゃんとは6年間絶対に一緒のクラスにしないでほしい」といった、とても理不尽な要望を出してしまいます。その動機付けは、自分の子どもに「とにかく幸せに過ごしてもらいたい」という一点に尽きます。
先生からすれば「それは平等性に欠けるのでできません」と言いたいところですが、面倒は回避したいので従ってしまいます。親からすれば、悪気はないし、他の子に不利な思いをさせようとも考えていません。溺愛の果てに、自分でも気づかないうちにモンスターペアレンツと化しているのに、本人からすれば機転を利かせてトラブルを回避したと安堵しているのかもしれません。
このように高学歴親が溺愛してしまう要素のひとつに、高齢出産があります。大学や大学院を卒業しキャリアを築いた親たちは晩婚傾向にあります。他の友人が先に結婚して優秀な子どもを育てていると、とても幸せそうでキラキラ輝いて見えます。成功例があると、後発組としてはある意味辛い。後から来て、このまま自分が何もしなければダメな子になると焦ります。溺愛は本人の意図しないところで、リスクのある子育ての出発点になるのです。
「こんな子が生まれるなら妻とは結婚しなかった」と語る父
ある自治体の支援機関で、ヤスコさんという女性に出会いました。会社員で役職に就き、輝かしいキャリアを積んでいました。夫も一流企業勤務。私立中学校に通う長女と、同じく私立の小学校に通う次女を育てる、絵に描いたような高学歴夫婦でした。
それなのに中学校に通う長女の暴力に悩んでいました。気に入らないことがあると暴れ出すため、ヤスコさんも娘に手を上げてしまうと言います。
最も衝撃的だったのは、長女が次女の制服をハサミで切ってしまったことでした。切り刻まれたスカートやブラウス。泣き叫ぶ次女。ヤスコさんは激しい怒りにかられ、長女に暴力をふるってしまいました。
実はヤスコさん自身、妹と2人姉妹で実母との間に深い確執がありました。長女であるヤスコさんは必要以上に厳しい態度をとられていたのに対し、妹は明らかに贔屓されていました。感情の起伏が激しい母親の矛先はヤスコさんに向かっていました。母親の機嫌を損ねないよう気を遣う長女に対し、次女である妹は何をしても許されるのです。母親からの愛情が感じられず、辛い子ども時代を送っていました。
「すごくしんどかった。だから、私は正しい子育てをしようってずっと思っていました。自分と妹が育てられたような育て方をしてはいけない。私はちゃんとした子育てをするんだ。そう思いました」
実母を反面教師にしてきたはずなのに、結局おまえは同じ子育てをしていたではないか――切られて布の山になった制服が、ヤスコさんがやってきたことを全否定しているかのようでした。

とはいえ、ヤスコさんは特異な母親ではありません。子育て中のお母さん、お父さんの多くが、「自分の親は子どもをすぐに叩く人だったから、私は叩かないようにしよう」「話を聞いてくれなかったから、僕は聞く耳のある親になろう」と一度は決意します。ところが、自分が経験したパターンしか知らないため、つい育てられたように育ててしまいます。自分の親の子育てに疑問を持っているのに、無意識のうちに親を真似てしまいます。
ヤスコさんと話をすると「自分はダメな人間だ」と自己肯定感の低さやコンプレックスが見受けられました。高学歴で社会的な地位もあるのに、自分を認めてくれなかった母親の呪縛から逃れられないのです。常に不安がつきまとうので、感情が乱されやすい傾向にありました。
夫のほうは、私との面談に一度だけやって来ました。妻に言われ嫌々ながら、だったのでしょう。険しい表情で持論を語り始めました。
「仕事は管理職です。私の中のポリシーに従って人付き合いというか、人とのかかわりをすごく考えてやってきた。私が築き上げた人間関係のルールというものとは、娘は真逆の行動をしている」
そう言って、自分の娘がいかに間違っていて、自分が正しいかをとうとうと語るのです。
「娘が幼少期のころも、私が良かれと思っていることを伝えたり、注意しただけなのに、娘からは反抗されるし、妻からは虐待に近いからやめなさいと叱られた。まったく承服しかねる。次女は私が言ったことを聞き取ってそのように行動して、学校でもうまくやっている。それなのになぜあの子だけ許容してあげないといけないのか。全く理解できない。だから、これ以上長女を受け入れる気はありません」
そして、最後に言った言葉が衝撃的でした。
「この子が生まれることが予測できていたなら、私は妻と結婚しなかったと思います」
自分の価値観が絶対なのでしょう。自分と異なる意見に対し非常に頑なでした。ほかにも、自分は親にスパルタで育てられたが、その教育のおかげでここまで来たという「生存者バイアス」がありました。
サバイブ(生存)した、つまり何らかの苦しみを乗り越えた自身の感覚のみを基準として判断してしまうのです。サバイブできなかった側の気持ちを考えられないため、娘にも厳しく接していました。その点は、高学歴で優秀な父親に見られる特徴のひとつでしょう。