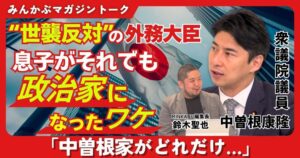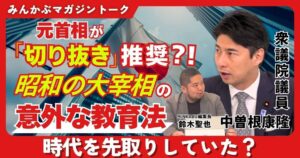竹中平蔵「中国との経済安保、規制厳しくしてはいけない」…「もう終わり」と言われ続ける中国が今も成長をしている理由(特集:丸わかり中国経済 第1回)

いよいよ1カ月後に迫った5年に1度の共産党大会。3期目続投確実と言われる習近平政権だが、この10年間、中国はどのような変化をしたのか。みんかぶプレミアム特集「丸わかり中国経済」(全10回)の第1回は、前・胡錦濤政権から中国の動きを観察してきた竹中平蔵さんが、アメリカと並ぶ大国へと躍り出ようとする中国の近年の動向と、今後の付き合い方を説く。
目次
バランスシートが痛んでいる中国がなぜ経済成長を続けることができるのか
10月16日から開催される第20回中国共産党大会を前に、日本でも中国という国に対する関心が改めて高まっています。ご存じの通り、習近平がこれまでの党の慣例を破って、3期目続投をすることが確実視されています。では、私たちはこの国に対して、どのように向き合っていくべきでしょうか。
近年の中国の状況を見てみると、経済は猛烈な勢いで成長している一方で、バランスシートが痛んでいるのではないかという問題が度々指摘されています。私は、小泉内閣の大臣を退任してからすぐに中国に呼ばれて講演をしたのですが、そのときのテーマが「不良債権をいかに処理したか」でした。その頃からすでに、中国はバランスシートの問題に直面していたのです。一方で、それでも経済成長を続けているのはなぜなのか。そこがいまの中国を見る上で重要な視点になるのです。
このカラクリを説くのは、一言でいうと「ビッグデータ」です。というのも、2007年にiPhoneが発売されました。当時はみな、画期的な携帯電話ができたぐらいの感覚でいたと思うのですが、実はここが大きなターニングポイントになったのです。スマートフォンはいわば小さなパソコンですから、通話をするだけではなく、そこにビッグデータが蓄積されます。ビッグデータが集まれば、人工知能を介して新しいサービスを生み出すことができます。
東大の松尾豊さんによると、iPhone発売から5年後の2012年に、人工知能の画期的な技術進歩があったそうです。いわゆるディープラーニングですが、14億人の国民を擁し、データプライバシーをさほど気にしなくていい中国にとって、ビッグチャンスの時代がやって来た。これが、バランスシートの問題を覆い隠すほど、中国の成長へのポテンシャルを高めたわけです。