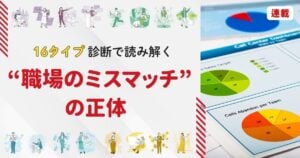「働かないおじさん」に迫るリストラの脅威…「明日は我が身」な30代予備軍の実態

急増する働かないおじさんにキレる若手たち
会社の「働かないおじさん」問題がメディアを中心に騒がれている。おじさんの中には“おばさん”も含意されていると思うが、要するに若手社員から見た40代半ばから50代の中高年社員のことだ。
また「働かない」とは、まったく働かないということではなく、仕事をサボっている人のことだろう。具体的にどういう人たちなのか。株式会社識学が20~39歳の男女の社員から見た「“働かないおじさん”に関する調査」(2022年5月27日公表)を実施している。
それによると自社に「働かないおじさん」がいると回答した社員は49.2%と半数に上る。そして働かないおじさんが仕事中にしていることで多かったのは「休憩が多い(タバコを吸っている・お菓子を食べているなど)」(49.7%)、「ボーッとしている」(47.7%)、「無駄話をしている」(47.3%)がトップ3。続いて「ネットサーフィンをしている」(35.3%)、「プライベート・趣味について調べている」(28.7%)と続く。