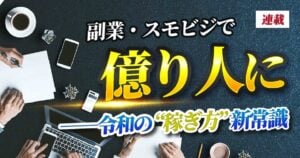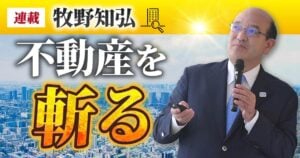迫る金融倒産連鎖、ついに日本へ飛び火の可能性…「リーマン・ショックより恐ろしい」どんな大銀行でも、一瞬にしてお金が消える

シリコンバレー銀行にクレディ・スイス。これらの大手銀行が経営難に陥ったことにより、世界的な金融危機への不安が高まっている。この負の連鎖はいかにして発生し、私たちは現状をどう見るべきなのか。日本人が深く目を向けていない世界経済のいまを、経営コンサルタントの小宮一慶氏が解説する――。
世界中のどんな銀行もつぶれるおそれがある
いまの世界の金融界の関心事は「世界金融危機が起こるかどうか」です。このところ、少しその懸念が後退したので、株価も底堅い展開をしていますが、まだまだ油断は禁物です。この発端となったのは、3月10日の米シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻。SVBが破綻した大きな原因は、米国の金利が急激に上昇したことで、運用している債券に多額の含み損が発生し、そのことに不安を感じた預金者が、一斉に預金を引き出す取り付け騒ぎを起こしたことにあります。
銀行は通常、ALM(Asset Liability Management)を行っています。これは、市場金利や為替の価格変動、流動性といったリスクとリターンを勘案しながら資産と負債を管理していくやり方です。ALMさえしっかりやっておけば、金利が上下したとしても、そこまで大きな影響を受けずに済むはずで、銀行経営の基本とも言えるマネジメント手法です。
しかし今回、SVBでは、このALMが不十分でした。景気の低迷により預金を債券運用に回す割合が増え、金利リスクを増大させてしまった上、金融当局からリスクを指摘されても迅速に対処できなかった。そんな中で金利が上昇し、保有債券の価格が下落したわけです。米連邦準備制度理事会(FRB)のマイケル・バー副議長は「明らかにひどいリスク管理だった」と批判しています。
ところで、銀行というのは、基本的にあまりお金を持っていません。これはどういうことかというと、銀行は主に貸出金利と調達金利の差から得られる「利ざや」で利益を得ていますが、この利ざやは1%あるかどうかです。優良企業への貸し出しなら0.25%やそれ以下ということもよくあります。つまり、かなり利益率が薄いんですね。そのため、少しでも多くの資金を運用に回そうとしているのです。