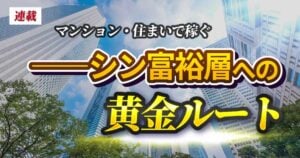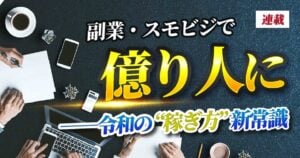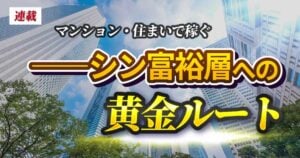地獄の高金利時代到来! 変動型住宅ローンを組んだサラリーマンの悲鳴が聞こえる

決して他人事ではない金利上昇による困窮
「夢のマイホーム」
高度経済成長期によく耳にしたこのコピーの生みの親は、かの阪急電鉄創業者の小林一三だそうだ。
戸建て住宅や分譲マンションの購入は、多くの人にとって人生最大の買い物である。
ここ10年間は低成長であったにもかかわらず、ゼロ金利政策による住宅ローン金利の低下などによって戸建て住宅や新築マンションの需要は比較的堅調であった。
ところが今年に入ってコロナ禍、ウクライナ侵攻、米長期金利などに起因する物価上昇が始まり、住宅需要を支えていたゼロ金利政策が転機を迎えている。
アメリカでは5月に10年物の長期金利が3%台にまで上昇。固定金利型の住宅ローン金利も5%を超えているという状況から考えると、いずれニッポンの住宅ローン金利も、世界経済をけん引する巨大なアメリカ経済の影響を受け、大幅上昇すると考えられる。
もちろん日本銀行が米国の利上げを「他人事」と決めつけ、かたくなにゼロ金利を維持していくという予想も十分妥当性はある。
しかし2022年1月、米国が利上げに動く中「日銀が政策修正を行うのではないか」との推測によって、わが国の長期金利(新発10年債利回り)が6年ぶりの高水準に上昇。これを受けて固定金利型住宅ローンの金利が上昇したという事実から、今後、変動金利型住宅ローンの金利上昇は高確率で起こると考えるべきだろう。
ゼロ金利政策が続くと考えて過大な住宅ローンを組んだ人々にとっては、今の状況は “地獄の入り口” かもしれない。
変動金利型住宅ローンのリスク
ここで変動金利型住宅ローンに潜むリスクについて説明したい。
住宅ローンの種類には「変動金利型」と「固定金利型」があるが、低金利が続いている日本では金利が低い(=金利が上がらなければ支払総額が少ない)前者を選択する人が完全に多数派。住宅金融支援機構が2021年に実施した「住宅ローン利用者の実態調査」によると、67.4%の人が変動金利型を選択している。
ところがゼロ金利のときは有利である変動金利型には、金利が大きく上昇すると毎月の返済額や支払総額が激増してしまうリスクがある。
例えば元金均等返済の変動金利型で借入金3500万円、返済期間35年のローンを組んだ場合、当初の金利が0.45%であれば、毎月の返済額は約9万円だ。これが3年経過後4年目から1%ずつ上昇していき、7年目に4.45%まで上昇したとすると、毎月の返済額は毎年1万5千円ずつ増え、7年目には月15万4千円まで跳ね上がる。しかも元金の減り方が鈍るため、ローンはまだ3000万円も残っている(下表)。
| 経過年数 | 金利 | 返済額/月(円) | うち元金分(円) | ローン残高(円) |
| 1年目 | 0.45% | 90,084 | 76,959 | 35,000,000 |
| 4年目 | 1.45% | 104,894 | 65,972 | 32,211,231 |
| 5年目 | 2.45% | 120,619 | 56,481 | 31,414,286 |
| 6年目 | 3.45% | 137,130 | 48,785 | 30,728,848 |
| 7年目 | 4.45% | 154,302 | 42,555 | 30,134,087 |
ただし、こうした返済額の急増リスクは借りる銀行を変えることによって、防ぐことができる。
「5年ルール」「125%ルール」
毎月の返済額については、多くの銀行が「5年ルール」「125%ルール」などを設けることで急増しないように配慮している。従って、これらのルールのない銀行でローンを組んでいる人は、これらのルールがある銀行の住宅ローンに借り換えると返済額の急増を回避できるのである。
| 5年ルール | 125%ルール |
|
借り入れ開始時または前回の見直しから5年間は、毎月の返済額が変わらない、というルール。 このルールが適用されると(5年間は返済額を変えることができないため)金利が急上昇しても家計に悪影響が及ばない。 |
見直し後の毎月の返済額も、それまでの返済額の125%までしか上げることができない、というルール。 5年ルールのみでは「見直し後にいきなり返済額が倍増した」といったケースも起こりうるが、125%ルールによって、この場合も返済額を「前回の125%」に抑えられる。 |
これら2つのルールがあれば、もし金利が上昇を続けた場合でも、最初の5年間は返済額が一定。その後、5年に一度行われる変更でも、月々の返済額の増加は1.25倍が上限となる。
例えば毎月10万円を返済している人なら、見直し時は最高でも12万5千円までしか増額されない。
ただし「5年ルール」「125%ルール」があっても、急増しないのは毎月の返済額だけである。 金利の上昇による支払利息の増加は通常の住宅ローンと一緒だから「毎月の返済額の内訳で利息の返済割合が増えた結果、最終的な総支払金額が激増する」というリスクが残っている。
つまり
半年ごとに金利が見直された結果かなり高水準まで金利が上昇 → 支払総額が激増 → 毎月の返済の大半が利息のみ → 元金がたくさん残ってしまった結果、ローン終了時に返済不能
ということになりかねない。
買いたい物があってもガマンして何十年も住宅ローンを支払い続けたのに、元金がたくさん残ってしまったためマイホームを売却して返済する、という事態も大いにありうる。
もちろん短期間で急激に金利が上昇する可能性は低いかもしれない。しかし、変動金利型にはこのようなリスクがあるのは間違いないこと。「賃金が上昇した結果、いままでの反動で物価が急上昇。基準金利をやむを得ず引き上げる」ということもありうるのだ。
固定金利にすればリスクは回避できる?
今後、変動金利型の住宅ローンを抱えている人が取れる対策は次の通りだ。
1.固定金利型に借り換える
「低金利なら固定金利型を選ぶ」というのが住宅ローン選択のセオリーなのだが、固定金利型より変動金利型のほうが金利が低く、かつ政府が一貫して低金利政策を推し進めたため、現状では多くの人が変動金利型を選択している。
したがって、ここでセオリーに立ち返って固定金利型に借り換える、という選択肢もあるだろう。
固定金利型は返済額が決まっているため毎月の返済額が増える不安はなくなるが、一方で借り換えには審査もあり、手数料や登記の書き換え費用などもかかる。コストとメリットをよく考えて決断しよう。
2.家計を見直して余力をつくる
返済額が上昇しても支払っていけるように家計を見直して、当面は低い変動金利の恩恵を受けるという考え方もある。余裕ができれば繰り上げ返済をして、金利上昇の影響を抑えることも可能だ。
3.収入を維持できるよう努力する
(ペアローンなど)夫婦の収入を合算することで借入額を増やしたローンを組んだ場合、配偶者が出産や育児のために退職したり、非正規雇用になったりして返済に窮するケースがある。
共働きを前提にローンを組んだのであれば、男性が責任を持って家事や育児を同等に負担し、女性が正規雇用に留まれるようにすることが重要だ。
また今、企業ではデジタルトランスフォーメーション(DX)対応の人材育成に取り組み始めている。勤務先が人材育成している場合は、真っ先に利用してリスキリングにチャレンジすべきである。
勤務先がそれほど社員の教育に熱心でないなら、自分でリスキリングしたり、資格を取得したり、高等教育機関でリカレント教育にチャレンジしたりすることは無駄ではないだろう。