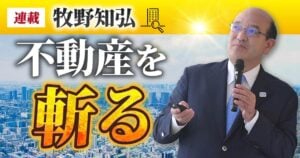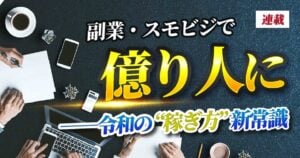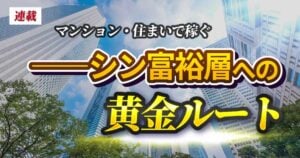「ワンルーム投資」に目がくらんだサラリーマンの末路…売れない、貸せない、危険すぎた遊びの代償

「不動産投資は出口があって初めて結果が出る」と不動産評論家の牧野知弘さんは言う。かつてのように、若い世代が増え続け、アパート需要が伸びる時代ではないにもかかわらず、ワンルーム投資が流行ったのはなぜなのか。「節税欲望」にかられて、サラリーマン投資家や素人投資家がなけなしの銭を握りしめ、ワンルーム投資をした暗すぎる現実と未来とはーー。(第3回/全4回)
※本記事は、牧野知弘著『不動産の未来 マイホーム大転換時代に備えよ』(朝日新聞出版)より抜粋・再編集したものです。
第1回:タワマンに”勝ち組エリート”が住まない理由…住民たちが「考えたくない」悲惨すぎる未来
第2回:今、中国が狙っているのは西日本! 福岡、那覇…不動産の勝機はここにあり!
第4回:晴海フラッグを絶対に買ってはいけない理由…不動産関係者がネットの悪評火消しに奔走?
サラリーマンの隠れ副業「ワンルーム投資」の危険度
節税目的の不動産投資のもう一つの動機が、所得税の節税ニーズである。日本は所得税率の累進性が高いため、一定以上の所得になると稼ぐ割には実入りが少ないという不満が出る。これを不動産投資することで見かけ上の赤字所得をこしらえて、所得を下げ、結果的に節税しようというものである。
この目的に適った投資がワンルームマンション投資である。節税効果という意味ではワンルームでなく、1LDKでも2LDKでも構わないのだが、効率が最も良いのがワンルームなのである。
まず、ワンルームは1戸が面積で6坪から8坪程度、投資総額も1000万円台から2000万円台が多く、サラリーマンでも高給取りであれば手が出る範囲である。また、ワンルームは1LDKや2LDKに比べて投資効率が高い。東京都心であればワンルームは坪当たり1万2000円から1万5000円程度とれる。これがファミリー向けになると賃料単価は下がってしまう。面積の拡大に家賃が比例してくれないからだ。つまりワンルームマンションは収益性もファミリータイプに比べて高いといえるのだ。
またワンルームマンションは同じように節税したいサラリーマンがいれば転々流通するのではないかという思惑もあり、手頃な節税手法として定着したのだった。
不動産投資して赤字を作るとはどういうことかと言えば、ワンルームをほとんど借入金で買って、金利を経費計上する、建物の減価償却を経費計上する、テナント確保等でかかる経費、修繕費などを経費計上するなどして赤字所得を作り、所得税を節税するのがその手法だ。
所得が高いほど節税効果が高いため、平成バブル期などにはサラリーマンの課長、部長クラスの間でワンルーム投資はブームになった。当時のサラリーマンは大抵の会社が副業禁止だったが、なぜかワンルームなどに投資して運用しているのは副業とはみなされないために大勢が手を出したのだ。
しかし、何度も言うように不動産投資にあたっては多くのチェックポイントがある。ワンルームの場合は需給バランスと投資家の懐具合だ。郊外の田園地帯で、テナントなんてあまり見込めないような場所で相続税対策だけに目が眩んで投資したアパートオーナーが、その後、同じようなアパートが周辺に林立してテナントを奪われ、空室に苦しんだことがワンルーム投資でも起こっているのだ。