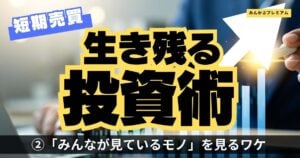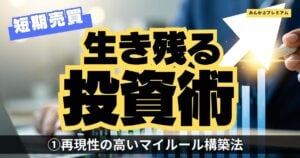「ESGブーム」もうすぐ終わる~躍った投資家が知る本物とニセモノ

空前絶後の市場流行語となった「ESG」とは
株式市場ではさまざまな流行語や新語、造語が浮かんでは消えてきた。最近では「ESG」。環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)のそれぞれの頭文字をつなぎ合わせたものだ。「ESG投資」、すなわち企業の環境対策や社会問題への取り組みを評価に取り入れ株式を売買する手法や、関連の投資信託が人気を集めている。
この言葉は本当によく見たり聞いたりする、という直感は正しい。日本経済新聞の朝刊に限って「ESG」の語を含む記事の数を調べてみた。2015年には28本だったが、5年後の20年には417本へと急増。21年にはさらに加速して707本になり、22年は1~6月だけで443本。単純に2倍して年換算すると886本となる。もちろん、過去最高だ。
この検索は、日経夕刊や日経ヴェリタスなどは含まず、電子版も対象にしていない。紙の朝刊だけでも、毎日2つ以上、紙面にニュースが載っている計算だ。テレビやウェブサイト、広告などまで含めれば、本当に巷にあふれているといっても過言ではない。私は1990年前後のバブル期からずっと国内外の株式市場を取材しているが、こんな流行語はちょっと記憶にない。あえて言えば「BRICs」(ブラジル、ロシア、インド、中国)だが、先ほどと同様の検索をしてみると、2005年から09年の間に年150本前後にとどまる。
知りうる限り、空前絶後ともいえる市場流行語「ESG」。なぜこれほどまでに広がり、これからどこへ行くのだろうか。本稿ではそれを考えてみたい。
欧米の流行をセールスに活用するのは日本の証券会社のお家芸
まずは、問題を一つ。次の文章を読み、●●●に当てはまるアルファベット3文字を当ててほしい。
「環境や人権に配慮する企業の株式に投資する●●●が世界的に広がっている。企業が長期的に価値を向上させるには、社会的責任を果たすことが不可欠という考え方が背景にある。しかし、●●●の手法は確立されているとはいえず、運用成果が上がるかどうか疑問視する向きも多い。(中略)世界最大級の規模を誇るオランダ公務員年金(ABP)は今年初め、環境保護に熱心な企業に重点投資する●●●投資信託を立ち上げた」
私の原稿をここまで読んでいただいた方の多くは、●●●に入る語句はESGだと思われるだろう。残念ながら不正解だ。答えは「SRI」。Socially Responsible Investment の省略語で「社会的責任投資」と訳されることが多い。
問題として読んでいただいた文章は、私がロンドン特派員をしていた2003年、日経金融新聞という専門媒体に書いた記事だ。企業評価に環境や社会の視点を入れる投資の手法は20年近くも前にあり、ヨーロッパではそれが連綿と続いてきたのだ。
日本の証券会社は欧米の流行をめざとく取り入れ、金融商品のセールストークに使うのが得意だ。本質を深く考えず、次から次へと言葉を乗り換えていく。だから、2000年代初めには「SRI投信」がはやり、最近は「ESG投信」を売り込んできた。SRIもESGも本質的に重なる部分が多いのに、まったく違う画期的な新製品のように投資家に売り込む。高い手数料を取りやすいからだ。
流行を追っているだけだから、飽きられたら次のセールストーク、新しいテーマを見つけるだけ。最近は証券会社の方々と話していると「ESGもそろそろ終わり……」といった雰囲気が伝わってくる。BRICsと同じく、ESGも遠からず忘れ去られるのだろうか。
ESGが流行語でなくなる時‥それは当たり前になる時
資産運用の本場である英国や米国でも「ESGは消える」と断言する専門家は少なくない。私がインタビューした範囲で紹介すると、例えば英シュローダーのピーター・ハリソンという経営者はこう断言している。
「あと5年もすれば、だれも『ESG』について語らなくなる。なぜなら、あらゆる資産運用会社が実行するからだ。ESGはまったく当たり前のことになる」
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズという米大手運用会社のサイラス・タラポールバラ最高経営責任者の言葉も紹介する。
「あと数年するとESGについて単独で語られることはなくなる。多くの財務情報と同じく、判断材料の1つになるからだ。だれも運用者に向かって『1株利益(EPS)を考慮しますか』などとは聞かない。それと同じだ」
ちなみに、ハリソン氏のインタビューは2021年、タラポールバラ氏は2022年のものだ。両氏の見立てを信じるとすれば、本稿の冒頭で紹介したESG関連の記事数は今年あたりにピークアウトし、来年から減少に向かう可能性が高い。
日本の証券会社と米英の資産運用のプロ、どちらの見方によっても「ESGは消える」。しかし、理由はまったく異なるし、次元が違うことは明らかだろう。流行やブームが去り、ESGが運用の常識になった時に初めて、投資の知見を身につけ、実力を磨いていたかどうかが分かる。「潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたのかが分かる」という賢人投資家ウォーレン・バフェット氏の言葉は、ここでも当てはまる。
ESGをグローバル経済の必然と考えた欧米の証券会社…対する日本の証券会社は?
そもそも、ESGは日本の証券会社が金融商品を売るためにひねり出したキャッチフレーズではない。ブームが続いている間に、この点が案外忘れられているようにも見える。おさらいをしておきたい。