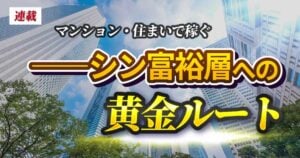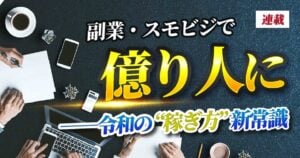倒産連鎖で日本大ピンチ「どんな企業が危険?」0.3%の大企業以外は不況下に…DeepSeekショックで大混乱!海外アクティビストが狙う日本企業8社

本稿で紹介している個別銘柄:ユタカフーズ(2806)、沖縄セルラー(9436)、協和キリン(4151)、タカラバイオ(4974)、トーエネック(1946)、オルガノ(6368)、ユアテック(1934)、蝶理(8014)
2024年、日経平均株価は過去最高値を更新した。その背景として、新NISAブームももちろん大きかったが、株式評論家の木戸次郎氏は「外国人投資家のマネーが史上最高値更新に大きく影響した」という。なぜ今、外国人投資家が日本株に注目しているのか。注目セクター・銘柄と合わせて紹介していただいたーー。みんかぶプレミアム特集「あなた一人だけ『勝つ』方法」第1回。
目次
日銀の追加利上げで17年ぶりに政策金利が0.5%に…0.75%も視野に見えてきた
さて、2025年の幕開けは日銀が半年ぶりにようやく追加利上げし、政策金利が実に17年ぶりの0.5%となったことからのスタートとなった。
振り返ってみると17年前の2006年3月にも日銀は量的緩和政策を一旦解除して、これに続いて7月にはゼロ金利も解除した事があった。資産バブル崩壊後から長らく低迷していた日本株式市場であったが、追い打ちをかけるように2001年の米国同時多発テロ、2003年のイラク戦争不安、更にはりそな銀行の公的資金投入で一時は日経平均が8000円台を下回ったものの、何とか持ち直して17000円台まで回復していた時期だった。あの時、何事もなければ株価はもとより日本経済そのものも回復の一途を辿るきっかけになっただろうと思う。
しかし、それも束の間、2007年のサブプライムローン問題に端を発し2008年の大手証券会社リーマンブラザーズが経営破綻した所謂リーマン・ショックによって世界中の経済が大混乱に巻き込まれ、一気に瓦解していった。この時はあらゆる株価が下落し、金融危機が発生した。無残にもこの影響で日経平均は10月28日に資産バブル崩壊後の最安値となる6994円90銭まで下落し、臍を嚙んだ経験がある。まさにゼロ金利解除のタイミングというのはハプニングの有無に拘わらず難しいのだろうと思う。
現在は2%超のインフレが続く中で日銀は段階的に利上げする構えを表明している。次の利上げで0.75%となれば、1995年以来、日本が30年間経験していない領域も視野に入ることとなる。同時に大多数の投資家にとっては未知の領域となるわけだ。
日本の実質金利はまだまだ諸外国と比べて低い
更に日銀は政策金利を中立金利の水準まで引き上げることを想定。因みに中立金利は1~2.5%程度と幅広いレンジ)で推計されている。日銀内には1%までは利上げを進めたいと意見が多数あるのも事実だ。
何故なら、日本は「実質金利」がまだ低い水準だからだろう。実質金利は名目金利から物価変動の影響を除いた金利水準のことをいうのだが、政策金利を0.5%にしたところで日本の実質金利が未だに-3%程度と極端に低いからであろうと思う。他の先進国と比較しても英国やオーストラリアは2%台で米国、カナダ、スウェーデンも1%台、景気減速懸念がくすぶるドイツでさえ0.5%を保っている状況だ。
つまり、2025年は「失われた30年」と言われる以前の政策金利に引き戻されることになる。長年に渡り、この低金利の環境にどっぷり浸かっていた大企業は「失われた30年」といわれる中で過酷なリストラを重ねながらディフェンシブ型の経営を構築していき、積もり積もった総額600兆円を超える内部留保を産出して、今やそれが矛にも盾にもなっているのである。つまり今の日本経済が「失われた30年」で作り上げた「矛盾」なのであろうと思う。自らの内部留保が潤沢にある大企業にとってみれば今や政策金利が0.5%だろうが0.75%だろうが利子負担など全く意に介していないのが実情だろう。
日本の国家予算の約6倍以上ものお金が市中で循環される事なく大企業の懐で滞留しているのだから、現在のような極端な二極化が進行していても何ら不思議ではない。
24年は11年ぶりに年間の企業倒産件数が1万件を突破した
だから経済指標の字面ばかりが良いのも大企業の数字だけが極端に良いというところが大きく寄与しているのは間違いないであろう。ただ、日本の実態経済を支えているのは企業全体の99.7%を占めている中小企業約336万社なのである。そして中小企業で働く従業員数は3300万人で全従業員数の69.7%に当たるのだ。今や好景気を謳歌しているのは0.3%の大企業とそこで働いている29.3%の大企業従業員だけであり、それ以外の大部分は不況下にあるといっても過言ではない。
現在の不況の深刻さは倒産件数を見てもわかる。なんと、24年の企業倒産件数は、11年ぶりに1万件を突破したというのだ。11年前の2013年は民主党が政権与党で舵取りをしていたが、完全に行き詰まり、長期に渡るデフレと景気低迷で喘いでいた年だった。その後はデフレ脱却のための異次元の金融緩和を織り込んで円安が進み、更にその円安による輸出企業の採算改善を先取りし、2013年初から株高が進んだことで景気回復の原動力となったのだが、今とは逆で円高による企業倒産が主だったわけだ。今や円安による原材料高、燃料高、人件費高騰による倒産が大半だ。
2023年の日本の合計特殊出生率は1.22でまたも過去最低を更新
そして現在、ほとんどの企業での最大の懸案事項は「人材不足」だ。仕事やお金はいくらでもあるのに肝心の人材がいないのだ。皮肉にも大量の首切りをしてコツコツ貯めた内部留保を今度は人材確保で使うことになるのである。
2023年の日本の合計特殊出生率は1.22と低調に推移していて、毎年過去最低を更新している。2024年の人口こそ世界第12位の1億2375万人となっているが、増加率も-0.5%と人口減が続いており、今後も毎年数十万人規模の人口が減少していくと見られている。一方、米国はというと人口3億4542万人に対して0.6%も人口が増加している。無論、米国は多民族国家で移民が多く増えているのは事実だが、確実に人口は増加しているのだ。日本も近い将来、移民を受け入れて人口を増やすということをしない限り、人口も経済成長も減少の一途を辿る可能性が高いといわざるを得ないであろう。
金利が上がれば日本経済も活性化する
さて、これまでを振り返っても金利が上がるくらいのほうが金利コストを吸収できるようにするために経済活動がより活発になり、貨幣流通高は確実に上がる。市中に資金が循環すれば日本経済全体も活気が出てくる。つまりポジティブシンキングになるのだ。
しかし、今までは長きに渡る低金利によってネガティブシンキングで防衛の為のリストラと内部留保確保だけに躍起になっていた側面がある。2025年は30年ぶりに訪れるであろう金利1%時代の到来によって「競争力」を蘇えらせるチャンスなのだ。円安によって完全に失われた国際競争力も同様のことがいえると思う。
ハワイ滞在で目の当たりにした現地日本人、日本人向けサービスの惨状
私事だが、先週は某大手外資証券の仕事でハワイのホノルルに滞在する機会があった。海外に出てみると円安によって如何に日本の国力までが弱くなっているかを痛感させられる。ハワイではイミグレーションでもタクシーでもホテルやレストラン、銀行までもほぼ日本語が普通に通じる完全な日本人優遇社会だ。だから有名芸能人がハワイに別荘を持つのだろうが、そのハワイでさえ、日本人は円安によってかなり肩身の狭い思いをさせられている。飛行機でもCクラスに乗っているのは欧米人や台湾人、東南アジア人がほとんどでほぼ日本人は座っていない。
ハワイには日本人や日系人を対象にしたサービスやビジネスが実に多いが、そのいずれもが大苦戦しているのを目の当たりにして猛烈に悔しく、情けない気持ちにさせられた。いち早く中立金利に戻して、ある程度の円高誘導する政策をとって、日本人がワイキキビーチを闊歩する姿を見てみたいものだ。