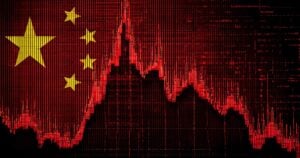年間300社の経営陣と面会した投資家が見つけた「成長余力のある企業」の探し方

日米両市場の投資家として40年活動してきた米国在住のワイズマン廣田綾子氏は、「世界中の投資家を引き付ける優良企業には、必ず行っていることがある」と話す。優良企業の探し方や実際の企業事例について、同氏が語った。
※本稿はワイズマン廣田綾子著「海外投資家はなぜ、日本に投資するのか」(日経プレミアシリーズ)から抜粋、再構成したものです。
第1回:投資キャリア40年・米国在住投資家「日本はいま、世界のバリュー投資家から注目されている」バリュー投資の三つの型
第3回:“米ドル一強”崩壊の足音が聞こえる……「金融の核兵器」を発射した米国、対抗するロシア
目次
埋もれた優良企業を探すのは難しくない
私はバリュー投資を専門としている日本出身の海外投資家という立場で、年間300社の日本企業の経営陣と面会してきました。一口に経営者といってもその能力や経歴、キャラクターは千差万別です。が、彼ら、彼女らと繰り返し膝詰めで意見を交わすうち、成長が期待できる企業の経営者に共通する特徴が分かり、その見極めがだんだんにできるようになってきました。
いざというタイミングを逸することなく経営者が迅速に判断を下し、市場から受ける期待を現実の成長力へと転換していける企業かどうかを見定めるためにはどうしたらよいのか―最終的な投資判断はご自身で行っていただくことを前提として、私が数十年の経験の中で練ってきた分析法の一端を紹介します。
世界中の投資家を引き付ける優良企業が必ず行っていることがあります。それは、「選択と集中」です。
部門で日本勢の影が薄らいでいく一方で、お家芸だったはずの白物家電さえ、低コストが強みの韓国企業、中国企業にみるみるシェアを奪われ、最終的には彼らに事業を売却するというパターンが相次いだのです。
この話には、二つの側面があります。企業として競争力を最大化する経営方針という観点で言えば、たしかにコングロマリット形態は望ましいとは言えません。が、中長期的に収益拡大を狙う投資家の立場からすれば、現在多角経営の罠に陥っている企業は逆説的に、大きな変化の可能性があるということでもあるのです。投資先企業の経営陣が事業の選択と集中を断行して脱コングロマリットを実現できるのであれば、それは本業の稼ぐ力を高め、企業価値を向上させる巨大な余地が残っていることを意味しているからです。
こうした点を押さえておけば、日本の市場で成長余力のある企業を探し出すことはそれほど難しくありません。他の事業部門の中に埋もれてはいても世界的にもシェアが高く、利益率も会社平均より頭一つ抜けている「宝物」の部門を抱えている企業を見つけ出せばよいのです。