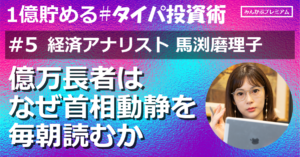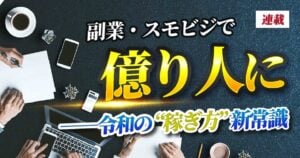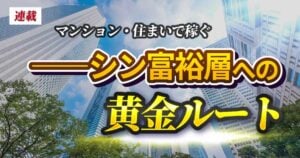見えた!日本経済「大復活」…この夏、日本に巨額マネーが流れ込む

そもそも「円安」は悪なのか
円安が止まりません。2021年1月に1ドル=103円を記録してから下降し続け、4月下旬には、ついに20年ぶりに1ドル=131円台に突入。長くは続かないだろうと予測する専門家もいる一方で、このまま140円台に突入するのではと、する見方もあります。
今さらですが、円安が続くと日本経済はどうなるのか。「円安」とは、「円の価値が安くなること」。仮に日本がこれまで100円で仕入れていた輸入品(石油や食料など)があるとすれば、それが140円出さなくては買えなくなる状態です。
一方、デメリットばかりではなく、メリットもあります。日本は80年代以降、輸出大国としてテレビや自動車、ゲーム機や白物家電など、多くの日本製品を海外に輸出してきました。そうした企業にとって、「円安」は大いなるメリットとなります。
ただ、「円安」が行き過ぎると、デメリット面も無視できなくなります。世界がグローバル化し、サプライチェーンが複雑化するにつれ、日本企業は安価な労働力や部品調達を、海外に求めてきました。最終的な製造は日本で行うにしても、その前段階の調達コストが上昇、または調達不能に陥れば、その負担は企業にブーメランのように跳ね返ってきます。
悪いのはデフレマインドの日本人
しかも、そのコスト上昇分を、商品・サービス価格に転嫁できないジレンマが、デフレマインドの染みついた日本特有の悩みの種としてずっと続いてきました。
一方、庶民生活にとっても、行き過ぎた「円安」は家計を直撃します。日本は食料自給率が低く、エネルギーも他国への依存度が高い。現在、日本の食料自給率はカロリーベースで37%(2020)、エネルギー自給率は12%(2019)です。
日々の食べ物、ガソリンや電気代などは、削りたくても限度があります。しかも「輸入品が高いなら、国内製品で」とできないところが、海外依存度の高い国の悲しいところ。
新型コロナによる経済の鈍化や、ウクライナ危機による穀物やエネルギー価格の高騰、物流混乱による輸送コストの上昇に、慢性的な人手不足、長引くデフレ、そして「円安」……、これが現在の日本経済を直撃している不安要因の数々です。
アメリカと日本のインフレは何が違うのか、どうヤバイのか
なぜ今、「円安」が続いているのか。世界的な金利上昇が大きな要因となっています。
日本が「失われた30年」という名のデフレスパイラルにもがいている間に、いつの間にか世界はインフレ状態にシフトしつつあります。IMF(国際通貨基金)は4月の段階で、2022年の「世界の物価上昇率(インフレ率)」を、前年比7.4%に見通すと発表しました。
実際、22年3月時点で、アメリカは8.5%の物価上昇率を記録しました。日本がひたすら「物価上昇率2%」を目指している中でのこの数字は、アメリカにとっても40年ぶりの高水準だそうです。アメリカ中央銀行にあたるFRB(米連邦準備制度理事会)は、22年ぶりに0.5%の利上げを決定しました。
アメリカは今、一種のバブル状態に近づきつつありあます。経済がふかれすぎて、モノの値段が上がりすぎてしまっている。インフレが過熱すれば、国民の不満はたまります。行き過ぎれば、かつての日本のバブル崩壊や、リーマンショックも繰り返されかねません。
なぜ、こんな状況でも「日本政府は何もしない」のか
その手前で抑え込む方法の一つとして、いわば経済の過熱状態を冷ますために、利上げが行われているのです。
なぜ利上げをすると、インフレが押さえられるのか。個人や企業が資金借り入れをする際、高金利では躊躇せざるを得ません。その結果、需要高騰を防ぐ効果を期待しているのです。
その一方で、金利が高ければ、お金を預ける際は有利です。結果的に、低金利が続く日本円は敬遠されて売られ続け、ドル買いが続いているというわけです。ちなみに、これまでセオリーだった「有事の時の円買い」も、今回のウクライナ危機では実現しませんでした。期待された「円高」は起こらなかったのです。
現状、日本は利上げをしない、あるいはできません。上記に掲げた「インフレ→利上げ」のロジックが日本には当てはまらないからです。
アメリカの物価上昇率が8%を記録したのに対して、日本は2%に満たない状態が続いてきました。ようやくこの4月、日本の物価上昇率が2%の大台に乗る試算が出ましたが、その物価上昇は自然なものというより、エネルギー価格や穀物価格高騰などが背景にあります。ここで一気に金利引き上げをすると、国民生活を直撃し、景気後退を招きかねません。
でも、大丈夫だ! すでに希望は見えている。日本経済は底強い
というわけで、ここまで厳しい日本経済の状況をご説明してきました。でも、実は私は必ずしも将来を悲観的に捉えてはいないんです。むしろ日本にも投資家にも大チャンスが訪れていると思っています。株で言えば今が買いと判断します。それには、これだけ理由があります。
たしかに、ウクライナ危機は今後もしばらく続くでしょう。エネルギーや様々な商品価格の高騰が、目に見える形で企業や家計を圧迫してくるのは夏以降でしょう。
ただ、ウクライナ危機もコロナもいずれは落ち着いていくはずです。エネルギー価格や商品価格も、どこまでもうなぎ上りに上昇していくとは考えにくい。
さらに先にも述べましたが、結局のところ「円安」は企業にとって恩恵も大きい。保守的な日本企業は楽観的な見通しを避ける傾向にありますが、8月に出される第一四半期決算では、「やはり良かった」数字が続出するのではと予想しています。
我慢の限界… 外国人は日本に旅行したくてウズウズしている
もうひとつ、希望的予測もあります。新型コロナが少しずつ落ち着き、日本の〝鎖国″状態が解ける今後、インバウンド熱が戻ってくるだろうという予測です。
岸田首相は6月以降、国境をG7並みに開放すると表明しています。コロナで押さえつけられてきた旅行熱、中でも富裕層の消費熱が解き放たれ、それが一気に日本に流れ込んでくる可能性は極めて高いと思っています。
「ついに旅行ができる!」その時に、彼らはどこに行くか。ヨーロッパはウクライナ危機できな臭く、中国も強烈なロックダウンが記憶に新しい。東南アジアもコロナ禍によるダメージが大きく、安全面などに不安が残ります。
だとすれば日本を選択する外国人は、極めて多いはずです。事実、「コロナ後に旅行したい国」のアンケートをオンラインで実施した結果、ダントツ1位で「日本」が挙げられています。
安全で、治安が良く、しかも「円安」。旅行先としてサイコーではありませんか。むしろ1年後の日本は、「予約が取れない国」になっているというのが、私の予想です。
海外企業は「最高すぎるニッポン」に目をつけている
コロナ禍では、旅行・飲食・サービス業は軒並みダメージを受け続けていましたが、ついにここにも「円安」の追い風が吹くのです。むしろ政府も、そこを目指しているはずです。「円安」を〝てこの原理″として上手に使い、経済再生を目指すというシナリオです。
さらに、日本に進出する海外企業も増えるでしょう。治安や政治情勢が安定しており、円安で工場も建てやすい。しかも、真面目で技術力も高い優秀な日本人を雇えるのです。
もしかしたら、そんな「世界の下請け」国としての日本などごめんだ、と思う日本人もいるでしょう。かつては日本こそが「安い労働力」を求めて、海外に進出していたわけですから、その気持ちも理解できます。でも、そこは妙なプライドは捨て、雇用機会が増えるとポジティブに考えてはいかがでしょう。
もちろん、海外企業の下請けとして、この先もずっと甘んじろというつもりはありません。
日本株に注視を。メイン・イン・ジャパンが再認識される
現状、日本経済がマズいのは、「円安」そのものではなく、「失われた30年」で染みついたデフレマインドが、景気回復の足を引っ張っている事実です。「安いニッポン」に慣れ過ぎて、「モノの価格」が上がることを極端に厭う消費者を前にして、企業も様々なコストを商品価格に転嫁できていません。1997年以降、日本人の平均年収は上がることなく、非正規雇用ばかりが増えていっています。
この負のスパイラルに終止符を打つべきです。
目指すべきは、「モノの価格」が正当に上がり、企業の利益も上がり、給料も上がること。その結果、産業界での投資やイノベーションが進み、モノやサービスの付加価値が上昇し、「メイド・イン・ジャパン」の価値が高まっていくこと。
昨年の21年、日本がベンチャー企業に投資した額は、アメリカのわずか1%でした。これではエッジの立つ優秀な企業が育つわけがありません。このまま下請け国として甘んじて生きていくか、あるいはかつての製造業・自動車産業に代わる新たな産業を国内でしっかり育てていくか。2022年は、マインドリセットの年となりそうです。私たちも短期的な視点だけでなく、中長期的な成長や恩恵を視野に入れて、日本株を注視していきたいですね。