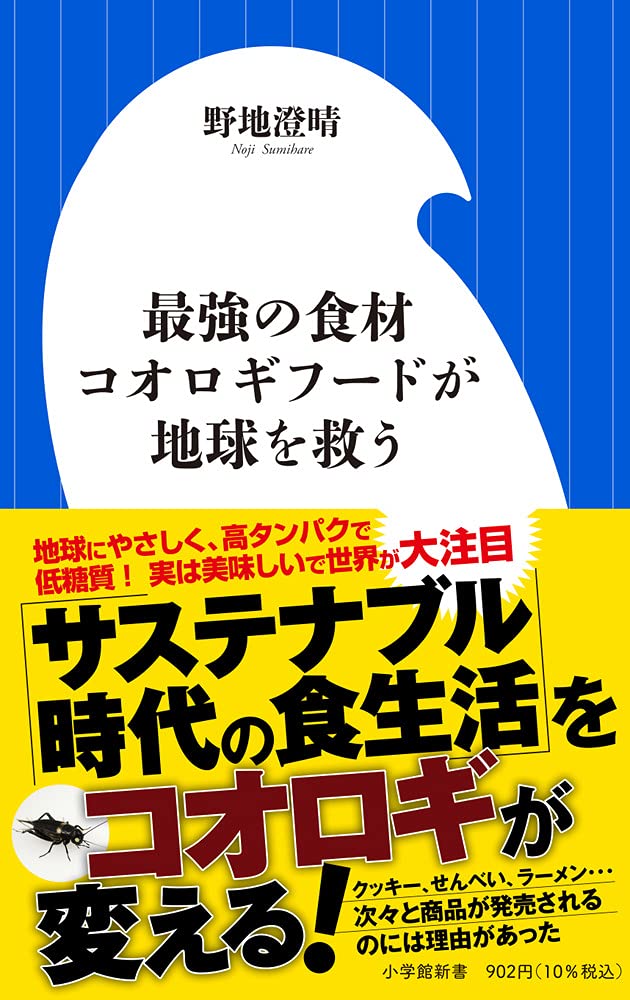なぜ国はコオロギ食を推進するのか…”畜産・水産養殖よりコスト数倍” なのに

元徳島大学学長でコオロギ研究の第一人者である野地澄晴氏は、コオロギの持つ様々な可能性に期待を寄せる。国もコオロギの研究を推進し、2050年までの成果創出を目指す「ムーンショット型研究開発制度」としてコオロギに関するプロジェクトを採択した。食用コオロギを巡っては世論が分かれているが、そもそもコオロギの持つ“可能性”と“課題”を、野地氏の著書を基に考える――。全4回中の4回目。
※本稿は野地澄晴著『最強の食材コオロギフードが地球を救う』(小学館)から抜粋・編集したものです。本著は2021年8月に発売されたものであり、記載内容は当時のものです。
第1回:前・徳島大学長「なぜあなたはコオロギを食べるべきか」…世界を救うのは”やっぱりコオロギ”と語るワケ
第2回:前・徳島大学長「栄養満点スーパーフードなコオロギは1200年前から人に愛されていた」 …だが本当に安全なのか
第3回:前・徳島大学長「コオロギせんべいをBigHITにさせることがわれわれの使命」…エビせんに似て美味
日本発のコオロギシステムを世界へ
徳島大学のコオロギ研究グループは、次世代タンパク源としてフタホシコオロギに着目しているが、今後の課題である飼育コストの削減や付加価値の増加のためには、革新的なコオロギの生産技術と系統育種技術の開発が必要である。この事業のコンセプトは「昆虫食」を超えた「完全循環型タンパク質生産体制構築」である。
フタホシコオロギを用いた循環型の動物性タンパク質を生産することを実現するために、まず、フタホシコオロギの特徴を確認する。
- フタホシコオロギは飼育が容易で成長が早く、雑食であり、かつ、味にクセがないため食用に適する。
- 通年で繁殖・飼育が可能なことも大きな特徴である。
現在の課題は以下である。
- 現在の飼育方法では既存の畜産・水産養殖と比較して数倍のコストがかかるので、コストを削減しなければならない。
- 食品残渣のみでの飼育技術が十分に確立されていない。
- 昆虫食への抵抗感があるために、社会認知度(社会受容性)が低いこと。
飼育コストを削減し、フタホシコオロギの大規模養殖を実現するには、飼育スペースの効率化が必須である。過密な飼育に適応できるコオロギであるが、当然限度がある。限度を超えると共食いや生育環境の悪化が生じる。
現在の単位容積あたりの生産量は、衣装ケース(40×60×30センチ)あたり成虫で1000個体程度である。徳島大学の渡邉崇人助教らは、飼育ケースの仕切りの構造を工夫し、フタホシコオロギの生態を考慮して空間利用効率を適正化することに成功し、単位容積あたり通常飼育の約5倍の高密度生産を可能とした。
さらに、日々のコオロギの飼育維持作業及び収穫時の分別作業に関わる人件費が全体のコストの約8割になるので、自動化を実現することが必要である。
徳島大学発のベンチャーであるグリラスは、生産を担う大手機械・自動車部品製造会社のジェイテクトの技術により給餌や収穫などの飼育作業が自動化されれば、極めて高効率な革新的昆虫大量生産システムが実現できると考える。
その完全自動化システムを、旧小学校の各教室に導入し、大量生産を進めるとともに、システム自体の販売及び運用のコンサルティングも行うことにより、日本及び世界の展開を考えているのだ。
昆虫食の心理的ハードルを下げる…特に重要なのは子ども向け食品だ
フタホシコオロギが雑食性であることは、非常に重要な性質である。徳島大学三戸研究室では、飼料の一部を食料残渣で置き換える研究を行ってきた。例えば、大豆から豆腐を製造する過程で、豆乳を絞った際の残渣は「おから」である。おからを利用して飼育をした。
一方、小麦から小麦粉を作製する工程で出てくる「フスマ」を利用したり、みそ作りの残渣など様々な残渣をコオロギに与え、体重や体重の変化などから成長速度などを解析し、糞などを調べ、その影響を調べている。
当然、様々な残渣の栄養素を栄養学の観点からも解析している。コオロギの成分がヒトなどの免疫機能を上げるなどの報告もあるので、機能性を増強するために必要な栄養素についても研究している。
得られたデータを基礎に、種々の食品残渣の最も良い混合率を人工知能を利用し、より科学的手法も取り入れ、効率的に明らかにする予定である。
次の課題は、昆虫を食べることに対する心理的ハードルの低い試作的な商品を製作することである。特に、子供用の食品が重要である。
ヒトの味覚の嗜好は、6〜8歳までに決定されるらしい。このような現象は、ヒトの他の能力においても知られており、例えば、絶対音感もそのような能力の一つである。絶対音感を持つ人と持たない人の違いは、幼児期の学習の差である。
実際に食の選択を決定する重要な要素は、幼児期の食事に依存するので、コオロギ食も幼児期から食べていただくことが重要である。さらに、栄養素・機能性物質から得られる「うれしさ」を明確にすることも重要である。
より長期的には、メディア戦略も含めて社会認知度の向上を図り、社会浸透を図ることも重要である。また、各ステップと並行して食味改善や機能性向上が見込まれる因子の探索も進めるべきであろう。
コオロギ1対から1年間飼育を継続すると、生育した成虫が約477兆匹となる。グリラスにおいては、ジェイテクトと共同で完全自動飼育装置を開発している。この技術の画期的なところは、コオロギは成虫になるまでに8回脱皮するが、その脱皮した殻を回収できることである。
回収したコオロギの脱皮殻をナノファイバーとして利用できる可能性がある。昆虫の表面は硬い殻で覆われている。その成分は、カニの硬い殻と同じである。それを外骨格と呼ぶが、20〜30%程度のキチンとキチン結合性タンパク質や炭酸カルシウムで構成されている。
中国の武漢大学のフェンファ・タオ博士らは、科学論文「Carbohydrate Polymer、2020」に、キチン・キトサンベースのナノファイバー・スカフォールドが、骨の再生を助けることができることから、骨の再生治療に有効に使用されていることを報告している。
この骨再生治療にフタホシコオロギのキトサンおよびキトサンベースのナノ粒子が利用できる可能性を韓国の漢陽大学のK-Sチェ博士らが、科学論文で報告している。
その論文では、コオロギキトサンのナノ粒子を調製に最適な条件を決め、キトサンの特性を明らかにし、低分子量の昆虫キトサンが機能材料として利用可能であることを証明している。
鳥取大学大学院工学研究科の伊福伸介教授によると、殻の成分であるキチンを、キチンナノファイバーとして単離でき、そのファイバーで補強したプラスチックフィルムを作製すると、透明なフィルムができることが報告されている。
コオロギ由来のナノファイバーは今後、医薬品、化粧品、繊維などの多方面の分野において、様々な用途に利用されると考えられる。
政府も推進、コオロギフード
「地球は青かった」とは、1961年に人類で最初に宇宙に行ったソ連のY・A・ガガーリンの宇宙から地球を見た時の言葉である。当時の宇宙開発競争に負けたアメリカの第35代大統領であるJ・F・ケネディは、「1960年代が終わる前に人間を月に送り、無事に帰還させる」という、無謀とも思われる計画、アポロ計画を発表した。
この計画はムーンショットと呼ばれた。現時点では簡単には実現できない目標だが、実現すれば大きなインパクトとイノベーションを生み出す目標を、ムーンショットと呼んでいる。
「月に人間を送る」目標は、当時では到底不可能であると世間は思った。しかし、それを目標にすることで、発想が変わる。個人も同じである。
シンギュラリティ大学の共同創設者のピーター・ディアマンディスは、「ムーンショット・マインドセット」が重要であるとしたが、日本語にしたら「若者よ、大志を抱け」となるのか。実際、〇〇を実現したいと思わなければ、絶対に〇〇を実現することはできない。ちなみに、徳島大学のムーンショット目標は、「世界の課題を解決して、最も豊かな大学になる」である。
2020年7月、内閣府は「ムーンショット型研究開発制度」を発表した。この制度は、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する新たな制度である。
この制度では、未来社会を展望し、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題などを設定し、研究開発事業を国が支援する。設定された2050年までのムーンショットの目標は7つ。そのうち、昆虫のプロジェクトは目標5の「未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」に関係している。
特に「微生物や昆虫等の生物機能をフル活用し、完全資源循環型の食料生産システムを開発する」ことを目標に、お茶の水大学、早稲田大学、東京農工大学、長浜バイオ大学、徳島大学が連携してプロジェクトを立ち上げることにした。
その結果、2020年9月に「ムーンショット型農林水産研究開発事業」の一つに採択された。利用する昆虫はコオロギとミズアブである。各大学を中心に幅広い研究・教育機関が参画し、英知を結集させ、目前に迫る人口爆発に伴う食料問題の解決や人類の宇宙進出を支える食料開発に挑む。
地球を救うために全世界から研究者を招聘して世界トップクラスのコオロギとミズアブの研究を行い、さらにその成果を社会実装しなければならない。これは、コオロギとミズアブが主役の日本の国家プロジェクトであり、世界を救うプロジェクトでもある。