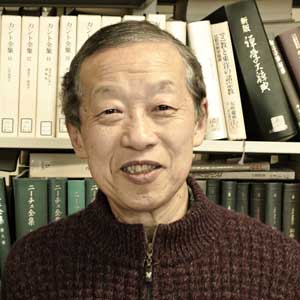新宗教信者が「つい献金したくなる」キラーフレーズ…なぜ金を支払うことが快楽につながるのか

いみじくも統一教会をめぐる一連の報道で浮き彫りになったように、新宗教には信者から多額の金が集まってくる。宗教学者の島田裕巳さんによると、新宗教は信者にお金を出させることに「宗教的な意味合い」を持たせることが多いという。それでもなぜ、信者はときに自らの生活に支障を来してまで宗教にお金を投じてしまうのか。「献金が快楽に至る」までの過程を、島田さんが詳しく解説する。全4回中の3回目。
※本稿は島田裕巳著『新宗教 驚異の集金力』(ビジネス社)を抜粋、編集したものです。
第1回:統一教会「韓国・財閥としての顔」日韓トンネル利権の仕組み…なぜ女性入信者は「統一原理」に惹かれるか
第2回:公称550万部!朝日新聞より売れる「聖教新聞」…創価学会の驚異的な商材ビジネスモデル
「神殿を建立 」で献金を集める
新宗教の教団では、信者が教団に金を出す行為を、たんにメンバーとしての負担として位置づけるのではなく、そこに宗教的な意味づけを与えることによって、より積極的に金を出させるよう仕向けていく。
真如苑では、歓喜を「かんぎ」と読ませ、特別な意味があることを強調しているが、そうした名称が採用されるのも、教団に金を出すことが、信者にとって大いなる喜びを伴うものであるというイメージを与えるためである。
教団によっては、献金を行うことを「修行」として位置づけているようなところもある。霊友会から離脱して誕生した妙智会では、1974年に新本殿を建設するための献金を呼びかけたが、その際に、献金という行為が「欲の根性を取り、先祖や自分がおかした金銭上の罪けがれを許していただくための尊い修行」(教団の機関誌から)であると位置づけた。
しかし、そうした形で献金を世俗的な行為、あるいは信者としての義務にとどまらず、修行にも結びつく宗教的な行為として宣伝したとしても、それだけでは信者は納得して、多額の献金を行うことにはならない。
その際に、もっとも効果的なのが、建築物を建てることを目標として設定する方法である。これまでの事例から考えて、これほど効果的な方法はない。
新宗教の各教団が、競うように巨大な宗教的建築物を建ててきたが、それも、神殿や本部の建物を建てるということが、集金のための目標になりうるからである。
大本では、1992年に、京都の綾部に開教100周年を記念して「長生殿」という神殿を建設した。建設期間は6年で、20世紀最大の木造建築とも言われている。総工費は100億円である。新宗教関連の建物としては決して高額ではないが、建築費はすべて信者の献金によって賄われた。
現在の大本は、中教団の一つであり、年間予算は16億円程度である。普段長生殿などを訪れても、信者の姿を多くは見かけない。その点では、いつも賑わっている真如苑などとは対照的である。しかし、その大本でさえ、100億円を集めるだけの力は保持している。
それほど、教団の中心となる宗教的な建築物を建てるという目標は、信者の献金意欲を強く刺激する。宗教建築物の建立が献金の目標となりうるのは、建築物が完成した暁には、信者たちの努力がどのような形で報われたのか、目に見える形で示されるからである。
神殿や本部が完成すると、そこには全国から信者が集まってくる。彼らは、壮大な神殿や本部の建物を目の当たりにして、感動する。そうした建物は、とても個人の力では建立できない。自分たちが努力し、金を出したからこそ、完成したのであって、そこに組織としての教団の力を感じる。しかも、巨大な宗教的建築物は、教団の力を外に向かってアピールするための格好のシンボルになっている。
「世界の終わりに金はいらない」
宗教的な建築物の建築を目標とはしない、効果的で効率的な金集めの方法がもう一つある。そのやり方とは、世の終わりが近づいているとする、「終末論的な予言」の強調である。
それぞれの宗教には、世の終わりという考え方がある。ユダヤ教やキリスト教、イスラム教では、それぞれの教えの根幹に、世の終わりが近づいているという認識がある。神は、腐敗堕落した人間の世界を終わらせるために、世界全体を崩壊へと導こうとしているというのである。
キリスト教系の新宗教では、終末論的な予言が強調されることが多い。その際に活用されるのが、「ノアの方舟」の物語である。この物語は、旧約聖書の「創世記」に出てくるが、そこでは、どの民族にもある「大洪水神話」が語られていて、ノアの方舟に乗ることで大洪水を乗り切れるとされている。
キリスト教系の新宗教は、自分たちの教団をこのノアの方舟にたとえる。彼らは、現実の世界は腐敗堕落し、それに怒った神は、遠からずこの世界を崩壊させるであろうと主張する。そして、世の終わりを生き延びたいと考えるなら、一刻も早く自分たちの教団という方舟に集まり、その船に乗って入信するしかないことを強調する。彼らは、世の終わりの接近とそこでの救済の可能性を説くことで、信者を教団に結集させるのである。
終末論的な予言は、新しい信者を集めるためにではなく、金集めの手段としても用いられる。この世界に終わりがもたらされれば、世俗的なものにはいっさい価値がなくなる。つまり、世俗の世界ではもっとも価値があると見なされている金は、まったく無価値なものになってしまうのだ。無価値なものに執着しても仕方がない。キリスト教系の新宗教は、そう説くことで、遠からず価値を失う金を教団にすべて出すよう促すのである。
世の終わりという期限の設定は、絶大な効果をもたらす。それは、新宗教が採用する金集めの手段のなかでも、もっとも有効な手立てである。宗教的な建築物を建てること以上に効果的である。
だがそれは最終手段でもある。これ以上に教団に緊張感を生み、信者に切迫感を生む手段はほかに存在しない。そこには人の命、さらには人類全体の運命がかかっている。これまでも、さまざまな教団がこの方法を使い、世の終わりが近づいていることを強調することで、信者を集め、金集めをしてきた。
しかし、当然のことだが、世の終わりは訪れない。これまで、終末論的な予言が当たったことはない。当たっていれば、いま、この世界は存在しないはずだ。終末論的な予言を掲げれば、必ずや「予言が外れたとき」を経験しなければならない。
予言が外れるという事態に直面した教団は、重大な危機に直面する。信者たちのあいだには失望感が広がり、下手をすれば、教団や教祖は自分たちを騙(だま)していたのではないかという疑いを抱くようになる。教団が外に向かっても世の終わりを説いていれば、教団や信者は社会的な信用を失うことになる。
献金が快楽に
ではなぜ、信者たちは、それほどの熱意をもって、教団に金を出すのだろうか。そこには、人間と金との複雑な関係が示されている。現代の社会においては、ほとんどの商品やサービスは、金を通して購入され、金は生活上不可欠なものになっている。金がなければ生活は成り立たない。それは否定しようのない事実である。
ところがである。金が生活上欠かせないものになっているからこそ、かえって金は世俗にまみれたものとして、高い価値を与えられない。金儲けに走ることは、欲望丸出しの生活を送ることであり、とくに宗教が価値をおく精神性とは対極にあるものと考えられている。
強い信仰をもち、世俗から離れた生活を送ろうとする宗教人には、金儲けはふさわしいことではないし、金自体、所有していることがはばかられる性質のものである。新宗教の側は、金にとらわれることを「執着」や「我執」、「我欲」としてとらえ、それから解放されることに価値をおく。献金に対する宗教的な意味づけも、そうしたところから発している。
かつては天理教が、教祖の生涯をモデルに、「貧に落ちきれ」をキャッチフレーズにして、信者に対して際限のない献金を促し、社会問題を引き起こした。それは、天理教に限らず、新宗教全般に共通する。強い信仰をもつためには、金を手放して、無欲になる必要があると説き、信者にそれを実践させるのである。
自分のために金を使うことは、欲望の充足であり、新宗教の教団では低い価値しか与えられない。高く評価されるのは、献金し、金を手放す行為である。これによって、同じ金の価値が変わる。欲望の象徴であった金も、献金という形をとることで、宗教的な意味をもつ尊いものとして高く評価されるのである。
欲望の象徴である金と、宗教的な意味を与えられた金とは、本来同じものであり、その価値は変わらないはずである。ところが、そこに信仰が介在することで、同じ金が別の意味をもつようになる。その点で、新宗教による金の宗教的な意味づけは、「マネーロンダリング(資金洗浄)」と似ている。献金という行為は、世俗にまみれた金を浄化するものとして意味づけられるのである。
金が浄化されたとき、献金した人間は、そこにすがすがしさを感じる。金だけではなく、自分までが清められたように感じる。そのため、金を手放すことで、欲望から自由になったような解放感を得ることができる。
こうした感覚が得られるために、際限のない献金が行われる。献金する側は、献金という行為自体に快楽を感じてしまう。自分があたかも執着から解放されたかのように感じて、さらに献金をしたいと望む。そのくり返しによって、常識では考えられない額の献金が行われる。