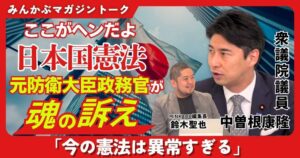今度は「公選法違反疑惑」浮上!斎藤知事の苦難 「大混乱まだまだ続く」…企業広報と民主主義への攻撃『考えてる人、嘘つき、情報操作人、スパイ』

兵庫県知事選では下馬評を覆す逆転勝利をおさめた斎藤元彦知事。しかし、またもピンチに陥っている。PR会社がmerchuの代表が選挙戦略を大暴露し物議を醸している。公選法違反を指摘する声もあがっており、窮地に立たされている。斎藤知事の支持者からはXなどで「斎藤さんの足を引っ張りやがって何を考えてんねや」「兵庫県民を舐めてるでしょ」という辛辣な批判があがっている。一方で激しいバッシングに代表の身を心配する声も出ている。一体なぜこんなことが起きたのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説するーー。
目次
この才能を放っておくことはない
兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事に持ち上がった「公職選挙法違反疑惑」がいまだ波紋を広げている。これまでの経緯を簡単に振り返ると、問題の発端は、PR会社「merchu」代表の折田楓氏が「note」に投稿した記事である。その内容には、斎藤氏が知事選での広報戦略全般を同社に“仕事として”依頼したかのように受け取れる表現が含まれていた。しかし、記事が注目を集めると折田氏は記事の一部を修正し、自身のFacebook投稿もすべて削除した。これに対し、斎藤氏側は「PR会社との関係はボランティアとしての認識だった」と釈明した。
様々な意見が飛び交っているが、私は折田氏が非常に優れたPRを行っていたのだと考える。もしnoteに書かれていた内容が事実であるならば、折田氏によるキャッチフレーズは、有権者にとってポジティブに作用したに違いない。
兵庫県知事選挙にこうしたPRがどの程度影響したのかは明らかではないが、政治家として、この才能を放っておくことはないだろう。別の名目で報酬を渡し、仕事を依頼する人物が現れるかもしれない。選挙での金銭授受が複雑な公職選挙法に抵触する可能性があるだけでなく、裏金の利用や懇意の企業を通じた支援を受けている政治家は少なくないのではないか。
私の知る範囲ではあるが、例えば、自民党総裁選では、小泉進次郎氏や茂木敏充氏がPR会社を起用し、TikTokなどを活用した選挙戦を展開していた。また、自民党総裁選全体の運営は、電通が「二桁億円」(官邸筋)という金額でプロデュースしていたという。
小泉進次郎氏について、選挙プランナーの藤川晋之助氏が、PR会社をこうほめている。
政治家のPR会社の利用は当たり前の時代に
<「他の陣営と比べて、進次郎陣営のPR部隊は段違いです。出馬会見を見ても、スマートかつ効果的に陣容を配置していることが見て取れます。会見で踏み込んだ発言をする際の打ち出し方がうまかったのは、PR会社がアドバイスをしているからでしょう」>(デイリー新潮、9月11日)
政治家としてPR会社を利用するのは、当たり前の時代になりつつあるのかもしれない。しかし、PR会社を用いなかったと思われる石破茂氏が勝利した事実からも、その限界があることがわかる。
華やかな職種に見えるPR会社は、候補者の魅力を引き出すとされる一方、有権者にとってネガティブな側面を覆い隠す危険性もある。PR会社が「夢を売っている」のか、それとも「現実から遠ざけている」のか、このような観点からPR会社を分析した論文が存在する。それが、2007年に発表された「Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on Democracy」(『考えてる人、嘘つき、情報操作人、スパイ:企業広報と民主主義への攻撃』)である。
ニュースが正確で公正であるべきという基本的な考え方を壊してしまう危険
この論文では、ニュースコンテンツの約80%がPRに起源を持つと推計され、以下のようにメディア操作の広がりが指摘されている(<>内は筆者による論文第1章の要約)。
<企業は多様な手法を駆使してニュースを植え付けたり削除したりし、メディア消費者に巧妙な形で影響を及ぼしている。企業は、忙しい記者や資金不足の編集部の弱みを利用し、自分たちに有利なニュースを作り出している。たとえば、企業が記者に送った情報をそのまま記事として広めさせたり、自分たちの利益になる話題を強調させることがある。このような手法は、企業の利益を守るためであり、真実や公益に役立つ情報を隠してしまうことにつながる。こうしたメディア操作は、ニュースが正確で公正であるべきという基本的な考え方を壊してしまう危険がある>
これは民間企業がPRを利用した場合を述べたものだが、政治家がPRを利用する場合、さらに厄介な事態を引き起こすことになると私は推測する。
「フロントグループ」(見せかけの市民団体や公的な審議会)を設立し、負担増や環境保護、社会正義を掲げる団体や会議体を形成することで、オフィシャルな雰囲気を装い、政治や行政の政策を支持しているかのように見せかける手法がある。
社会的に弱い立場の人々の個別のストーリーを強調
このような手法は、政策への批判を回避しつつ支持を広げることを可能にする。こうした団体の活動は表向きには中立的に見えるが、実際には政治家や行政の利益に従属している可能性がある。
さらに、環境問題や社会格差、国民負担に関するデータを誇張したり、対立する研究に疑問を投げかけることで、政策の正当性を国民に信じ込ませる方法も考えられる。このような情報操作により、政策が実際以上に効果的であるとの印象を与えることが可能になる。また、社会的に弱い立場の人々の個別のストーリーを強調することで、政策の急務性を感情的に訴える一方、問題の全体像や複雑な背景を覆い隠し、共感を基にした支持を得ることができる。
特に厄介なのは、マスコミを利用した情報操作である。友好的なメディアを通じて政策を積極的に報じさせたり、対立意見や批判を意図的に隠すことで、政策の効果や支持基盤を実態以上に見せかけることができる。
「支持者と政治リーダーの一体化」ともいうべき状況
こうした問題を浮き彫りにする一例として、梶原麻衣子氏の著書『「“右翼”雑誌」の舞台裏』(星海社新書)がある。この本には、梶原氏が所属していた月刊WiLLや月刊Hanada、さらには安倍政権の内幕が赤裸々に記されている。そして、今回の記事の文脈で注目したいのは、以下の部分である。
<第一次安倍政権退陣時の悲劇もあり、朝日新聞をはじめとするメディアからの総攻撃もあり、安倍氏は「支持者である自分たちが支えなければならない人物」となった。ある面で「弱者」であることが、「私たちが支えなければ」という心情を強くさせ、他ではなかなかお目にかかれない「支持者と政治リーダーの一体化」ともいうべき状況を作り出した。第一次政権時に朝日新聞をはじめとする左派メディアに引きずり降ろされた「悲劇の宰相」というナラティブが、より一層、支持層の胸を熱くさせたのである>
<政策についても同様で、右のイメージで支持者を引き付けつつ、実際には柔軟な選択を行っていた。しかし保守派は時にブレたと批判されてもおかしくない柔軟さは批判せず、左派は歓迎すべきリベラル的と言ってもいい政策を評価することはなかった。このイメージと実態の乖離が、支持者であれ批判者であれ、安倍政権の本質をつかみづらくした原因であろう>
PRによる情報操作は民主主義を脅かす危険性をはらんでいる
この引用からも、政治というものがいかに曖昧な評価の上に成り立っているかがわかるだろう。民間企業のように数値で評価されるわけではなく、経済成長が停滞しようと貧困率が悪化しようと、政治家の評価とは直接関係がない。このような状況では、PR会社やコマーシャルを使って印象操作をしようとするのも致し方ないといえる。
政治家がPR会社を利用するのを止めることは現実的に困難である。PRは企業だけでなく政治家にも利用され、世論を巧みに操作する強力な手段となっている。たとえば、フロントグループを活用し、中立性を装った支持を集めたり、科学的事実を都合よく利用して政策の正当性を主張する手法は政治の場面でも広く応用されている。こうしたPRの利用により、政治家は自らの政策を正当化し、批判をかわすことが可能となるが、それが国民の利益に適っているかは別問題である。
このような状況において重要なのは、私たち市民が政治家の発言や政策提案を批判的に考える力を養うことである。「その政策に本当に実績があるのか」「増税の主張は必要性に基づくものか、それとも単なる言い訳か」といった疑問を持ち、情報の真偽を確認する姿勢が求められる。PRによる印象操作に惑わされないためには、表面的な言葉に流されず、その背後にある事実や意図を見抜く必要がある。
PRによる情報操作は、民主主義を脅かす危険性をはらんでいる。これに対抗するためには、市民一人ひとりが発信内容を精査し、政治家に透明性や説明責任を求めることで、健全な民主主義の維持に寄与することができる。