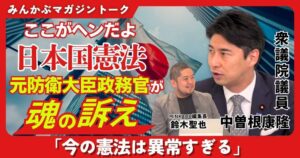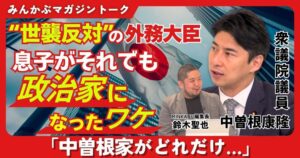斎藤元彦知事が恐ろしいことを起こしてる…「報道特集」テレビ屋・村瀬キャスターの偏見に唖然!国際NGOは日本のネット環境より記者クラブを問題視

11月17日投開票の兵庫県知事選で、パワハラ疑惑などをめぐり知事不信任決議を議決された斎藤元彦氏が返り咲きを果たした。序盤の劣勢を挽回した斎藤氏には「SNSの拡散で追い風が吹いた」「新聞・テレビというオールドメディアの報道に有権者が嫌気をさした」といった分析がなされている。そんな中で、11月30日に放送された「報道特集」が物議を醸している。司会の村瀬健介キャスターは、知事の疑惑を告発した後に亡くなった元県民局長に対する公益通報者保護について、斎藤知事から「人ごとのような回答しかありませんでした」と強く批判。「本当に恐ろしいことが起きている」とも述べた。しかしこの報道は本当にフェアなのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が改めて解説するーー。
目次
司会の村瀬健介キャスターや解説員による勝手な思い入れ
テレビがオールドメディアだと批判は、単純にテレビの歴史が古いということだけでなく、一部の番組作りが化石のような思考回路でつくっているからではないのだろうか。兵庫県知事選で再選された斎藤元彦知事をめぐり、11月30日放送のTBS系「報道特集」では、知事の選挙戦の内幕や疑惑について改めて追及し、この内容が物議を醸している。ニュース特集を通じて、司会の村瀬健介キャスターや解説員による勝手な思い入れの強い内容が展開されていた。
それらの問題があると思われる言葉を拾っていくと、以下だ。
<(立花孝志氏が立候補し、YouTube上で「告発文書は名誉毀損」「斎藤氏ははめられた」などと自身の考えを繰り返した)その中で「情報を隠蔽した百条委員会とオールドメディア」対「真実を伝えるネット」という対立構造がにわかにつくられ、うねりになっていった>
<公益通報者保護という観点からは本当に恐ろしいことが起きているんです。公益通報をした人が亡くなるという痛ましい事態に発展した上にですね、亡くなった後も選挙の中で、そして今もですね、その方のプライベートな情報とされるものが流布されています。知事としてどのように対応するか、考えがあるのかと直接聞きましたけれども。VTRにあったように、他人事のような回答しかありませんでした。これは、知事本人に対する批判が書かれた文章がまかれたときに、すぐに知事の権限を使って犯人探しをして、会見で嘘八百だとか、公務員失格などと激しく反応したこととあまりにも違う対応ではないかと思うんですね>