「万博関連予算」を黒字化するのために必要な入場者数は1日何人なのか…経済誌元編集長「経済効果という幻影が、現実を覆い隠す」
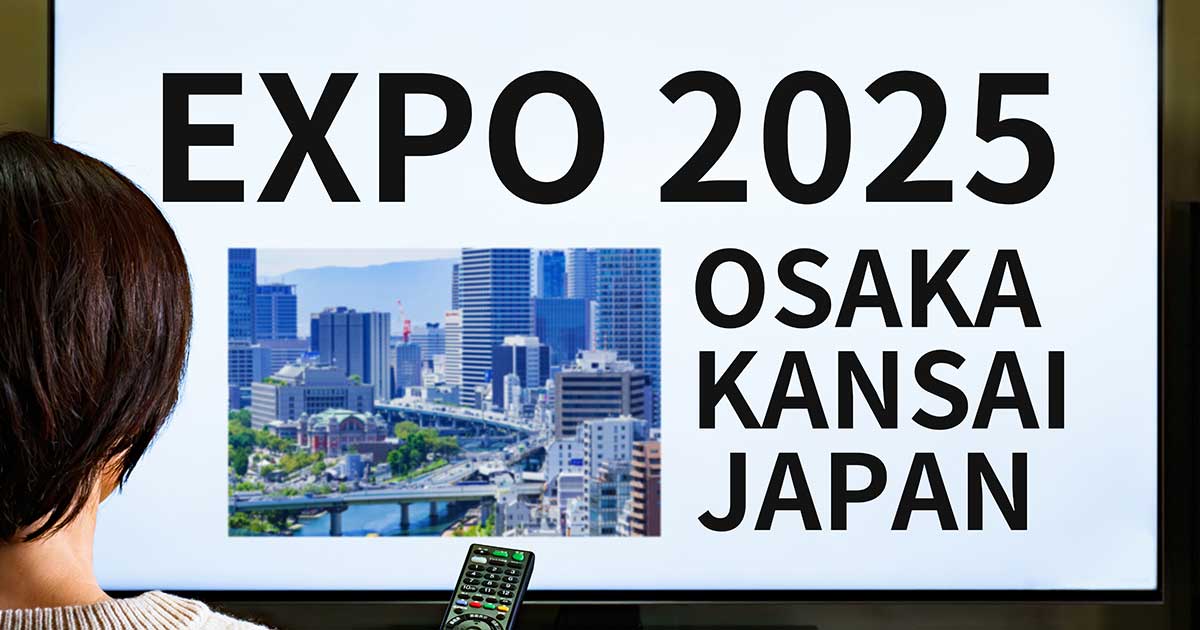
大阪・関西万博が開幕11日目で入場者100万人を超えた。ちなみにこれはスタッフも含めた数であるが、いずれにしても想定している入場者数の一日平均15万人には届いていない。後半にかけて入場者は伸びるというが、入場ゲートで並ぶことや、輸送力不足などさまざまな問題が指摘されている。今後どうなっていくのだろうか。
目次
「万博目的」として予算化を求めたにもかかわらず…
大阪・関西万博に向けては、耳障りの良いフレーズが絶え間なく流されている。「未来社会の実験場」「いのち輝く未来社会のデザイン」「ポストコロナの起爆剤」「世界の課題解決の処方箋」――これらのキャッチコピーは、あたかも万博が沈滞する経済を救済し、日本を新時代へと導く特効薬であるかのような幻想を振りまいている。企業は成長機会の到来に期待を膨らませ、メディアは視覚的に映えるパビリオンや先端技術の断片をセンセーショナルに取り上げる。だが、その喧騒の裏で、現実を直視する冷静さが求められている。表向きの華やかさの背後に横たわる構造は、かつての大型事業が陥った過ちと酷似しており、いまも地方に残るインフラ整備の負の遺産を想起させる。
2021年7月に、大阪府・大阪市・関西広域連合・関西の主要経済団体が連名で国へ提出した「万博関連事業に関する要望書」は、この構図を物語る決定的な資料である。吉村洋文(当時大阪府知事)氏と松井一郎(当時大阪市長)氏が名を連ねたこの文書は、万博擁護派が現在主張している「関連事業と万博は無関係」という逃げ口上を根底から否定するものである。実際、近年「万博費用13兆円」という数字が批判の的となるや否や、維新関係者や一部報道機関は「四国の道路整備まで含めるのは不当」「会場建設費とは別物」などと説明し始めた。しかし、この要望書を読めば明らかなように、それらの事業は最初から万博の名の下に国費支出を求めた対象である。
吉村・松井両氏は、会場周辺の整備にとどまらず、関西一円、さらに中国・四国地方にまたがる道路、鉄道、港湾、河川など膨大なインフラ事業を「万博の一環」として位置づけ、その実施と財源を政府に強く要望していた。「健活10ダンス」なる施策についても、大阪府庁の担当者が私の取材に対し「万博関連予算からの支出である」と明言している。自らの手で「万博目的」として予算化を求めたにもかかわらず、非難が集まると「万博とは別」と主張を反転させる姿勢は、明らかに無責任であり、関連予算の設計が初期段階から恣意的に膨らまされてきた証左である。










