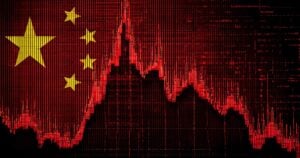大量失業の未来…竹中平蔵・監「雀の涙ほどの賃金しかもらえぬ人が劇的に増加する」稼ぐ能力の二極化
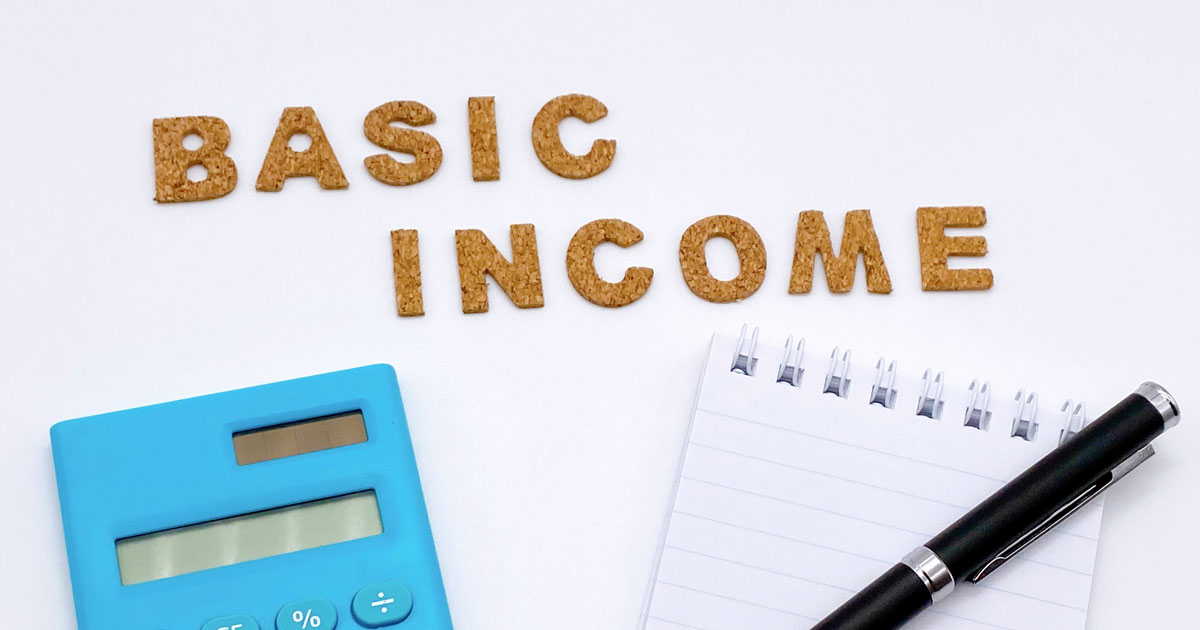
政府が国民一人ひとりに無条件でお金を支給する「ベーシック・インカム」。日本でも新型コロナウイルスの影響で生活困窮者が増えたこともあり、にわかに注目が集まっている制度だ。ベルギーの政治経済学者フィリップ・ヴァン・パリースは、「ベーシック・インカムは、自由な社会の大黒柱だ」と断言する。ベーシック・インカムがなぜ必要なのか、いま改めて考える――。全4回中の1回目。
※本稿は フィリップ・ヴァン・パリース、ヤニック・ヴァンデルポルト著、竹中平蔵監訳『ベーシック・インカム〜自由な社会と健全な経済のためのラディカルな提案〜』(クロスメディア・パブリッシング)から抜粋、編集したものです。
第2回:竹中平蔵・監「 生活保護とベーシック・インカムは何が違うのか」…嫌な仕事にNOと言える優しい世界
第3回:竹中平蔵・監「どうやったらベーシック・インカムの財源を確保できるのか」少額なら”全住民が貨幣を引き出せる”
第4回:竹中平蔵・監「人間としての自由を得るために…」ベーシック・インカムを実現させる3つの戦略
「多くの人が死ぬ可能性がある」 未来
私たちは、多くの力によって作り変えられた、新たな世界に生きている。このような状況では、何よりも、私たちの社会と世界における経済的な安定を追求する方法を、根本から立て直すための措置が必要だ。今日および未来のいずれの社会でも、人が個人として、そして共同体としてしっかり立っていられるような土台が求められる。
不安を食い止め、希望を強めようとするなら、一般にベーシック・インカムと呼ばれているものを、思い切って導入するべきだ。すなわち、社会の個々の構成員全員に対して、ほかの収入源からの収入とは関係なしに、付帯条件もつけず、定期的な所得を現金で支払うのである。
ベーシック・インカムへの賛意を公に表明する人の数が記録的に増えているなかで、よく引き合いに出されるのは、オートメーションの新たな波がすでに押し寄せてきており、これからさらにそのうねりが大きくなっていくという予想だ。
ロボット化が進み、自動運転の乗り物が開発され、人間の頭脳労働の多くがコンピューターにとって代わられる。新しい技術を設計する人、操作する人、そしてそれを最も活用しやすい地位にいる人といった、一部の層の富や収益力は、これまでにないほどの高みに達する一方で、それよりも多くの人が急激に貧しくなるだろう。
稼ぐ能力のこのような二極化は、制度的な背景によってさまざまな形をとって現れてくるだろう。最低賃金法、団体交渉、豊富な失業保険によって給与水準がしっかりと保たれていて、今後もそうであり続ける場所には、大量の失業が起こるという結果になることが多いだろう。
そうした給与水準の保護がすでに弱いか、これから弱くなる場所では、雀の涙ほどの賃金しかもらえない不安定な仕事をして、必死にお金をかき集める人の数が劇的に増加するという結果になるだろう。
過去には、成長が続けば失業や雇用の不安定は抑え込めるのだという合意が、右派と左派の間に存在した。今日、世界の豊かな国々で、これまでにないほどの規模でベーシック・インカムが注目されているという状況は、この合意がもう消えてしまっている証左である。
アメリカ国家安全保障局(NSA)の内部告発者エドワード・スノーデンでさえも、この答えに行き着いている。2014年の『ネーション』誌上でスノーデンはこう語っている。
「科学技術者として時代の流れを見ているが、オートメーションがますます職を奪うことになるのは避けられないだろうと思う。職がない人や、有意義な職に就けない人にベーシック・インカムを支給する制度を整えなければ、社会不安が起こり、人が死ぬ可能性がある」
生活保護は “奴隷状態” を生む
有意義な職が減っていくという予測のもとでは、増えていく失業者に対して何らかの生計の手段が提供されなければならないという確信に容易に至る。この確信を具現化するには、まったく別種の2つの方法がある。
ただし、その1つはとても魅力に乏しい。16世紀に起源を持ち、今では条件つきの最低所得保障制度という形で実例が存在する、古き公的扶助のモデルを拡充するという方法だ。
このような制度は概して、貧困世帯が仕事によって直接的ないしは間接的に得ている所得(あるならば)を補い、社会的に定義された何らかの最低水準まで届くように補完する。それが広範囲をカバーするものであろうと、困窮する人々の一部の層しかカバーしないものであろうと、このような制度は極度の貧困の除去には大いに貢献する。
ところが、条件制限ゆえにこの制度は、受益者を永久に福祉手当を受給し続ける1つの階級にしてしまうという傾向を内在的に抱えている。貧困状態が続き、それが自発的ではないと証明できるという条件のもとで、継続的に補助金を受け取る資格が与えられる。そして受給者は大なり小なり、生活に干渉されるような屈辱的な手続きを強いられる。
さらに、公式の制度ではない、人と人との結びつきによって支えられている「安定の基盤」が弱くなり続けるにつれ、不安定な状況に置かれる人々の数はますます膨れ上がるだろう。
家族がばらばらになる割合はこれまでにないほど増加しているし、核家族の規模はますます小さくなっている。また、労働者の流動性が高まることによって、近親者同士が離れ離れに散らばり、地域共同体の結びつきが弱まっている。
したがって、来るべき有意義な職の減少に対処する方法が条件つきの最低所得保障制度のみであった場合、私たちを自由にしてくれるはずだった技術の進歩は、ますます多くの人を奴隷状態にしてしまうだろう。
生活の基盤となるベーシック・インカム
では、ほかに方法があるのだろうか?万人の自由を実現することに専心している人々にとっても、今日の未曾有の課題に対処し空前の機会を活用する適切な方法として、最低所得制度が欠かせないのは確かだ。だが、それは無条件であるべきなのである。
ただし決定的に重要なのは、無条件の最低所得制度の「無条件」という形容詞は、厳密に解釈されなければならないということだ。すでに存在する制度も、若干の緩い意味において「無条件」と呼ばれる場合がある。
社会保険よりも公的扶助という形をとるそれらの制度は、給付を受ける資格を得られるだけの社会保険料を支払った人に限定されないし、通常、制度を運用する国の国民に限定されず、ほかの国籍を持っていても合法的に滞在している人は受給の対象となる。そして多くの場合、現物給付よりも現金給付が行われる。

しかし、ベーシック・インカムとは、これよりもさらに厳密な意味において無条件なのだ。世帯の状況とは関係なく、完全に個人として受給資格が与えられる。
また、それは一般に普遍的と呼ばれ、すなわち収入や資力の調査を必要としない。そして、それは対価として労働をしたり、就労の意思を証明したりする必要のない、義務を課さない制度である。
ベーシック・インカムの給付額は定義上、均一でなければならないかというと、必ずしもそうではない。第一に、年齢で差をつけうる。ベーシック・インカムとは生まれたときから受給資格が発生すると考えられている。その場合、すべての案においてではないにしても普通、未成年者への給付額は低く設定される。
第二に、場所によって差をつけてもよい。一般には、ある国の内部でのベーシック・インカムは均一であるとされ、目に見える生活費の違い(特に家賃の違い)は考慮されない。これによって「周縁」にいる人々に対する再分配の機能がしっかりと働くのである。
しかし、特に国境を越えた規模で運用する場合、生活費の差を考慮に入れて給付額を調整してもよい。この場合、貧しい地域に対する再分配の効果は、なくなりはしないが減ることにはなるだろう。
第三に、同一空間内では変わらないとしても、時間によって変化する場合もありうる。ベーシック・インカムが意図された役割を果たすためには、1回限りや予測不可能な頻度ではなく、確実に定期的に給付される必要がある。
ベーシック・インカムは、定期的に給付されなければならないだけではない。その給付額が安定していなければならず、とりわけ、突然の景気悪化の影響を受けてはならないのだ。しかしこれは、給付額が固定されていなければならないという意味ではない。
ひとたび実施されるとなれば、物価指数に合わせて変動してもよいし、1人あたりのGDPと連動させればより効果的だ。
最後に問題になるのが、ベーシック・インカムは抵当として利用できるのか、そして課税対象になるのか、ということだ。ベーシック・インカムを抵当設定できないようにする、すなわち、ベーシック・インカム受給者が将来の給付の見込みを融資を受けるための保証にできないようにするというルールを定めるのが、一番道理に適っている。
他方で、ベーシック・インカムを所得税の課税対象としないことが最良かどうかは断言できない。税制によっては、この点が重要になるからだ。
たとえば、個人所得税の課税単位が世帯であり、世帯全体の収入の合計に対して累進課税される場合、課税基準にベーシック・インカムを含めれば、人数の多い世帯ほどベーシック・インカムの額が実質的に減ってしまう。
反対に、個人所得税の税率が固定されているか、厳密に個人単位で課税される場合、ベーシック・インカムを所得税の課税対象にすれば、一定量の給付額が減るのに等しい。こうなると、給付額をあらかじめ低く設定して非課税にするほうが、行政管理上、より合理的だ。