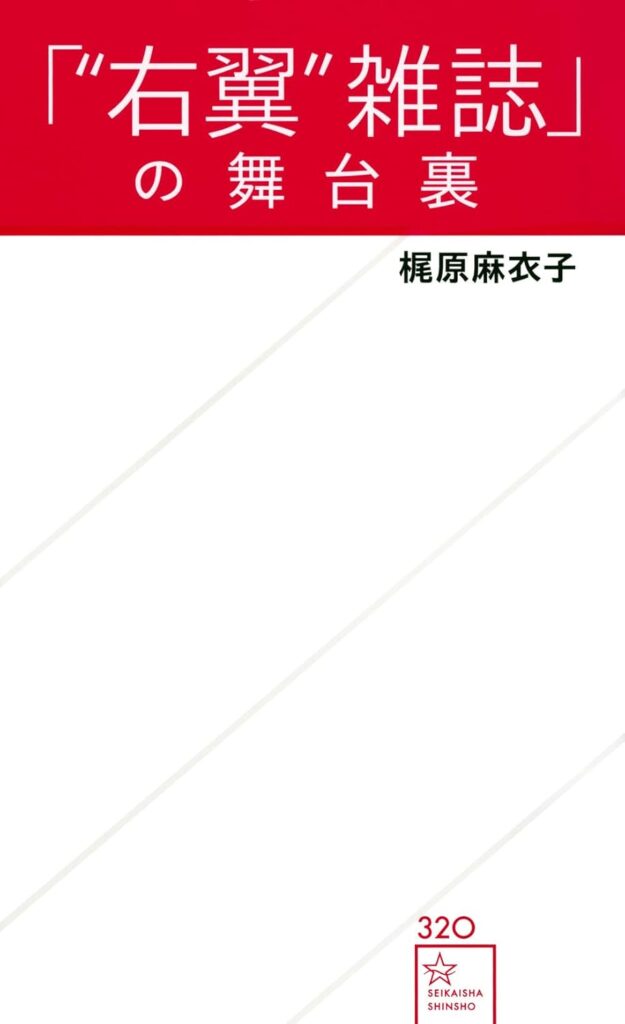元編集者が内幕を暴露…“右翼雑誌”『WiLL』『Hanada』の爆売れの理由は「朝日新聞叩き」だった!一時13万部の大人気

“右翼雑誌”と呼ばれることもある、『WiLL』と『Hanada』。休刊が相次ぐ雑誌業界の中で、『WiLL』は一時13万6000部(公称)を達成。いかに『WiLL』『Hanada』が部数を伸ばしていったのか。そこには週刊誌づくりで養った大メディアへのカウンター意識と、月刊誌にあるまじきスピード感にあったという。その裏側を編集部内でつぶさに見てきたライター、梶原麻衣子氏がつまびらかにした。
※本記事は梶原麻衣子著「“右翼”雑誌」の舞台裏」(星海社新書)から抜粋、再構成したものです。
第2回:自分たちを社会は理解してくれない…“右翼雑誌”『Hanada』『WiLL』元編集者が語る「社会・国家間の溝が深まったワケ」傷ついた、だからやり返す
第3回:花田紀凱が語る「ヘイト批判への反論」爆売れ保守系雑誌『WiLL』『Hanada』生みの親…WiLLとHanadaの違い
目次
「朝日叩きの急先鋒」が朝日へ入社する時代
ジャーナリズムと保守派の接点として『WiLL』『Hanada』のメインとなり、最も得意としてきたのは、文春以来の「反朝日新聞的姿勢」だ。
『WiLL』は、発売直後は部数が振るわず、「3号雑誌(3号で休刊になる雑誌)」とささやかれたこともある。それが大ブレイクしたのが、4号目(2005年4月号)の朝日新聞批判特集だった。当時筆者は読者の立場だったが、鮮烈な印象を受けたのを覚えている。
すでに『諸君!』や『正論』で再三にわたり朝日新聞の批判は展開されていたが、やはりこれらとはどこか違う、企画の立て方、タイトルのセンス、読みやすさなど様々な点で新鮮さが感じられるものだった。『諸君!』『正論』にも老舗の良さはあったのだが、後発の『WiLL』は筆者にとってまさに「自分の雑誌」だった。
朝日特集でブレイクし、その後も朝日批判が大きなテーマの一つとなる『WiLL』だが、創刊前の花田編集長は一時とはいえ朝日新聞社に在籍したこともある。これまた「無節操」と評されそうだが、ここが雑誌人の面白いところでもある。当時、朝日社内からは「なぜあんなに朝日を叩いてきた人を入社させるのか」との声もあったそうだが、その意味では移籍した花田編集長も、受け入れた側の朝日新聞も、なかなか融通無碍で面白い時代だったのだろう。
右も左も包摂する土壌があった
それは雑誌の誌面にも反映されていた。2015年3月号の〈わが体験的メディア論〉には、『WiLL』の天敵・朝日新聞出身の轡田隆史氏がコラムを寄せている。あるいは『WiLL』の連載陣にも、右でないだけでなくリベラル、左翼としか言いようがない執筆者が名を連ねていた。
その最も象徴的な存在が、元『噂の真相』編集長の岡留安則氏だろう。学生運動の闘士だった岡留氏は、創刊号から3年にわたって、『WiLL』に連載していたのである。どこからどう見ても特集の傾向とは相容れない思想の持ち主だが、花田編集長との個人的な付き合いから掲載されていた。
この連載に対して読者から「なぜこんな連載が掲載されているのか」との指摘が来たこともなくはなかったが、いわゆるクレームや、極端な言い方で排除を求めるようなもの、不買をちらつかせるようなものは記憶にない。ほかにも連載陣にはオバタカズユキ氏やいしかわじゅん氏など、やはりどう見てもリベラル(左派)、あるいは少なくとも右では全くない、という執筆者がそろっていた。
また『Hanada』になってからも、「右派」とは全く無関係の連載陣が雑誌の脇を固めている。在日韓国人の執筆者や、韓国・中国出身者、その後日本国籍を取得した執筆者も登場している。ある在日韓国人の執筆者は、「自分のように在日同胞に対しても時に厳しいことを書いたり、歴史問題について日本側の言い分を批判しなかったりする私のような書き手は、リベラルの媒体では書かせてもらえない」と言っていた。一定の方向性というのはあるが、必ずしも「画一的な保守・右派だけの排他的な雑誌」ではなかったのだ。
読者は、様々な感想を抱きつつも多様な執筆者の、多様な意見が掲載されている状態を支持していた(少なくとも許容していた)のである。むしろこれこそが、雑誌の醍醐味だろう。
「反朝日新聞」は雑誌の矜持
それにしても、なぜ朝日新聞をこうも目の敵にするのか。創刊初期の朝日新聞批判特集のタイトルをいくつか並べてみても、〈朝日は腐っている!〉(2005年11月号)、〈許すな! 中国と朝日〉(2006年2月号)、〈朝日新聞の大罪〉(2008年9月号)と穏やかでない。
これは花田編集長が文藝春秋社に所属していた頃からの考えに基づく「雑誌は大メディアのカウンターであれ」という思想から来ている。雑誌の役割は、テレビや新聞のような大メディアが取り上げない視点を取り上げ、疑問を呈すことにある。新聞は社会の公器、社会の木鐸として政権や行政の監視を一つの役割としている。テレビもそうだろう。
しかし新聞やテレビのようなマスメディアには絶大な影響力があり、第四の権力とも呼ばれる。そうである以上、マスメディアを監視する役割を誰かが担う必要がある。雑誌こそがまさに、その役割を担うという認識だ。
「喧嘩を売るなら、でかい相手がいい」と朝日新聞を批判していた面もある。それで実際に訴訟になって大変なことにもなったのだが、これは新聞・テレビが情報発信の多くを担い、ネットメディアやSNS、動画サイトなどが出現する以前の、「大メディア」が存在していた頃の名残でもあった。
その中でも朝日新聞は、特に既存の権威の象徴であった。大勢が読んでいるだけでなく、特に知的エリート層が好んで読み、識者や執筆者として登場するためである。それを庶民の目線から批判するのが花田編集長のスタンスだ。文春時代はそうした視点からの批判であったろうし、『WiLL』になってからは政治的スタンスの異なる保守からの批判という側面をより強めたことになる。
朝日の影響力低下で「朝日批判」も落ち着いた
こうした「色」になるのは、ひとえに読者層に合わせて企画や記事の取り合わせを練っているからに尽きる。花田編集長は、もともと「朝日新聞のカウンター」的な発想は持っていたが、『WiLL』4号目にしてこの企画が大当たりし、「なるほど、保守系の雑誌とはこういう風に作ればいいんだ」という手ごたえを感じたに違いない。
2024年現在、『Hanada』ではしばらく朝日新聞批判特集が組まれていない。連載を含め、毎号なにがしか朝日新聞を突く記事は掲載されているが、トップで朝日特集を銘打ったのは、2019年9月号の〈ざんねんな朝日新聞〉が今のところ最後となっている。
朝日新聞の質が変わり、批判すべき記事、突っ込むべき論調が減ったのも理由の一つかもしれない。あるいは安倍政権終焉以降、特集を組むほどの対立軸がなくなったのかもしれない。安倍政権期という朝日新聞と保守派が激しくやり合った時期を過ぎ、朝日新聞の部数が減って世帯当たりの購読数が0.5部を下回る(つまり朝日新聞を購読している世帯は半分以下になった)ここ数年で最も朝日批判が盛んだったのは、他でもない安倍元総理の国葬儀の賛否をめぐってのものだった。これは実に象徴的であろう。
「週刊誌」の作法でつくったら売れた
それにしても、朝日新聞批判や、2010年代まで多く特集されてきた歴史認識問題、中国や韓国との外交問題などは、先行する保守系雑誌である『諸君!』や『正論』でも長年にわたって取り上げられてきたテーマである。その中で、いくらタイトルがキャッチーだからと言って、それほど他誌との差別化が図れるのかという疑問はある。実際、両誌と一緒に購読している読者は少なくなかった。
ではなぜ、『WiLL』は創刊から数年で、雑誌では異例の増刷が何度もかかったり、公称10万部に達するなど一気に2誌の部数を抜き去ることができたのだろうか。
他誌と違う特徴として、タイトルなどのほかに考えられるものを挙げてみたい。まずは編集スピード。通常、雑誌(特に月刊誌)は特集が決まり、ラインナップとページ数が決まり、台割ができてから動き出すものだという。「という」というのは、『WiLL』や『Hanada』では「校了直前に台割が決まる」ものだったので、他誌が事前に特集も掲載記事もページ数さえも決まった状態で寄稿依頼や取材が始まると聞いたのは、この業界に入ってしばらく経ってからのことであった。
『WiLL』と『Hanada』の場合、発売直後に次号の特集や取り合わせを決める企画会議が開かれる。しかしその時決まったラインナップが、そのまま実現されることはまずない。発売は約1か月後になるわけで、その間、どんな出来事が起きるかわからないからだ。
どの雑誌でも、突発的に重大な事件や出来事が起きた場合には記事の差し替えや特集の組み換えが行われると思うが、『WiLL』や『Hanada』の場合は、それが平常運転なのである。要するに「もっと面白い記事があったら当初の予定など無視してそちらを載せる」「ページが足りなくなれば一部記事は翌月(以降)に繰り越す」のである。これも、おそらく文春時代からの花田編集長のやり方なのだろう、ためらいがない。
以前は1週間から10日前後の終電帰りと最終日の徹夜作業を繰り返していた。2024年現在、花田編集長は82歳となり、さすがに徹夜・始発帰りはしなくなったものの、それでもほぼ毎月、数日間の終電帰りと校了最終日の午前様帰りを繰り返している。汲々とならずに済むよう、作業進行を調整すべきとの声は20年前から絶えないが、「最後の最後まで面白い記事をねじ込むために作業を行う」ためにどうしてもそうなってしまうのだ。