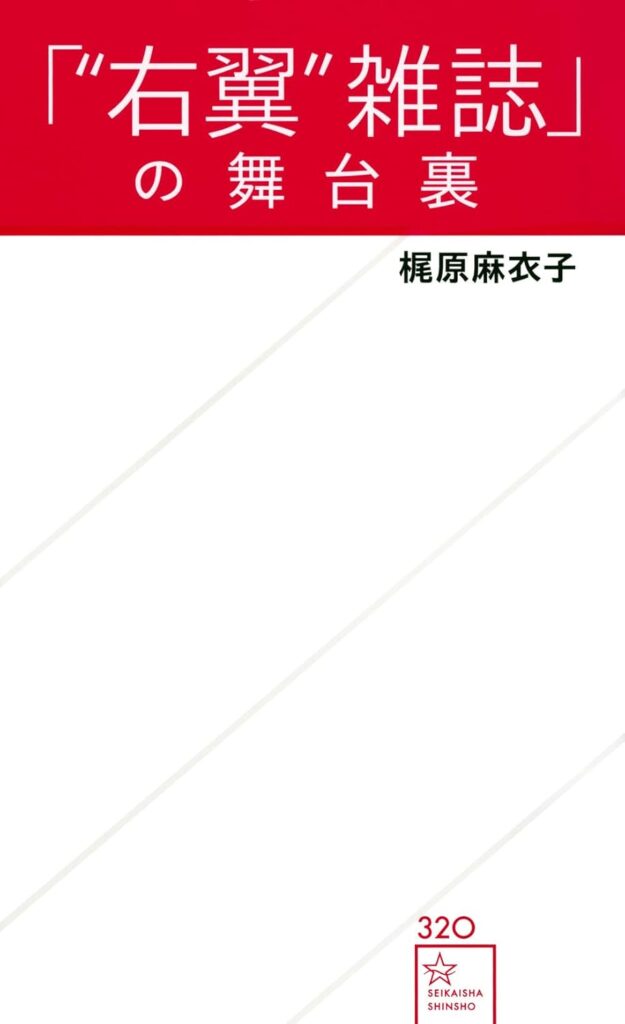自分たちを社会は理解してくれない…“右翼雑誌”『Hanada』『WiLL』元編集者が語る「社会・国家間の溝が深まったワケ」傷ついた、だからやり返す

“右翼雑誌”と呼ばれることもある、『WiLL』と『Hanada』。休刊が相次ぐ雑誌業界の中で、『WiLL』は一時13万6000部(公称)を達成。いかに『WiLL』『Hanada』が部数を伸ばしていったのか。両誌が熱烈な支持を受けたのは、「自分たちを理解してほしい」との切実な思いがあった。両誌の編集部に在籍し、日本の論壇の潮流を見てきたライター梶原麻衣子氏が、これまでの歴史の流れを踏まえた上で、なぜ社会の分断が深まったのかについて考察する。
※本記事は梶原麻衣子著「“右翼”雑誌」の舞台裏」(星海社新書)から抜粋、再構成したものです。
第1回:元編集者が内幕を暴露…“右翼雑誌”『WiLL』『Hanada』の爆売れの理由は「朝日新聞叩き」だった!一時13万部の大人気
第3回:花田紀凱が語る「ヘイト批判への反論」爆売れ保守系雑誌『WiLL』『Hanada』生みの親…WiLLとHanadaの違い
目次
「自分たちの言うことを社会はわかってくれない」と嘆く保守
今でこそ状況はがらりと変わったが、まだ90年代からの空気を引きずっていた2000年後半から10年代にかけて、保守派には「自分たちの意見や立場を、日本社会が理解しようとしてくれない」との思いが色濃くあった。
歴史認識問題にしても、戦前の話となればすぐに朝日新聞などのリベラルメディアは、日本否定の立場に立つ。つまり中国・韓国の側に立つ。そして中韓と一緒に、保守派の主張に圧力をかける。それによって、保守派は「押し込まれている」「常に劣勢に立たされている」との思いを抱いていたのだ。
かなりさかのぼるが、1969年に『諸君!』が創刊された当時、保守派の人々は「(自衛隊に対する迫害など)何かおかしいと思っていた」「解せない」状況があったが、「保守というより反左翼で、左翼的偽善をこっぴどく叩く」「左翼伝染病に対する免疫」ともいうべき『諸君!』の誕生によって「ようやく自分たちの思想的受け皿ができた」と感じたという。
しかしそこから40年以上経った2010年代でも、社会にはまだ「反戦前」的な左翼の名残が息づいていた。もちろん戦争には反対であるが、「戦争反対」と言い、日本が軍事的に無力であればアジア地域の安定が保てるというような時期は既に過ぎている。自衛隊は違憲だとする憲法学者がいて、国際貢献であっても自衛隊を海外に出すことはまかりならず、武器も使用させてはならない。ナショナリズムや愛国心などもってのほかだというのである。
朝日による「愛国心」の否定
2014年3月7日の朝日新聞朝刊一面コラム・天声人語は、安倍政権下で検討されていた道徳教材の内容について、次のように書いている。
〈「日本人としての自覚」「我が国を愛し発展に努める」といった記述に、ふと立ち止まる。食事中に砂粒を噛んだような感じがする〉。
確かに「愛し」というような言葉遣いに違和感を覚えることはあるだろうが、「砂粒を噛んだような感じ」となると相当の不快感で、食事だったら吐き出しているだろう。
同年9月6日、朝日新聞の社説は、国連人種差別撤廃委員会が日本のヘイトスピーチに対する勧告を出した際に、次のように書いている。
〈「誇りある日本国民として恥ずかしい」「日本人としてやめなければならない」という物言いにも違和感を覚える。差別を受け、恐怖を感じている被害者への視点が抜け落ちてはいないか。
安倍首相は国会でヘイトスピーチについて「他国の人々を誹謗中傷し、まるでわれわれが優れているという認識を持つのは全く間違い」と述べた。 「日本人の誇り」の強調は、そのような間違った認識を助長することにつながりかねない〉
こうした状況下では、「歴史の光と影の両方を知る」などと言っていては立ち行かない。実際にはそうあるべきなのだが、影が強ければ強いほど、光に目を向けさせたい側はより強い表現になるしかない面もあったのだ。朝日新聞側からすれば、右派の安倍政権下で「愛国心」が高まることに危機感を覚えたからこそ、より強く否定せねばという意識が働いたのだろう。しかし一部の人々はそうしてより強く押さえつけられた(と感じた)ことで、余計に愛国心を刺激されることになったというわけだ。
中国・韓国の愛国心が日本の愛国心を育てた
しかも2000年代に入って情報環境も大きく変わり始め、中国・韓国もそれぞれ愛国心を発露する模様が日本にダイレクトに伝わるようになった。その愛国心が「反日」を基礎にしているとなれば、突き付けられた自分たちは何も言い返さなくていいのか、となるのは自然の流れであろう。確かに戦前、両国に被害を及ぼしたことは認めても、だからと言って、一生謝り続けるのか。謝る以外の関係性は持ちえないのか。そうした考えを持つ人が出てくるのも当然だったと考える。
だからこそ、2015年の安倍総理による戦後70年談話で、「孫子の代へ謝罪の宿命を負わせない」と述べたことに対する保守派の心境は、「安堵」だったのである。
北風と太陽の寓話ではないが、戦前の日本について是々非々の立場を取る太陽政策で臨んでも、相手も同じように「確かに戦前の日本にも言い分はあるでしょう」などと言わないことは火を見るより明らかだったので、やはり北風を吹かせるしかない。
中韓に対してだけでなく、これは国内のリベラルに向けても声を上げていたのだが、「こちらの思いを知ってくれ」「韓国や中国に言われっぱなしで、俺たち日本人の誇りはどうなるんだ」と北風を吹かせれば吹かせるほど、相手側も頑なになっていった。しかも北風を吹かせれば吹かせるほど、保守派が本当に言いたかったことから話がずれていったのも確かだった。
「時代」が変える、慰安婦問題の認識
歴史認識問題の中でも一、二を争うテーマだったのが南京事件と慰安婦問題だ。南京事件にまつわる「百人斬り」報道では、戦意高揚報道に協力した日本軍の兵士が罪を問われ、戦犯となり処刑されることになった。当時の記事をもとに、今なお中国の「南京大虐殺記念館」には二人の写真が掲示されている。
「百人斬り」ご遺族の向井千惠子さんの話を聞いた筆者は、父が自衛官であっただけに他人事とは思えなかった。国のために戦って、良かれと思って戦意高揚記事に協力したら、負けたとたんに処刑されたのである。先の戦争全体の評価を変えてほしいわけではない。しかし部分的にでも、戦後長く無念の思いを背負って生きることになった人たちに寄り添うことはできないのか。
また南京事件は、被害者の数についても議論になっていた。「歴史修正主義」と言われる側も、当初は事件そのものを全否定するつもりは(恐らく)なく、あまりにも中国が多く見積もる犠牲者数や残虐行為について「(中国や朝日新聞が言うような)南京大虐殺は存在しない」と言っていたのである。だが、強く打ち返そうとの意が先に立ち、議論から次第に( )の部分が欠落して行った結果、事件そのものを全否定する人たちも出てきたのであった。
慰安婦問題では、当初は強制連行や連行の規模などが争われており、保守側としては「いくら何でもトラックに乗せて無理やり連れて行ったわけではない」「さすがに20万人は多すぎる」というものだったが、論を展開している間に時代が下り、価値観が変わってきたために慰安婦問題における女性の尊厳の面が強くなっていった。すると、「そもそもそんな施設を設けただけでも反省に値する」というような話に展開していくことになる。
当時の韓国人慰安婦の中には、日本の兵隊と恋をしたとか、買い物を楽しんだ、あるいは「親に家を買ってあげたくて慰安婦に志願した(が、終戦で給料の受け取りがうやむやになった)」といったことを書き残している人たちもいた。しかし「女性の尊厳の問題としてあり得ない」と言われてしまえば、彼女たちの口はふさがれたも同然になる。
「あっちが言うからこっちも…」がエスカレート
この頃の編集後記に、筆者は「望まずに慰安婦になった方は本当に気の毒。しかし貧しさから親のためと慰安婦になった人まで性奴隷扱いでは浮かばれないのでは、その一言が傷をえぐっているのでは」などと書いていた。
こうなってくると、慰安婦問題で少しでも巻き返しを図りたい右派側は、論点をずらしてでも、わずかでも失地を回復せんとすることになる。当時その必要があって女性たちにお願いしたことであるというような姿勢は全く消えて、「たんまり儲けたくせに、まだたかるのか」「慰安婦じゃなくて売春婦だろう」というような、単なる罵倒に発展していく。
歴史認識問題に端を発する韓国批判がエスカレートしていたことは確かで、しかしそれが国内の在日韓国人を傷つけるものになるというところまでは考えが及んでいなかった。「あっちも言っているのだから、こっちも言い返すまでである」という国別対抗戦の様相こそが、当時の認識上の構図だった。
この「傷ついた人がいる」問題は厄介で、それを言ったら日本にも歴史認識問題や靖国問題で中韓から差し込まれて「傷ついた人がいる」。もちろん戦争で被った被害とは比べ物にならない。しかし、『WiLL』編集部に「一体いつまで、朝日新聞や中国・韓国は私たちの祖父を悪者にすれば気が済むのか」と泣かんばかりに電話をかけてきた読者もいたのである。