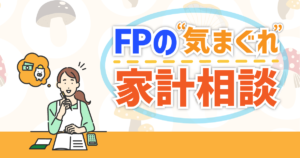第1回 ライフプランを立てたら人生が変わる

はじめまして。私はファイナンシャルプランナー(FP)として十数年にわたり家計相談に携わっています。
家計相談を通して、いろんな人生の分岐点に立ち会ってきました。
この家計相談では、家計と向き合い、お金の問題を解決して、どちらか一方に進もうと決心なさった相談者(読者)の皆さんの気持ちを受け止め、夢に近づくためのヒントをお届けしていきます。
目次
ファイナンシャルプランナーになった理由
私自身の分岐点は失業でした。
出版社で一人前の編集者として仕事を任されるようになった頃、出版不況とバブル崩壊で会社がなくなりました。
編集者として転職したくても思うような求人はなく、消去法で選んだのが生命保険の営業でした。事務は苦手。営業なら、著者やさまざまな関係者と折衝する編集者の仕事に通ずると思ったのです。
就職した保険会社は、法人契約の経営者保険がメイン商品。社長や経理担当、顧問税理士と話をしなくてはなりません。
当時は金融・経済の知識はゼロに等しく、毎朝経済新聞を読み、会社の提供する金融・財務の通信教育や生保業界の育成制度を使い必死に学びました。とにかく食べていかなくてはならなかったからです。
好きで就いた仕事ではありませんでしたが、お金を通して社会や人の生き方を眺めると、今までと違う世界が広がるのが面白くなりました。しかし残念ながら、生保の営業は一生の仕事として考えることはできませんでした。
ここで習得したことを活かして何かできないかと探っていたとき、マネー雑誌にFP養成講座の小さな広告を見つけました。金融業界で一部の社内資格の位置付けだったものを、「貯蓄から投資へ」とお金の流れを変える、その営業の最前線に立つ共通資格としてFPを育てようという動きが始まっていたのです。
必要なのは「お金の知識」と「情報」と「ライフプラン」
私がFPとしてやりたかったのは、社会保険や税制を含め生きていくうえで必要なお金の知識の教育啓発でした。仕事のために勉強する中で、自分の加入している年金制度や払っている税金の仕組み、契約している保険の中身をまるで知らなかったことに驚き、これは誰もが学ぶ必要があると感じたからです。
しかしFP資格を取って独立したものの、当時は一般にはまだFPという存在が知られていない時代です。名刺交換をすると、金融関係の怪しげな仕事をしている人、と見られてしまいました。
それでも「お金の教育が必要だ」と考えて根気強く話をしていたら、次第に理解者が現れて、講師として話す機会をもらったり、商店街の人たちと子どものお店体験イベントの企画をしたり、地元新聞に連載もさせてもらいました。
ある時、その記事がきっかけで学生に「金融経済入門」の授業をすることになりました。
半年間の授業の後、「専業主婦が夢だったけれど子どもができても働こうと思う」と言ってきた学生がいました。話をよく聞くと「人生にはとてもお金がかかるのが分かった。でもどうせ働くならお金のためだけでなく、やりがいのある仕事を見つけたい」と考えを改めたようです。
この授業の最後にライフプランを立ててもらったのですが、この時「ずっと専業主婦を続ける」というライフプランを立てる生徒がいても、私は何も言わなかったでしょう。専業主婦では受け取る年金が少ないことや、子どもの教育費がかかることなど理解し、何より家事育児に専念することが生きがいなのだと考えた末の結論ならば。
しかし過去にはリーマン・ショックがありました。そして新型コロナウイルスによるパンデミックが起き、今も世界のどこかで紛争が絶えません。気候変動が生活に大きな影響を与えるという予測もされています。どんなに注意深く生きていても、将来大きな困難に見舞われる可能性があります。
その時、何の準備も心構えもなしに直面したら取れる手段も限られてしまいます。もし起きる事態を予測していたり、少しでも備えがあったりすれば、困難への向き合い方、乗り越え方も違ってくるでしょう。
未来は不確実なことが多いからこそ、お金の知識・情報、そしてライフプランが役立つのです。
ライフプランには2つの目的がある
いやいや、こんな不透明な時代に10年先20年先のことなんか考えられないよ、という声もあります。
でも人は老い、いつか働けなくなります。
自分は70歳までしか生きないと主張しても(実際、そういう相談者はいます)、70歳の人の平均余命は男性でおよそ16年、女性でおよそ21年(厚生労働省「令和2年簡易生命表」)あり、100歳までとは言わなくても90歳まで生きると考えるのが現実的です。
また子どもが生まれれば、家を建てたくなり教育費がかかるようになります。
ライフプランを立てる目的の一つは、今予想できるリスクを洗い出してそれに備えるための準備をすることです。
例えば老後資金が不足するならiDeCo(イデコ)を始めたり、大学進学のために子ども保険を契約したり。もし何も考えていなかったら、その時になって進学を諦めるか、ローンを組まなくてはなりません。
もう一つの目的は、その人にとっての目標実現のためです。
例えば、独立起業を希望しているけれど、今は子どもが幼く、マイホームも欲しい。
少し欲張りな希望ですが、ライフプランを立ててみると、時間をずらしたり予算を調整したりして、「起業」と「家族の生活」と「マイホーム」という3つの夢を諦めることなく実現できる可能性は高くなるでしょう。
「ネコを飼いたいけれど、シングルだから老後のお金も貯めないといけない」というある相談者は、日々の家計を見直し、貯蓄とペット費用を優先して予算を組んでライフプランを作成し、望み通りネコと生活できるようになりました。
ライフプランは夢との距離を縮めるツールともいえます。
◇ ◇ ◇
次回からは、「人生100年時代」のライフプラン、マネープラン作りの参考になるよう、これからの働き方やNISAの活用術などを取り上げていきます。