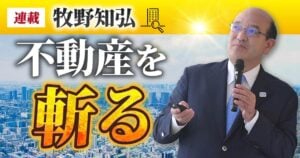いよいよ始まった円安「倒産連鎖」…これから危ない3業種

際限のない円安で食料品の値上げも止まらない
円安が止まらない。
2022年4月28日に東京外国為替市場で1ドル=131円台に円が下落、その後も120円台後半を推移し、6月6日時点でも130円台をキープしている。円が130円台まで下落するのは、実に約20年ぶりのことだ。
もちろん円安の影響には一長一短あり、海外資産を持っている場合はその価値が相対的に上がることになる。また、海外で日本製品が安くなるため、輸出産業の業績が伸びやすいなどメリットもある。
だが資源に乏しい日本では、大半を輸入に頼っているエネルギー資源の値上がりは避けられない。食物も同様で、カロリーベースでの食物自給率が4割を切っている現状では、円安の影響が直接、食卓に響く。実際、連日、ニュースでは輸入品への円安影響による物価高騰の話題が報じられている。これまで「価格を上げず、内容量を減らす」というシュリンクフレーションを続け、俗に「ステルス値上げ」などと揶揄されてきた日本の食品メーカーの対応も、ついに表立った値上げをせざるを得ないほどの限界が来た、ということだろう。
今後、危惧されるのが「円安不況」と、その先にある「円安倒産」だ。すでに4月の段階で、「円安」関連倒産が発生している。東京商工リサーチによれば、福岡県の貿易商社が新型コロナ感染拡大に伴う業況悪化に加え、円安で価格が上昇した商品の輸入制約もあり、破産を申請した、という。
原油価格の高騰に加え、円安進行で原材料や資材などの価格上昇が続けば、中小企業を中心に「円安倒産」の連鎖が起きないとも限らない。デフレ続きの日本では、仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁するのは難しい。だからこそ「ステルス値上げ」でしのいできたのだ。ましてや中小企業の場合、仕入コストの負担増が収益悪化を招き、経営に大きな打撃を与えかねない。
さらには、ウクライナ情勢の悪化と情勢の長期化で、ウクライナが世界的産地となっている小麦の輸出が滞り、関係する食料品の値段が高騰している。ようやくコロナ禍が落ち着きを見せ、物流もコロナ前の平常運転に戻るかに思われていただけに、関連する業界の暗雲は晴れないどころか、ますます厚みを増す可能性さえある。
円安・物価高を前に何もできず、円安連鎖倒産が迫る
「物価高に対応できていないという声は大きい。不信任に値する。最終的な判断の段階に来ている」
円安が続く六月上旬にこう述べたのは立憲民主党の泉健太代表だ。ウクライナ危機と共に到来した「円安」の波が、日本経済を襲っている。それゆえの「内閣不信任案提出」だが、国民の反応は渋いものだった。
だが、岸田政権が円安・物価高に対応できていないことは火を見るより明らかだろう。岸田文雄首相は5月26日の衆院予算委員会で、現在の円安事態に対し「一般論として事業者、生活者には物価の引き上げで大きなマイナスになる」と言及しながら、一方で「円安は輸出企業や海外に資産を持つ企業には追い風になる」とも発言。さらには「円安が大きな議論になっているが、外国から観光客が来れば円安は追い風になる」と述べ、6月10日から始まる外国人観光客の受け入れを再開するにあたり、「円安はむしろ強み」であると見ていることを明らかにした。
だがこれは「円安倒産」におびえる輸入業者、輸入によって成り立っている食料品メーカー、繊維業者などにとっては怒りすら覚える発言だろう。
東京商工リサーチが2021年12月に実施したアンケート調査によれば、「円安が自社の経営に『マイナス』である」と回答した企業は実に4割に上る。業種別でも、「繊維・衣服等卸売業」(77.5%)、「食品製造業」(71.0%)、「家具・装備品製造業」(70・8%)の3業種は7割以上が「マイナス」と回答するなど、その影響の大きさを物語っている。(https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220419_02.html)
一方、「円安が経営に『プラス』と回答した業種」も宿泊業、業務用機械工具製造業などあるにはあるが、「プラス」と回答した割合は最高でも16%と、「マイナス」と答えた企業とは60%近くも差がある。岸田総理が「むしろ強み」と胸を張るほどには、宿泊業の現場は円安に期待しておらず、プラスだと考えている割合も2割を切っている。こうした実態を、岸田総理はどこまで把握しているのか。
国際社会・市場が「日本を見捨てた」と言える理由
これまで、国際社会に危機が起きると円が買われ、円高になる現象、つまり「危機の円買い」「危機の円高」が続いてきた。日本経済自体は低成長が続いている2000年代に入ってからも、2008年のリーマン・ショックはもちろん、日本のみが危機に陥った2011年の東日本大震災時にも、円買いが起こり、1ドル=70~80円台という、文字通りの円高が一気に進んだ。
その理由は、〈世界経済への不透明感が強まると、投資家がリスクを避けるため、株や海外通貨を売り、世界一の対外純資産国の日本の円にマネーが集まるから〉(2022年3月23日付、朝日新聞)とされてきた。
しかし今回のウクライナ危機では「危機の円買い」現象は起きなかった。こうした変化の理由として、原油高による日本の経常収支の悪化、日本企業による海外資産の保有状況の変化、アメリカの利上げに対し、低金利政策が続く日本の金融政策の影響などが挙げられている。
だが、より深刻な理由として考えるべきは、日本経済に成長の見込みがない、と市場から判断されているからではないか、という点だ。
神話は崩れた
今回の円安現象に対し、日本では「これまでは『危機の円高』だったのに、今回そうならなかったのはなぜ?」という疑問に答える解説記事が多く書かれた。これは多くの読者(日本人)が「なぜ?」と疑問を抱いたからこそだが、ここに日本人と市場の意識ギャップがある。