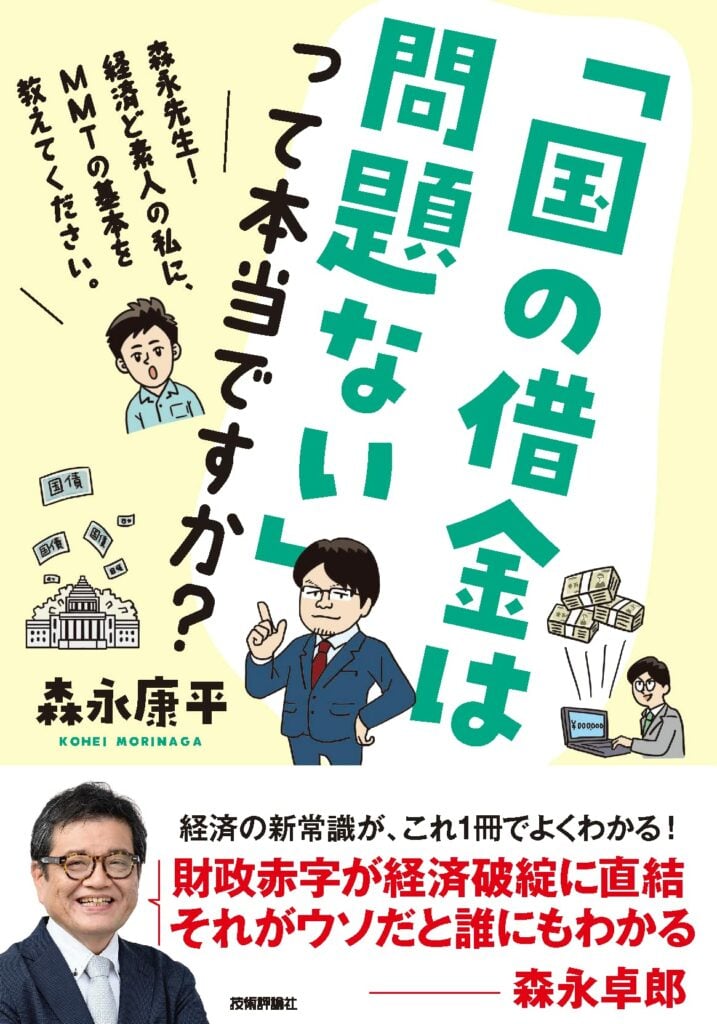瀕死の日本に増税は本当に必要なのか? 森永康平が経済ど素人にモノ申す「国の借金は円の発行履歴でしかない」

「国の借金は将来に負担を先送りしているだけ」――。このような言葉を聞いたことがある人も多いだろう。今、岸田総理が増税議論を活発化させているが、株式会社マネネCEOで経済アナリストの森永康平さんは「借金はいまの2倍以上になったとしても何の問題もない」と断言する。銀行がお金を生み出す仕組みや、国の借金がどれだけ膨らんでも許容される理由を、学生との対談形式でわかりやすく解説する。全3回中の2回目。
※本稿は森永康平著『「国の借金は問題ない」って本当ですか?〜森永先生!経済ど素人の私に、MMTの基本を教えてください。』(技術評論社)を抜粋、編集したものです。
第1回:岸田総理「令和の大増税」の悲劇…森永康平「国の借金がいくら増えようが、財政破綻はしません」
第3回:日本は度重なる増税で低成長国家になってしまった…「政府は国民からカツアゲする金を減らせ」
▽登場人物
森永先生:大学で経済学を教える先生
中村くん:日本経済と自身の将来に不安が絶えない大学4年生
お金は「貸し出した瞬間に生まれる」
中村:先生、“国の借金” である国債は、民間銀行が日本政府から購入するんですよね。では民間銀行は、そのお金をどこから調達したのでしょうか?
森永:なるほど、もっともな質問です。その前に中村くん、国債の売買はどんな種類のお金で行われますか?
中村:日銀当座預金ですね!
森永:そうです。日銀当座預金の発行者は誰ですか?
中村:ええと……日本銀行ですね。
森永:その通り。日銀当座預金も日本銀行が発行者ですから、民間銀行が国債を購入するお金も日本銀行から供給されるのです。
中村:なるほど。それでは、日本銀行は日銀当座預金に入れるお金をどこから調達するんですか?
森永:結論から言うと、調達していません。「信用創造」という機能を用いて、お金を貸し出した瞬間に新たにお金を生み出しています。
中村:貸し出した瞬間にお金を生む……?どういう意味ですか?
森永:中村くんは借金をしたことがないようなので、身近な借金の例で見ていきましょうか。
中村:身近な借金の例? そんなのあるんですか?
森永:たくさんありますよ。例えば住宅ローン。自分の家を買うとなると、3000万円くらいは必要になったりしますよね。でも3000万円を一括で支払うケースはあまりなく、ほとんどの場合は住宅ローンを組むことになります。つまり、家を買う人に銀行が3000万円を貸してあげて、そのお金で不動産会社に支払い、家を買った人は何十年かかけて借金を返していくんです。
家を買った人をAさんとしましょう。Aさんに貸してあげる3000万円を、銀行はどこから調達しているでしょうか?
中村:そりゃあ銀行が預かっているお金からじゃないんですか?
森永:そう思いますよね。しかしそれは間違いなんです。「どこから調達しているか?」と聞かれたら、「どこからも調達していない」というのが答えです。ではどのように貸し出しを行っているか? 答えは、預金者の通帳に「30,000,000」と記入しているだけです。銀行とは、預金者の預金データに数字を記帳するだけで、お金を生み出す能力を持つ機関なのです。
中村:先生、さすがに意味がわかりません。そんなことできるわけないでしょう!?
森永:疑う気持ちはよくわかります。しかしこれは実務として行われていることです。銀行が貸し出しによってお金を生み出す行為を「信用創造」と言います。
1円もなくてもお金は貸せる
森永:創立1年目で、まだ自行に口座を開設している人がいないため、預金が1円も集まっていない銀行があるとします。その銀行は、貸し出しを行うことができるでしょうか?
中村:で、できるんですか?
森永:できますし、実際にやっています。
中村:そうなんですね……。どうして銀行はそんなことができるんでしょうか?
森永:これは銀行業の成り立ちを学ぶことで仕組みが見えてきます。中村くん、世界ではじめての銀行って、何年にどこにできたか知っていますか?
中村:いえ、わからないです。
森永:1694年にイギリスで生まれた「イングランド銀行」が世界で最初の近代銀行だと言われています。当時のイギリスは、現在とは違い金本位制でした。つまり、金貨がお金として流通し、その金貨の中に金(ゴールド)がどれだけ含有されているか、という基準でお金の価値が決まっていました。
中村:「ソブリン金貨」ですよね?
森永:その通りです。いつの時代にも裕福な人はいるもので、大量に金貨を持っている資産家が一部にいました。当時のソブリン金貨は直径2cm程度の大きさでしたが、大量に持つとやはり保管場所に困ります。
そこで、金貨を預かる金庫番のような仕事を始めたのがゴールドスミスでした。もともとゴールドスミスは金細工職人で、金貨を作る組織でしたから、その金を守るセキュリティもしっかりしていたのです。
金貨を預かったゴールドスミスは、代わりに預かり証を手渡していました。「あなたからは金貨〇〇枚を預かっています」という証書ですね。
中村:先生、知ってますよ。その預かり証が次第に人々の間で流通して、お金の代わりになって、買い物の時に預かり証で取引されるようになったんですよね!?
森永:おお、冴えていますね! その通りです。これが現代における紙幣の始まりとも言われています。自らが発行した預かり証がお金として流通している様子を見たゴールドスミスは、次第に金貨を持たない人にも預かり証を発行するようになりました。
中村:どういうことですか?
森永:「近い将来、必ず金貨を稼いで持ってきます。だから今ここで預かり証を貸してください」という人がいたので、その約束を取り付けて、金貨を持っていない人にも預かり証を発行したのです。さて、この行為をなんというでしょうか?
中村:え……あ、借金ですか!?
森永:正解です。「将来必ず返すので、いまお金を貸してください」という約束は、まさに借金そのものです。「銀行がお金を生み出した」ことは現在と変わりません。つまり、信用創造と同じことなのです。
ゴールドスミスが考案した銀行業の最大のポイントは、金貨を預かったことではなく、元手もなしに預かり証を発行することで、それが新たなお金となり、紙幣を流通させたことにあるのです。
国の借金はただの発行履歴
森永:ゴールドスミスの話を、現代の銀行業に当てはめてみましょう。ゴールドスミスがもちろん銀行です。預かり証は現代の銀行預金で、預かり証の発行は信用創造による銀行預金の増加と言えます。預かり証による買い物は、銀行振り込みによる買い物ですね。
中村:とはいえ、金貨以上に預かり証を発行してしまったら、交換に対応できなくなるのでは? そしてそれは現代の銀行でも同じなのではないですか? ってことはやっぱり現金が必要なんじゃないですか?
森永:鋭い質問です。たしかにゴールドスミスが預かり証を大量に発行できたのは、「すべての人が同時に金貨の引き換えに来ることはない」ということに気づいたからでした。仮に預かり証を持っている人すべてが「金貨に交換してください」と集まっていれば、その要求に答えることができず、銀行業は成立していなかったかもしれません。
しかし現代の銀行では、仮にすべての国民が銀行預金から現金紙幣への両替を求めたとしても、時間をかければその要求に応えることができます。そのため、「やっぱり現金が必要なのでは?」との問いには「No」と答えることになります。
中村:ちょっと信じられないです……なぜでしょうか?
森永:17世紀のイギリスと現代の日本の違いは、金本位制と管理通貨制度です。金本位制では、作ることができるお金の量は金(ゴールド)の量に制約されます。一方、管理通貨制度では、国内でモノやサービスを生産する能力が貨幣発行の制約になります。「貨幣」とは、本書ではお金の総称で、現金紙幣と硬貨の発行者は……もうわかりますよね。
中村:金貨はもちろん現金です。現金紙幣が日銀で、硬貨が日本政府です。
森永:大正解。つまり、民間銀行が保有する現金以上に、預金者から現金への両替要求があったとしても、日銀や政府が必要な分だけ貨幣を供給してその要求に応えることができます。
さて、「日本銀行は日銀当座預金に入れるお金をどこから調達するんですか?」という最初の質問に戻ります。結論から言うと、日銀当座預金も、日本銀行の信用創造によって、口座に数字を打ち込むだけで生まれています。
民間銀行が所持している国債は、日本銀行が買い取ります。買取の際には、日銀当座預金の数字を増やすだけで信用創造を行うため、原資は必要ありません。そして日本政府は、国債で調達したお金を使って支出し、その支出は民間の資産になります。つまり……。
中村:国債発行によって、世の中にお金が増えている……?
森永:その通りです。“国の借金” を発行することによって、民間の資産が増えるのです。そして “国の借金” は政府預金と日銀当座預金を介して取引され、そのお金が民間に出回ることはありません。また日銀当座預金は、日本銀行が貸し出しのみで作ることができるお金です。
つまり “国の借金” とは、日本政府による貨幣発行のこと。“国の借金” 1200兆円とは、これまでに日本政府が発行してきた貨幣の履歴にすぎないのです。“国の借金” が2050年には2000兆円を突破していても不思議ではなく、かつ何の問題もありません。
中村:あんなに「やばい」って言われていたものが、ただの貨幣発行の履歴だったってことですか……?