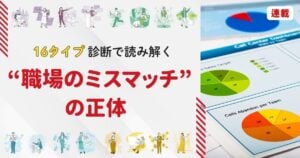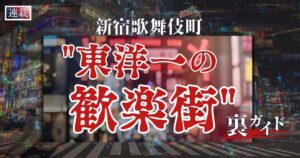国民食サイゼリヤへの「異論を徹底排除」…サイゼ教信者たちの”貧困正義感”の正体――『空気の研究』から読み解く

サイゼリヤ問題。それは批判派と擁護派との果てしないバトルの舞台
SNSで定期的に燃上する話題といえば、サイゼリヤ問題である。
炎上の経緯も、誰かがサイゼリヤを酷評するとその倍以上の擁護意見が湧き、批判者は打ち首獄門の勢いで吊し上げられる。その渦中で当のサイゼリヤは、まるで神社仏閣のように無言で佇み、神聖性をさらに高めていく。毎回、ほぼこの繰り返しである。
サイゼリヤを批判すると大火となる理由は、利用者の層の厚さにあるということで既に結論が出ている。老若男女、家族、恋人、友人、お一人様、それぞれがサイゼリヤにそれぞれの「ストーリー」と思い入れを持っているのだ。
擁護派と批判派のあいだで、「正義」と「感情」が対置関係になっていることも延焼の要因だ。擁護派はサイゼリヤの企業努力、経営手腕を肯定し正義と捉え、「安くて美味しい、好ましい」という「感情」を持つ。
一方で批判派は「低品質、貧しい、本場の味ではない」という批判材料を掲げ、企業努力については「労働者の過剰な搾取」といった恨みに似た感情を向ける。このような対立する正義と感情が火をくべ合い、燃え広がってゆく。
そんななか、最近もとあるツイッターアカウントが「実際の話、『サイゼリヤで満足』してるような感覚は、まぎれもなく『貧しい』んだということは、忘れないようにしたいね。これは、お金や味覚の問題に限らず。(あそこが「安い」のはともかく、「うまい」ということになっているのが、個人的にまったくわからんが)」と発言したところ、著名な料理研究家らまでが参加し、当該ツイッターアカウントに膨大な数の批判が集中した。
サイゼリヤへの深い「信仰心」がもたらす呪術的情況、空気の異質さ
当該ツイートの前後関係を指摘する声もあるが、わざわざそこまで調べる人は少数だ。また、「貧しい」と言われたところで現状どうすればよいのかという反発心もあったに違いない。だが特に食、なかでもサイゼリヤへの深い「信仰心」がもたらす呪術的情況、空気の異質さは類例を見ない。
そこで日本人の同調圧力の正体を喝破した名著、「空気の研究」(山本七平)の一部からサイゼリヤと炎上の関係を読み解いてみたい。
山本氏は本書で、「空気」が醸成されるいくつかの条件を挙げている。
1:サイゼリヤを取り巻く「情況倫理」
「空気の研究」では、旧日本軍の特攻隊強要やリンチなどを例示し、尋常ではない情況で狂った倫理観に支配されてしまった人々が後に「あの情況では仕方なかった」と述べ、正当化する現象を「情況倫理」と定義している。
さらにSNS上の情況倫理は、それぞれの “ムラ”(肯定派・否定派)における実力者(インフルエンサーなど)のお墨付きを得ることで強化される。SNSではしばしばこうした “ムラ” どうしの情況倫理のパワーゲームとなるが、いかなる場合においてもサイゼリヤが圧勝する理由は何か? それには「感情移入の絶対化」が関連している。
2:サイゼリヤへの感情移入の絶対化
前述のとおり、サイゼリヤの利用者層は幅広く、それぞれの感情移入が存在する。山本氏は日本人が善悪の基準を下す際の思考過程の特徴として、「感情移入の絶対化」を挙げている。
感情移入の絶対化とは、思考と現実、感情と論理、そして自他が渾然一体となり、自分たちが感情移入したものこそが絶対的に正しいという感覚に陥ることを指す。
山本氏自身の言葉によると「そういう状態になることを絶対化し、そういう状態になれなければ、そうさせないように阻む障害、または阻んでいると空想した対象を、悪として排除しようとする心理的状態」。
このような感覚が、サイゼリヤ批判を圧殺する原動力となっていることは間違いないだろう。
3:サイゼリヤを取り巻く、「空気」と「水」の関係
さらに山本氏は、空気には対となる「水」が存在すると説く。
「水」はつねに社会に存在する曖昧な「空気」を霧散させ、現実に引き戻す役割をしてきた。山本氏は、この「水」の連続性によって日本社会の正気が保たれてきたというのだ。
当該ツイートもまさに「サイゼリヤ崇拝」の空気に冷や水を浴びせるものであり、その指摘はまったくの間違いとも言い切れない。「味覚に限らず」と言うとおり、現在のすべての経済活動の根底に「貧しさ」とそれに伴う搾取が存在するのは紛れもない事実である。
それにもかかわらず、圧倒的な数量の批判に晒されてしまったのはなぜか? それは、水には空気を根本的に消す効能がないからであると山本氏は説いている。水は「雰囲気」や「空気」を壊すことができても、空気の裏にある「本音」にまで影響することができないのだという。
サイゼリヤ創業者「私も含めて、人は『自分が絶対に正しい』と言い切れるほど、たいした存在ではない」
当該ケースの場合は、本音というよりも図星を突いてしまったことが大きいが、問題は、貧しさに対し貧しいと指摘することがはたして有用だったのかという点だ。
ひょっとして、貧しいかもしれないことはわかってはいる。だが、それ以上に満足している。何をか言わんや……というところで、やはり水を差すことしかできなかったのである。何より、サイゼリヤを多く利用するであろう若年層は、日本経済の斜陽を相対的に体感できていない人も少なくない。彼・彼女らにとって「貧しい」というのは、単なる侮辱に聞こえてしまってもおかしくないかもしれない。
ちなみにサイゼリヤ創業者の正垣泰彦氏も自伝で「私も含めて、人は『自分が絶対に正しい』と言い切れるほど、たいした存在ではない。」と書いている(「サイゼリヤ おいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ」日本経済新聞社、P92より)。正垣氏はこの状況をどのように見るのだろうか。
最後に、人の自尊心を失わせるのはコメントの質よりも「量」だ。大量の憎悪が向けられると人は自らを責め、自身の存在を否定するようになるが、それは間違いだ。「炎上」に晒されたことのある人々には、ぜひ心に留めてほしい事柄である。