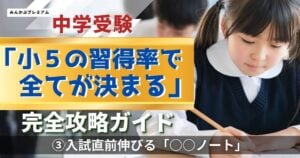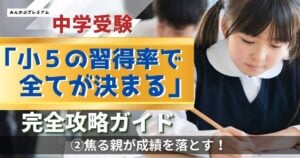「小5の習得率で中受の合否は決まる」専門家…親の向き合い方を変えないと失敗する中学受験の落とし穴
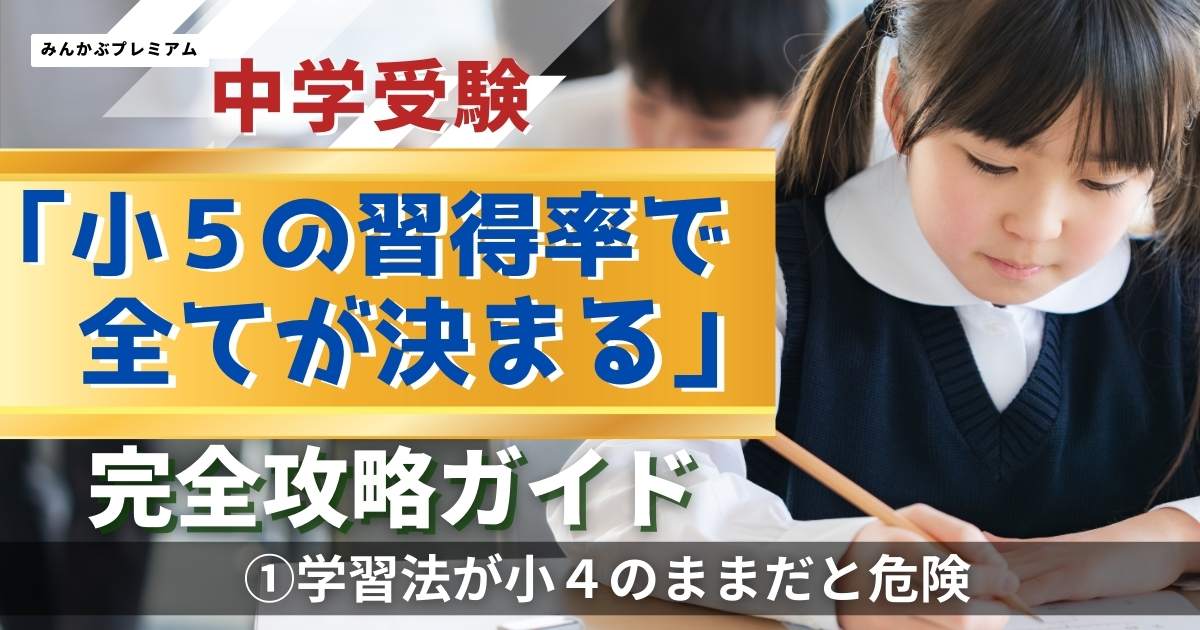
「中学受験は小5が天王山だ」「小5が学ぶ内容も量も多く、一番大変だった」
塾関係者、受験を終えた家庭でそう語る人は多い。
毎年、数多くのトップ校合格者を輩出し、算数・数学教育に詳しいmath channel(マスチャンネル)の滝澤幹氏は次のように語る。
「中学受験で塾通いをする小4〜小6の3年間のうち、小5は新たに学ぶ単元がもっとも多いのです。それぞれの単元の難易度も高く、習得に時間がかかります。受験生にとって大きな試練の場であるのは間違いありません」
中学受験で出題されるほとんどの単元は小5で習うため、その習得率によって志望校の合否が決まると言っても過言ではないと滝澤氏。
小4のうちからやっておくべきことは何か、小5で心がけるべき学習、そして小6で「重要単元のやり残し」を取り戻す方法とは何か。プロの視点から、すぐに役立つアドバイスを語ってもらった。全3回の第1回。
目次
単元のほとんどは小5で学ぶ
まず知ってほしいのが、中学受験塾の出題範囲です。中学受験の算数は、公立中学校で言えば中学2年生の数学レベルが出題されます。
それに対して、塾のカリキュラムは以下のようになっています。
小4:四則演算、基礎的な文章題、簡単な図形問題
小5:小4で習わなかった全単元(割合、比、速さ、規則性、平面図形・・・)
小6:応用問題の習得、志望校対策
小4のうちは、四則演算、つるかめ算のような簡単な文章題の学習がメインで、複雑な思考はそこまで求められません。通塾頻度も低いので、塾や宿題、テストに慣れる期間でもあります。
小6は志望校の過去問演習や実戦的な対策がメインです。
そのため、小5の1年間で受験に必要なほぼすべての単元を、一気に学ぶという構造になっているのです。それに加えて「割合」「速さ」「比」を筆頭に各単元の難易度も格段に上がります。
「これまで通り学習したのに成績が下がってしまった」「何度やっても点数が取れない単元がある」といったことは頻発します。