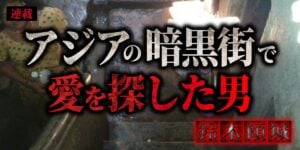好きに国境はない。海を隔てていても心の隔たりはない…「あなたはなぜ、羽生結弦を好きになったのですか?」 『羽生結弦をめぐるプロポ』「好き」(2)

目次
私の芸術観の源泉
こうした芸術観の影響は、間違いなく私の母にあるのだと思う。
その母が三週間前に77歳で亡くなった。大変忙しない日々だったが、ちょうどいい機会だと思い私の好きとみなさんの好きの話をしたいと思う。そもそもが1972年生まれの男の子が舞踏芸術の類を好きになったきっかけは母にあった。
これも書いたが私はそうした芸術を好きと小中高と公言したことなどない。昭和、男子がそういうものを語るには残念ながら社会は追いついていなかった。それでもハイネやコクトー、バイロン、アポリネールなどの詩集を読む分には問題ない中学時代だったが、まあ国語の勉強くらいにしか思われなかったのだろう。
しかし女子のフィギュアスケートで好きを語れば「スケベ」、男子のフィギュアスケートの話をすれば「モッコリ」とまあ、別に揶揄する彼らが悪いのではなくそういう時代だった。これはバレエであれ日本舞踊であれそうだ。
私の母はその日舞の中村流分家家元であり、大衆芸能では浅香光代の直門であった。
彼女は1947年、世田谷の砧生まれ。幼少期から中村流の日舞を学び、16歳のときに和服で砧商店街を歩いていると新東宝映画にスカウトされる。しばらく端役で登場するも新東宝映画はピンク映画色を強めたため嫌で早々に辞めている。1960年代、当時の砧は東宝、新東宝、新東宝映画、大蔵映画、国際放映、円谷特技(円谷プロ)といった映画会社の撮影所やその撮影で華やいでいた。
そうした中で彼女は中村流の分家家元となり、千葉県に嫁いで私が生まれたというわけである。幼少期の応接間に飾ってあった藤娘は襲名時に安田生命ホールで踊ったものである。10代の彼女、私にすればとても母とは思えなかった。
その後は浅香光代の直弟子となり大衆芸能の舞台にも立った。私も浅草にあった稽古場にはよくついて行った。
それでも、私からすれば美しいものを見るのは嬉しいが、目の前の九代目中村福助や二代目市川笑也のような可憐で美しい存在として舞うことは想像もしなかった。母は継がせたかったようだが私にその気はなかった。
いろいろ言う人はあるが、はっきり言って容姿は重要である。舞踏でお金をいただく、評価されるという世界は役者なら変化球のような三枚目や枯姿でも役はつくが舞踏はなんであれ違う。残酷だが現実である。私にそれくらいの自覚はすでにあった。
カタリナ・ヴィットみたいになりたかった
もっとも、見るのが好きで理屈好きの私からすれば好きをあれこれ語ることのほうばかりに興味がいった。どうやら大人たちの反応もよく、あからさまな的外れも美意識の錯誤もないようで、そうした好きの語りを止められることもたしなめられることもなかった。
その母――彼女が日舞はもちろん歌舞伎、新派、宝塚と同様に見ていたのがフィギュアスケートだった。日本人の活躍はそれ以降ほどでなく、あまり放送のない時代、母は冗談交じりに笑いながら言った。
「ああ~、カタリナ・ヴィットみたいになりたかったわ~」
1984年サラエボオリンピック、私は中学生に上がるかどうかだったと思う。それがテレビ放送だったか、ビデオデッキ(父の景気がよく、うちは早くからビデオデッキがあった)だったかは覚えていないのだが、それがフィギュアスケートを意識した最初だった。ロザリン・サムナーズだ、キラ・イワノワだ、アンナ・コンドラショワだのはずっとあとから知っただけで当時は何もわかっていなかった。
羽生結弦に引き継がれたチャレンジ魂
母はどちらかというと恰幅がよく、いわゆる柳腰の舞踊家ではなかった。彼女はどうやらバレエとか、フィギュアスケートといったスラリとした舞踊に憧れがあったらしい。人は誰しもないものねだりなものだが、母の言葉と共に映し出されたヴィットのお姫様のような氷上の姿は鮮烈に記憶している。